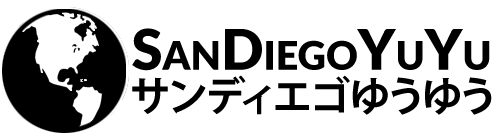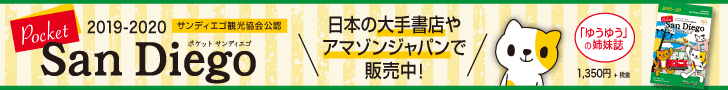語学留学生として米国生活を始めた1982年。当時は貿易摩擦でジャパンバッシングの叫びが喧 (かまびす) しかった。時代背景と相まって、ワシントン州東部のS市は白人が9割を占め、隣り町には白人至上主義団体の本部があった。日本人の存在が珍しいのか、店頭で顧客サービスを拒否されたり、何処からかリンゴをぶつけられたりもした。真珠湾攻撃の日 (12/7) に酔っ払い集団に行く手を阻まれながら難を逃れたことも。語弊があるかもしれないが、私はそんな体験を「新鮮」に感じていた。むしろ白人の本質を知りたかった。S市に暮らす私の大叔父 (great-uncle) からは、収容所体験として「白人は最後に裏切る」と聞かされた。私はこれらの出来事をエッセイにしてクラスに提出したところ、教員ほぼ全員がよそよそしくなった。ただ一人、20代の女性教師 Jさんから驚くべきアドバイスを受ける。「アメリカ市民になるのよ。そこから社会を変えるの」と、真顔で具体的なプロセスを私に細かく説明するのだ。アメリカ的な pragmatism の精神に触れた瞬間。冬の夕刻、大人数の少年少女聖歌隊が私を囲んで「あなたに神のご加護があるように」と賛美歌を合唱してくれた。子供たちの歌声を聞きながら、私は灰色の空を仰ぎ見て、落ちてくる綿雪の冷たさを感じつつ「これもアメリカか」としみじみ思った。在米1年目の冬の記憶。(SS)
冬の記憶

 |
|
 |
|
 |
▽故郷の福島県会津柳津は日本有数の豪雪地帯で、梁 (はり) や柱が黒光りする頑強な我が家には、煙にいぶされた大きい囲炉裏があった。祖母が作ってくれる味噌田楽を囲炉裏の前でほおばりながら、茅葺き屋根の空気穴からキラキラと雪が舞い降りてくるのを眺めるのが好きだった。雪はパチパチと燃える炉の上で一瞬で溶けてなくなった。「紅炉上一点雪 (こうろじょう いってんのゆき) だべ。大人になったら分かる」と、祖母が難しい話を教えてくれた。人間の命はもちろん、 この世に存在するすべてのものは、炉の上の雪のように現れて消えていく。一瞬でなくなる「はかない存在」だ。でも、だからこそ尊い。今、この瞬間、そして、今日という日を丁寧に生きなさい。そうして、明日という日をきちんと迎えなさい。還暦をすぎてようやく、祖母の話が少し分かってきたような気がする。▽雪国の粘り強さは「雪かき・雪下ろし」に由来するような気がする。千葉に移り住んだ我が家では、新天地の快適な気候を「千葉ボケ」と称して揶揄 (やゆ) していた。サンディエゴにも冬はある。でも、最も寒い1月の平均気温は14℃。会津の人にも千葉の人にも申し訳ないような冬だ。朝夕少し冷え込むようになると、すぐに暖房を使い始めるが、お気楽な「カリフォルニアボケ」にならないよう気をつけたいと思う。 (NS)
|
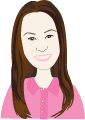 |
短大生のとき、家族旅行で母国の台湾から日本の大阪と京都へ行った。私と二人の妹にとって初めての海外旅行だったので、みんなワクワクしていた。冬の日本はめちゃめちゃ寒いと聞いていたので、暖かい格好で台湾から出発。若かったせいかも知れないが、そんなには寒く感じなかった。当時、日本語を勉強していた私は、台湾で日本語を教えてもらっていた先生から 「大阪の友人に本を届けてくれないか?」 と頼まれた。「もちろんです」と先生に告げた。家族でホテルにチェックイン後、両親から許可をもらい、二人の妹を連れて、梅田駅から目的の住所へ向かった。迷子になると困るから、三人で行き方と道をメモして、いざ “大阪探検” へ! めちゃくちゃな日本語で人に尋ねながら、無事に本を届けた。ホテルへ戻る途中、なんと雪が降ってきた! 初めて雪を見て、雪に触った私たちはとても興奮していた。通りかかった日本人の目を気にせず、ギャーギャー笑って、姉妹三人で楽しく雪遊びをした。あれから35年以上も経ったが、あの日のことは一生忘れられない! (S.C.C.N.)
|
 |
私の冬の記憶は、炬燵 (こたつ) にホットカーペット、みかんに猫。多分、どこの日本の家にもあるであろうこたつは実家では和室に置いてあった。テレビのある居間にはホットカーペットが敷いてあった。暖かいホットカーペットも好きだったが、やはり冬はこたつが一番。私も妹も、普段は和室をあまり使わないのだが、こたつが置かれると、自分たちの部屋から、小説、雑誌、漫画本を持ってきて、そこで寛いでいた。こたつぶとんの上には、こたつ板、こたつ板の上にはお菓子とみかん。傍らには猫が寝そべる。寒い日の休日にこたつでぬくぬくと本を読み、眠くなったら寝ころんで座布団を二つ折りにして枕にし、そのまま昼寝して、起きると夕方が近い。1日を無駄に過ごしてしまったなぁと、ちょっと反省する。こんな記憶が懐かしい。それほど寒くないサンディエゴでは必要ないが、もし、家にこたつがあったらどうだろう。。。こたつに入ったら全く動かない夫と息子に、私と娘が文句を言っている様子が眼に浮かぶ。やはり、こたつ購入はやめておこう。 (YA)
|
 |
北関東に実家がある。冬は東北地方などに比べると積雪量は大したことないが、それゆえに、たまに雪が降ると大変だった。すぐに交通機関が乱れてしまう。東京都内に会社勤めをしていた時、雪が降ると、通勤が命がけに近かった。まず、駅にたどり着くまでが至難の技。待てど暮らせど、バスが来ない、来ない、来ない・・・。仕方なく、父に車を出してもらって駅まで送ってもらうのだが、チェーンを付けても凍った雪道は滑る! 途中、田んぼに落っこちた車や溝にはまってしまった車が数台。やっと電車に乗っても、途中で何度も止まって、なかなか目的の駅に着かない。やっとの思いで出社しても、帰りがまた憂鬱。夜はもっとひどくなるのが分かっているから。電車は、ひどい時は自分の駅のかなり前の駅でストップしてしまい、そこからタクシーで帰らざるを得ないこともあった。タクシー乗り場は長蛇の列。凍える雪景色の夜更けに、いつタクシーに乗れるか分からずに待つ不安。思い返せば懐かしいけど、もう二度と経験したくない冬の記憶。 (RN)
|
 |
|
 |
冬といえば雪。雪といえばスキー、という訳で、私の冬の記憶は、スキーに直結している。高校時代、鳥取県の大山でのスキーが高校の行事にあったが、私はそれをキャンセルして、一人夜行列車で東京へ。初代ジャニーズのミュージカル鑑賞に出かけ、人生初のスキー経験を逃した。次に訪れたスキーの機会は大学時代、友達の誘い。スキー道具を揃え、夜行バスで信州、越後へ。生まれて初めて着るスキー服に胸を躍らせた。が、宿泊先のロッジの余りにもの汚さに耐え切れず、初日はスキーよりも掃除を買って出た。皆がスキーを楽しんでいる間に、一人黙々と掃除をしていたら…あろうことか、スキーパンツがストーブに当たり、お尻の部分に穴が…。替えがあるはずもなく、結果、ロッジ番をするだけのスキーツアーとなった。三度目の悲劇は、舞台が変わってスイス。言わずと知れたスキーの本場である。姉がチューリッヒにいたことで、長年勤めた出版社を辞めて訪れた際、姉家族が出かけるスキー場について行った。見たことないような広〜いゲレンデ。今度こそ初のスキー体験が、スキー人間憧れの場、スイスである。しかし! その美しいゲレンデで転げまくっているのは、周りを見渡せば私一人!!!! ああ、I don't likeスキー、But WE スキー (Whisky) (^_^)。 (Belle)
|
 |
|
 |
寒いのは苦手だから、冬に旅行するのはイヤなんだけど、実家への帰省は真冬の12月末〜1月の、どストライクゾーン (笑)。家にこもってればいいのに、と思うでしょ。うちは築50年の風通しのきく隙間風だらけの日本家屋。ネコのいる縁側が唯一あったかいので (昼限定)、そこにじっとしているけど、家のどこにいても基本、吐く息が白い!(笑)。クリスマスケーキやお刺身が「冷蔵庫に入らんよ」とお母さんに言うと「大丈夫、この部屋が一番寒いんだわ」(笑) と、応接間の床に置きっぱなしなのは、お決まりの光景 (笑)。だから、どうせ寒いなら、外も寒いけど、旅行に出かけたの。南国パラダイス、石垣島〜!! 名古屋と大違い! ヒートテック不要、カーデガンでおっけ〜! でも、なんと天気は雨・・・冬の雨って、さいあくの事態! と思ったけど、恐るべし石垣島 (笑)、寒く、、ない! (笑!) 宿で貸してくれる自転車を乗り回して、具志堅さんの親戚のマグロ屋へ行ったり、イノシシ刺し探しに行ったり、千ベロ (千円でベロベロになるの意 笑) 飲み街に行ったり、雨が、気にならない (笑)。すごい!石垣マジック!笑!が、同行したH部長に後で聞いたら、寒さが気にならなかったワケは、南国だからというより、泡盛でベロベロだったから、らしい (笑)。冬は千ベロで乗り越えよう! (は?笑)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
▽『私のサンタクロース編』:日本ではサンタクロースは枕元にプレゼントを置いていく。小学4年の私、イブの夜に就寝中、何かの音で目が覚めた。「あ、サンタが来た!」と思って薄目を開けると、そこにはとても見慣れた顔が…。いけないモノを見てしまった罪悪感で、そのまま眠っているフリをした。翌朝、母親の「あら~、サンタさん来たのね!」のコメントに「フフ、私はもう知ってしまったんだよ」と心で呟いた。▽『息子たちのサンタクロース編』:小さい頃は朝が早く来てほしいから、イブの夜は早く寝ていた。が、ある程度の年齢になると、サンタに会いたくて「リビングで寝る!」「今晩はずっと起きてる!」とか言ってくる。ある年、朝起きてクリスマスツリーの下を見ると、前の晩に置いたクッキーとミルク、一口ずつしか口をつけていない。息子たちが旦那に「何でサンタさん、ちょっとしか食べてないのかな?」と聞くと「お前たちが早く寝ないから、サンタは来るのが遅くなって、長時間放置したミルクとクッキーは不味いと思ったんじゃないの?」と、しれっと返事していた。現在17歳と15歳の息子、プレゼントは数が多い方が良いとサンタクロースに手紙を書き、ニヤニヤしながら私に渡してくる。今は、冬の記憶=金欠。(IE) |
(2020年12月1日号に掲載)