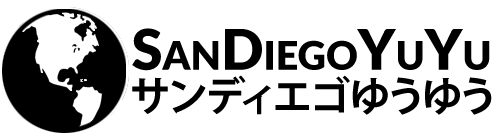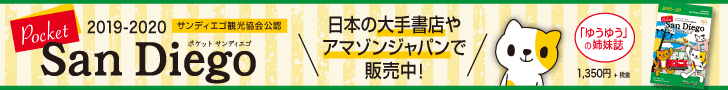▽試験答案にプラタナスの実 (スズカケノキの果実) を正確に描けば、出席不足でも合格点を与える風変わりな先生がいた。その人は一般教養科目の生物学を教えていた (植物学じゃない!)。満員電車に潰 (つぶ) されて早朝クラスに出るのは辛いので、先生の「温情救済」にすがることにした。授業の面白さを讃えるエッセイと欠席続きの “詫び状” を書いて、果実の外皮に整然と並ぶ突起1本1本を丁寧に描いたら、何と「A」をくれた。「C」の予定調和を超えた想定外の過剰報酬。その真意は・・? 自分の心に巣喰っていた「世の中こんなもの」という青二才の舐 (な) めた考えを覆す教育的効果が確かにあった。▽私がテニスの個人指導を受けていた先生は、サンディエゴでテニス留学をしていた20歳前後の若い日本人男性だった。教え方は上手い。レッスンを続けたお陰で私の腕前も磨かれてきたが、ひとつ困ったことが。先生は “若者言葉” を臆面もなく使いまくるので、しばしば理解不能に陥ることだった。私がサービスエースを決めると「それ、ま? レベチハンパねぇ〜! つ〜か、マジえぐいてぇ! 無理ゲーっすね」・・ホメているのは分かるけれど。レッスンが終わると「とりま、次は5時集合ということで、おつありです!」・・先生はプロテニスプレーヤーになる夢を叶えたのだろうか? (SS)
先生

 |
|
 |
|
 |
▽「バカとブスこそ東大に行け」。現在放送中の人気ドラマ『ドラゴン桜』の主人公、桜木先生 (阿部寛) がよく口にする言葉。原作はコミックとのことで、元暴走族で弁護士でもある教師が、偏差値の低い子どもたちを東京大学合格に導くストーリー。「スポーツとか、音楽とか、芸術とかは才能も絡むが、勉強は違う。努力が努力した分だけ返ってくる。だからお前は、勉強を頑張ったらいいんじゃないのか」。その言葉は型破りだが、理にかなっている気もする。▽自分は商業高校を出て銀行に勤めた。でも、人生のギアをチェンジをするために大学に入り直し、教育実習にも参加した。お好み焼き屋で先生たちが歓迎会を開いてくれた。「こんなドラマを放送するから生徒が勘違いするんだ」「現場がどれほど大変か分かっていない」と、武田鉄矢の『3年B組金八先生』を横目で見ながら、先生たちが顔を真っ赤にして怒っていた。1970年代末から80年代にかけて中学校に吹き荒れた校内暴力の嵐はすさまじかった。▽ドラマと現実は違う。でも、生徒が理想とする先生は概して、同僚から鼻つまみ者扱いされそうな破天荒な先生が多い。学校での立場など顧みない熱血漢。そんな教師だからこそ、1人の人間として教壇に立ち、生徒と立ち向かう姿が “最高の先生” として記憶に刻まれるように思える。 (NS)
|
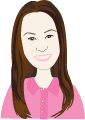 |
新型コロナウイルスのせいで、世の中がめちゃめちゃになっている。アメリカはワクチンのおかげで、少しずつ「普通の生活」に戻ってきているような気がするけど、完全にマスクなしの日常になるのは、もう少し時間がかかると思う。今から振り返ってみると、昨年3月からのロックダウンの時は、生活に必要不可欠な業種以外はいきなり全部クローズ! 毎日、家で仕事と近所で散歩ぐらいの「コロナ生活」を続けていた。ジムに通っていた私にはあまりにも運動量が少なかったため、オンラインエクササイズクラスを探していた。何と、フォローしていたジムの先生の何人かが オンラインクラス を始めた! 私はワクワクしながら オンラインクラス を取ることに。最初はラップトップの前で運動するのが慣れなくて、難しくて、右も左もなく混乱していた。でも、繰り返しているうちに段々と楽しくなってきた。今も、公園アウトドアとオンラインで同じ先生たちのクラスを受けている。この大変な1年間、精神的、肉体的にも、一緒に乗り越えてくれている先生たちに心から感謝! (S.C.C.N.)
|
 |
5月が始まった。今週の子供たちの学校は "Teacher and Staff Appreciation Week!" になっている。月曜日から木曜日まで、日替わりで "先生に感謝の気持ちを伝える" 催しが計画されている。月曜日は先生に賞状をあげる日、火曜日は先生にギフトを、水曜日はサンキューノートを贈る、木曜日は先生の好きな色を着る日。小学校らしいささやかなイベントだ。数年前に息子が学校に通い始めた時、ティーチャー アプリシエーション ウィークは、月曜日は花を、火曜日は手紙、水曜日はギフト.....というメニューだった。この「花」に困った覚えがある。結局、1年目は折り紙の花を息子に持たせ、2年目はフェルトを縫い合わせて花を作った。学校に着くと、高学年の子供たちが学校の周りに生えている草花を「先生に〜」って摘んでいたのが可愛かった。「あ、こんな感じでいいんだ〜」とも思った。アメリカの『先生に感謝の気持ち伝えよう週間』はとてもよい。私も、もっと気軽に先生方に感謝の気持ちを伝える機会があったらよかったのにと思った。(YA)
|
 |
△先日、日本に住む友達とテキストでおしゃべりしていたら「今週は子供たちの通う学校は家庭訪問ウィーク。コロナだから、玄関先だけで済ませるんだって」とのこと。家庭訪問!この言葉、すっかり忘れていた!アメリカの一般的な学校で、先生が生徒の家を訪れて親と面談する、という習慣はあるのだろうか。少なくとも、私たちの娘が通ってきた小学校、中学校では聞いたこともない。カンファレンスの時は、予約した時間に親が教室まで出向いて先生とお話しする、というスタイルにすっかり慣れてしまったので、先生がわざわざ生徒たちの家庭を訪れるということが信じ難い。思い出せば、家庭訪問の際、担任の先生が自分の家に来てくれるということが嬉しくて仕方なかったっけ。お茶菓子を食べながら、自分の親と話す先生はなんだか違う人のようにも見えた。先生たちも、生徒の家庭の様子を垣間見ることができて良いのだろうが、それにしても、結構大変な慣習だと思う。日本の学校の先生たち、お疲れ様です。△娘の通う中学校でも、今月は Teacher appreciation weekがある。このパンデミックで、オンライン授業実施など、先生たちも四苦八苦で頑張っている。先生方、お疲れ様です! (RN)
|
 |
|
 |
私は某大学の教育学部の附属中学、高校と同じ学校に6年間通った。この学校は私の入学時から、国立校では初の高校受験を廃止したり、英語の授業に LL (Language Laboratory) 教室を導入したりと、かなり革新的な学校であった。他の中学高校に比べると生徒数は遥かに少なかったが、その半数以上が将来の目標を「教師」と掲げているのに驚きを隠せなかった。まあ教育学部だから、将来は先生というのは頷 (うなず) けなくもないが、私は「絶対に先生にはならない」と決めていた。というのも、社会経験ゼロで大学卒業後に即先生となり、生徒の指導に当たる、という制度に疑問を持っていたからだ。教師たるものは学問だけを教えるのではなく、社会的経験から得られる知識なども含めて、子供たちを総合的に教育するというのが本来の姿という確固たる信念があった。社会的経験もなしに、昨日まで学生、今日から「あんたが大将」の先生。は? 故に先生にはならない、という持論が覆ったのはシンガポールで日本語教師として働いた経験から。指導対象は大人。私の人格や経験が彼らの成長に影響する訳もなく、日本語を教えることに集中すればいいというこの職は、実に見返りの多い仕事だということに気付かされたのだ。先生職に開眼した。以来、積極的にこの仕事に取り組んでいる。 (Belle)
|
 |
|
 |
中学生の頃、わたしにはお花とお茶の先生がいた。近所の幼なじみの家で、そのおがお寺なので、幼なじみのお母さんは “おくりさん“。和尚さんの奥さんのこと。だから、幼なじみのお母さんのことを先生じゃなくて、おくりさんって呼んでいた。お稽古に行くと、座敷に正座して、お花のお稽古。お花の後はお茶のお稽古。ここの先生がスゴいのは、これで終わりじゃないってこと。お寺だから、お稽古の座敷の周りはLの字に中庭に面してる廊下があって、なんと、そこの雑巾がけをするのが恒例。今思うとなんでわたしが、、?笑 棒が付いたモップじゃないよ。ブリキのバケツに水が入っていて、雑巾をカチカチに硬くしぼるタイプ 笑。寒い冬は指が、ちぎれる!それを、タッタッタッタって、一休さんのようになが〜い廊下を雑巾がけ。そんな時、ふっとおくりさんを横目で見ると、、あったかいお茶飲んで、さっきのお茶のお菓子食ってんじゃん!・・・さらに奥に目をやると、、ここの息子 (幼なじみ) は、、茶の間でリラックス? なんでわたしが雑巾がけで、坊主がコタツでテレビ? その後、おくりさんは師範種目を増やし、ご詠歌の先生となった。わたしが知ってる限り、さらに65歳ごろ、仏教短大に入学し、山道を車で通学してた 笑。こんなにバイタリティある先生、さすが昭和でしょ笑。 (りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
幼稚園の頃、先生が苦手だった。理由の一つは、給食を残さずに食べないと叱られた記憶があるから。ピーマンが苦手で、こっそり制服のポケットに入れてしまったのをおぼろげに覚えている。その後、ポケットから母が見つけたのか、自分で取り出したのか覚えていないが、「乾涸 (ひから) びたピーマン」の姿だけが写真のように記憶に残っている。母親になった今は、生徒の親として先生と接する機会が多くなった。最近、長女の成績に疑問があり、連絡を取ることがあった。一科目だけ成績がすごく悪かったのだが、長女が言うには、そんなに成績が下がった理由が分からないとのことだった。娘の勉強の様子はだいたい把握していたので、私もこれはないだろうと思い、思い切って先生に尋ねることにした。話をしたところ、先生も娘の普段のテストのスコアから考えても、何かおかしいと感じたらしく、再度成績を見直してくれた。その結果、テストのスコアを付け間違えていたことが判明した。娘を信じてくれて、私の説明を聞いてくれた先生に感謝。些細なことのようだが、ちょっとしたことが子どもにとってずっと記憶に残ることがある。私の 「乾涸びたピーマン」のように。娘の担任の先生も、きっと彼女の記憶に長く残るだろう。そして今、娘は、将来は学校の先生になりたいと言っている。 (SU) |
(2021年5月16日号に掲載)