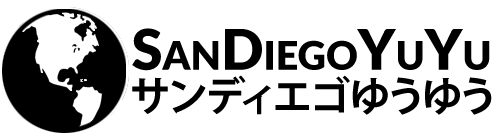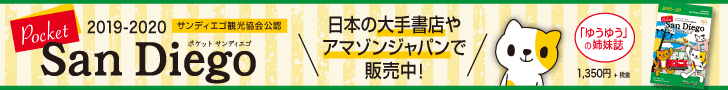「盛夏の灼熱の光は、我らを深く死に導く」 (誰の言葉だっけ?)。夏の太陽は旺盛な生命力の象徴なのに、胸騒ぎを覚える不吉さがある。特に日本の夏。幼少期から今まで、夏に寄せるスリリングな感触は変わらない。湿気まみれの暑苦しさ (諦念)、蝉の鳴き声 (読経)、蚊取線香の香りと煙 (法要) … 前世、現世、来世が渾然一体となった奥深い安堵感かも。COVID-19がもたらす死への恐怖感とは違う。茨城県の漁村 (平潟港) に家族と逗留していた6歳の夏。喫茶店で母とかき氷を食べていると、男児が溺れて行方不明になり、漁村全体が騒然となった。警察と村人総出の捜索が続いたが、少年は見つからない。薄暮に霞む無表情な漁港の海が幸福感を奪い去った。止むことのない蜩 (ひぐらし) の合唱、無機質に旋回して夜のしじまを破る灯台の光 … 鮮烈な記憶。2つの対照的な海岸があった。荒波が人を寄せつけぬ男性的な五浦 (いづら) 海岸と穏やかで女性的な勿来 (なこそ) 海岸。その夏に初めて海を見て、波の表情に人の心を感じた。五浦海岸には尊厳、勿来海岸には慈愛、静かな平潟港には安息、断崖絶壁から見下ろす太平洋には畏怖を ―― 。人間の喜びと悲しみは表裏一体と教えてくれた “原風景” となった。それにしても、父はどうして寂寥感の漂う8月末の海を好んだのだろう。 (SS)
夏の記憶
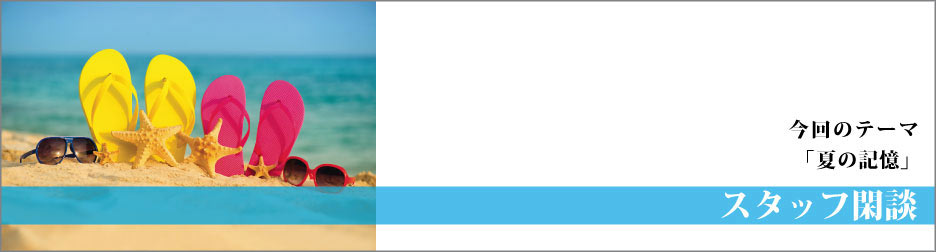
 |
|
 |
|
 |
▽子どもの頃、毎夏、潮干狩りを楽しんだ千葉県船橋市の海岸には、当時、国内最大のレジャーランド「船橋ヘルスセンター」があった。遊園地、プール、ボーリング場、観覧車、ホテル、大ローマ風呂、宴会場などがあり、無節操なパワーが炸裂していた。「ヘルスセンター」は1977年に閉園。1983年、すぐ近くに「東京ディズニーランド」がオープンした。▽夏と言えば甲子園。高校1年の時、東関東大会を制覇した母校、千葉商を応援するためにバスで甲子園に行ったことがある。緑のツタが絡まる球場はとにかく暑かった。校旗を掲げている男子にバケツで水をかけ、カチワリやタオルを持って走り回っている間に試合は終わった。▽学生時代、ワンゲルに入部してあちこちの山に登った。夏合宿ともなると、30kgの荷物を背負って1日10時間、約1週間、ひたすら山を歩く。飯豊連峰、朝日連峰、日本アルプスなどの山頂から稜線を振り返り、歩いてきた道のりと、壮大な景色にいつも感動した。▽20年前の夏、両親と姪がサンディエゴの我が家に初めてやって来た。SDを満喫した後、 「モニュメントバレーと3大国立公園」のバスツアーに参加。皆のスリッパを用意したまでは良かったのだが、自分の下着を忘れてしまい、母の綿製のデカパンを穿きながらアメリカ西部の壮大な自然を満喫した。 (NS)
|
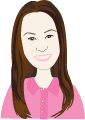 |
私は暑い夏に生まれた。2年前の夏、現在の家 (自分への誕生日プレゼント?^.^) に引っ越してきた。一階建て、天井が非常に高く(2階くらいの高さ)、風通しがとても良い家。上手く窓を開けたり、閉めたりすれば、エアコンを付けなくても、暑い夏でも快適に過ごせる。正式に入居する前、家具なしの新しい家で一晩 "キャンプ" をした。今までの家とまったく正反対で、夜は非常に静かで、虫の鳴き声しか聞こえないエリア。あの夜、リビングルームにブランケットを敷き、天井のスカイライトから綺麗なお月様と星を観ながら、夫とこの家を見つけるまでの "長い経歴" (1.5年間、400軒以上の家、オープンハウスを見てきた) の話をした。あの夏から少なくとも2年が経った。問題になっていたバックヤードの大きな7本の木をカット、広い範囲に伸びた雑草を抜く作業、キャニオン側の敷地内の雑木をカット、、、、いろいろな作業をしていた。自分の理想の家 (全然豪華じゃないけどね) に住むことができることに感謝。そして幸せを感じる。 (S.C.C.N.)
|
 |
毎年夏になると、母の実家に父を除く親子3人で帰省していた。母の実家は隣の県で、母の運転する車で2時間半ほど掛かっていた。車酔いする私は助手席に座り、気持ち悪くならないように、少し緊張しながら2時間半、外の景色を見たり、母と話をしたりしながら過ごすと、それが見慣れた景観になり、祖父母の住む家に到着する。車酔いとは縁のない妹は、旅の間、後部座席で横になり、昼寝したり、本を読んだりしていた。古い日本家屋の玄関をガラガラと開けると、祖母がにこやかに「よう来たねー、つかれたやろ」と私たちを迎えてくれた。滞在中、日中は田畑の畦道を散歩したり、従兄弟たちとセミを採ったり、スイカを食べたり、祖父母の家のすぐそばに住む叔母に手芸やお菓子づくりを教えてもらったりして過ごした。夜は母と妹と3人で蚊帳の中で寝るのが面白かった。今でも、夏の記憶というと祖父母の家が思い浮かぶ。ここ数年、夏は北カリフォルニアに暮らす夫の母の家にお邪魔している。子供たちはプールで泳いだり、裏庭でキャンプをしたりして夏休みを満喫している。子供たちにとっての夏の楽しい記憶になるといいなと思う。 (YA)
|
 |
夏の記憶といえば・・・ 蚊取り線香の匂い、スイカ割り、かき氷、キャンプ、凍らせたポカリスエット、海の家、サザエの壺焼き、夏祭り、ラジオ体操、寝台車、etc。こうやって挙げてみると、どれも日本に暮らしていた頃、それも子供時代の記憶が多いことに気づく。大人になってからも、いろいろ夏の思い出はあるはずなのに不思議。今でも夏に日本の実家に帰省中、セミの声、夜に聞こえてくるカエルの大合唱、夕暮れ時に鳴き始めるヒグラシの声を聞くと、幼い頃の思い出が一気に蘇ってくる。サンディエゴに住み始めてからの夏の記憶といえば、娘を妊娠中の夏。その年はサンディエゴには珍しく、蒸し暑い猛暑日が続き、冷房のない自宅で臨月の大きなお腹を抱えた私は暑さでバテそうになり、慌てて簡易式のクーラーを買って設置した。予定日を1週間以上すぎてやっと生まれてきた娘と一緒に帰宅すると、庭のプルメリアが綺麗に咲いていたのをよく覚えている。あれから月日は経ち、娘も12歳になった。今年は新型コロナウイルスの影響でいろいろな事が変わってしまい、いつもの夏の過ごし方もできない状態。まだまだ大変な状況が続いているが、家族みな、元気に日々を過ごせることに感謝したい。 (RN)
|
 |
|
 |
父は5人妹弟の長男。彼の祖父母は瀬戸内海の海辺で半農半漁を営んでいた。器用だった彼は、やがて田舎の海辺を去り、町に出て技術者となり、呉 (広島県) の造船所に勤務の後、自分で工場を立ち上げた。仲の良い妹弟4人に次々と機械と従業員を分け与え、それぞれを独立させた親分肌だった。毎年夏になると、彼と妹弟の家族全員が海辺の祖父母の家に集まり、三世代集合の大宴会が始まるのである。当時は瀬戸内海の透明度も高く、浜辺では直径10㎝はあろうかという蛤や大貝がざくざく取れて、それらを焼いて皆で食べる。祖母は娘や嫁たちと、総勢30人分ほどの天ぷらを朝から揚げている。揚がった天ぷらは麹蓋という平たい木製の特大盆のような容器に盛られる。アクセントに緑色の色粉が使われた天ぷらもあった。それを兄弟姉妹、姪や甥、従兄妹らとわいわい、がやがや言いながら食べる。毎年夏に繰り広げられる、平和そのものの家族絵巻。そんなノスタルジックな思い出も、今は昔。大手鉄鋼メーカーが進出して海は汚染され、魚介類の漁は大打撃を食らってしまった。あれから半世紀以上。祖父母どころか、両親さえもなくなってしまった今、二度と味わえない幻と化した10㎝大の蛤と、薄緑色の衣がついた天ぷら。これぞ私の夏の記憶以外の何物でもない。 (Belle)
|
 |
|
 |
わたしの育った愛知県春日井市の実家の裏には、イチロ-選手の母校、愛工大名電高校 (名電) の野球部合宿所があって、基本、一年を通して金属バットの音がカーン、カーンって鳴り響いていた。一番うるさく (うるさかったんだ 笑) 響いていたのは、夏。日が長いから、朝っぱらから夜まで音が鳴ってるし、暑くて窓開けているので、よーーく聞こえる。昼間はセミの鳴き声と混ざって、本当に暑苦しかったわ (笑)。野球部のお兄ちゃんたちは、家の近所や堤防を走っているのでよく見かけるし、当時の中村監督の娘さんと歳が近かったので、小学校の水泳大会/運動会となると、野球部員が娘を応援に詰め掛けていた (笑)。巷では、お兄ちゃんたちは大人気。わたしも調子にのって名電野球部のグラウンドを遊び場としていた。高校生と遊ぶのがすっごく楽しかった子供時代の中でも一番感動したのは、お兄ちゃんたちを応援に甲子園へ行ったこと。友達のお父さんの軽トラで向かい、暗いうちから入口に並んだよ。でも甲子園ということは、いろいろな高校のスターがいるワケよ。目移りするほど (笑)。名電野球部そっちのけで他校の球児をギャーギャー叫んで写真撮ってた、かわいい夏の記憶ですわ (球児見てギャーギャー言うの、かわいすぎじゃね?笑) (あれ?感動はどこへ?笑)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
夏の思い出と言えば、地元の『河童まつり』。♪うしーくー沼には、カッパがござーるぅ♪ カッパ誰の子、芋銭 (うせん) の子~♪ という河童ばやし。牛久 (茨城県) で小川芋銭 (河童の絵で有名な画家) を知らない人は、非国民ならぬ非市民。中学の時には友達と行き、見回りの先生に 「おごってくれ」とたかり、高校時代には好きな人と手をつないでプラプラ。2回ほどテキ屋のバイトをしたことがあった。紐を引っ張ったら賞品と繋がっているというゲーム露店。これがまたハッタリで、紐は豪華賞品には全く繋がっていないというインチキ商売だった。3年前、丁度、帰省時が河童まつりと重なった。私も軽く25年ぶりだ。子供たちにも体験させようと、地元の友達と妹家族で行ってみた。どうせインチキであろう露店ゲーム (笑)、たこ焼き、焼きそばを買って、思い切り日本の祭りを満喫。メインイベントは、地区ごとにいろいろな恰好をした、河童ばやし音頭パレード。観客で見ていたら、友達の地区が近づいてきた。皆でお揃いのハッピを着て楽しそう!「Iちゃん!入りなよ! 一緒に踊ろう!」と言い出した。遠慮していたら、周りのおばちゃん、おじちゃんまで「入れ!入れ!」と言ってくる。ここはノリだ!と思い、息子たちも引き連れジョイン! 楽しかった~。 地元ラブ ♡ (IE) |
(2020年8月1日号に掲載)