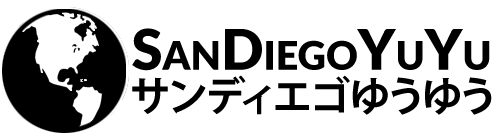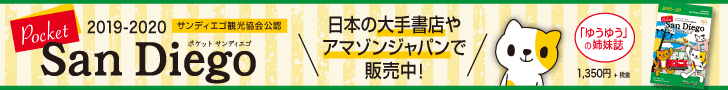総領事館経由で分厚い国際書留郵便が届いた。米国で三度の lawsuit を経験している私は、書留郵便 = 訴訟通知というイメージがあるので、嫌な予感がした。福島地裁からの民事訴訟関連書類。日本で裁判沙汰? それは土地問題に絡む “事件” だった (相続処理が済んでいるのに、何故?)。想定外の内容。話は昭和6年 (1931年) まで遡る。小地主だった曾祖父 (写真しか知らない) が▲さん宅の差押仮処分を申請したが、所有権移転の問題が浮上し、執行されずに約90年間、宙ぶらりんの状態が続いていたらしい。その家に住む4代目の▲さんが仮差押登記の抹消を申し立てた (実質的な債権・債務関係など現存しないのに、4世代目の▲さんは几帳面)。それには曽祖父の法定相続人 (私を含む生存する債権者) 全員の合意が必要。保全取消に異議があれば答弁書を提出し、裁判所出頭の義務が生じる。抹消に合意した私はコロナ禍中に帰国せずに済んだ。やれやれ。亡霊のように出現した曽祖父の生き様の断片。法定相続人18人の名前・住所一覧も含まれていた。幼い頃に遊んだ従弟妹たちは全員が存命。女は結婚していたり、離婚後に旧姓に戻ったり、外国で暮らしていたりと、人生の変化が滲み出ている。親族に思いを馳せる書留郵便だった。(SS)
メール/手紙/便り

 |
|
 |
|
 |
日本に里帰りしたとき、父の遺品の中から旧制会津中学49回生の同窓会の旧友に宛てた手紙のコピーを見つけた。「敗戦直前になってロシア軍と戦った我々は、シベリアで飢えと寒さに苦しんだ。そして、多くの戦友が異国の土と化した。復員後、食糧難とヤミ経済を体験し、所得倍増の掛け声のもと、豊かさを求めて夢中に走った。その結果が、高度成長とバブルの崩壊。我々自営業などは、蟷螂の斧 (とうろうのおの) を武器に大型店に立ち向かうことになった。気が付けば喜寿。いろいろなことがありました。人間機械は磨耗して、部品交換、部分切断は当たり前となっていますが、兎にも角にもいろいろ条件をクリアして、自分の足で同窓会に出席できるなどと云うことは、奇跡であり『神わざ』にも等しいことではないでしょうか。我々はみな、いつかは消えて行く身。同じ時代を生き抜いた戦友として、同窓会当日は心ゆくまで語り合いたいものです」。父は寡黙な人だった。毎年、終戦記念日の近くになると、さらに無口になった。もっとたくさん話をしたかったな~と、今頃になって思う。一期一会という言葉があるが、今日という一日、家族、仕事仲間、恩師、友人、知人、そんな奇跡的な出会いに感謝して、一緒の時代を過ごす喜びを大切にしたいと思うようになった。 (NS)
|
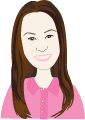 |
手で覚えているのか、頭で覚えているのか分からないけど、最近、恐ろしいことに、タイプしないと漢字が書けなくなってきた!! 日本語の場合はローマ字入力でコンピューター、携帯などの電子機器を使い慣れているので、とりあえず打ち込みは問題ない(手書きだとちょっと自信がないかも)。母国語の中国語の場合は、ローマ字入力じゃなく、"拼音" (ピンイン) で入力=音節をラテン文字化して表記=しないといけないので、"拼音" が元々かなり苦手な私には、まったく中国語を打ち込むことができない(恥ずかしい>.<)。そのせいで、台湾にいる家族とのメール、テキストなどのやりとりは全て英語もしくは日本語で打ち込んた "日本語兼中国語" になる。昔の手書き時代と比べると、本当に便利な時代になってきたけど、手紙やカードを書いて送ったり、送ってもらったりの時代がちょっと恋しいかも・・。またいつか暇がある時、手紙でも書いて、家族や友人に送ってみようかなぁ〜。みんなビックリするかもしれないね(笑)。 (S.C.C.N.)
|
 |
Eメール、テキストメッセージ、IM、Line、チャットなどなど、どんどん便利になって、手書きの手紙、葉書というものを
使わなくなった。昔はいろんなレターセットやかわいいシールを集めていたのだが・・。中学生の頃に、仲が良かった子に薦められて、海外の人との文通を始めた。当時 「ペンパル」「ペンフレンド」といって海外文通が流行っていた。私のペンフレンドは、スウェーデン、エストニア、ルーマニア、韓国の子たち。一番長く続いたペンフレンドとは5〜6年文通をした。私の文通相手には、なぜか英語圏の人はいなかったので (アメリカ人にも送ったけど、返事が来なかった・・)、お互い、拙い英語でやりとりをしていた。クリスマスには、ちょっとしたものを小包で送り合った。私は日本らしい和小物や日本のお菓子などを送り、文通相手からは見たことがない文字が印刷されたキャンディやポストカード、繊細なレース編みが届いた。手紙を送ってから返事が来るまでの2〜3週間が待ち遠しかった。そして、遠い外国とやりとりをしている実感があった。便利な今だからこそ、手紙を見直してみるのも良いかもしれない。(YA) |
 |
保育園でお世話になった先生との手紙のやり取りが、40年以上 (!) を経た今でもまだ続いている。私が子供の頃は、しょっちゅう先生に手紙を書いて送っていた。先生からはすぐに丁寧な返信が送られてきて嬉しかったのをよく覚えている。時が経つにつれ、年末年始の挨拶がてら、年に一度、お互いの近況を伝え合う程度になっているが、それでも、先生からの見慣れた優しい字体で書かれた手紙を読むと、ほんわりとあたたかな気持ちになる。もう70代になられているはずだが、まだ現役で保育の仕事をされていて、子供を取り巻く環境の変化を憂いながらも、愛情いっぱいに子供たちと接しておられる様子が手紙から伝わってくる。今年に入って頂いた手紙には、岩崎ちひろの描いた少女の絵が印刷された絵葉書が同封されていた。「子供の頃のあなたのイメージに重なるような気がするけど、どうかしら?」と一筆添えられていた。こんなに可憐な子供じゃなかったような気もするけれど、先生の優しい気持ちが嬉しかった。(RN)
|
 |
|
 |
今でも鮮明に覚えている、あの感覚。結婚して、憧れていた主婦生活を決め込んだものの、如何せん退屈。これは何とかせねばと、2階の2部屋を使って民宿を始めることに。が、どうやってお客さんに来てもらうの? 幸いにも友達が、当時まだ皆が持つ時代でもなかったコンピューターを持っていたので、彼女のアイデアで「ジャパンネットワーク」に書き込んであげる、と民宿の情報を出してくれた。それがきっかけで、少しずつお客様に来てもらえるようになった5人目。長岡 (新潟県) からのお客様が私の宿のコンセプトを気に入って下さり「僕がホームページを作りましょう」と、申し出て下さった。パソコン時代でもない頃に、HPを作る技術を持つ人に出会えた私は超ラッキー。慌ててパソコンを買いに走り、手早にセットアップして、私のホームページで使うコメントの原稿や写真のやり取りがHPの作者と始まる。生まれて初めてEメールなるものを送った時の、まるで、その人が隣にいて「ねえ、ねえ」と話しかけているような、その親近感あふれる感覚がいつまでも記憶に残っている。以来、20数年。Eメールは、人との距離、時間だけでなく感覚も縮めてくれた。世界中どこにいても瞬時に話が通じる。こんな素晴らしい時代に生きられることに、まっこと感謝! (Belle)
|
 |
|
 |
友達に、手紙、ホリデーカード、誕生日カードなどを一生分 (笑) 取っておいている人がいる。親からの手紙はもちろん、毎年来るであろう年賀状的なカードも、30年分くらい箱に保管してるって (笑)。「捨てないの?」 と聞くと 「え?捨てるの?」(笑)。わたしは受け取ると一旦は置いておくのだけど、、しまう場所がなくなっちゃうし、生活する面積が減るし、最終的には、手放す、と、毎年手作りカードをご丁寧に郵便で届けてくれている友達に (後から考えたら) 言いづらかった (ハズだろう 笑)、けど、普通にケロッと“捨ててるよ” (笑)。ポンポン捨てるのは母親譲り。基本ルールとして、人のものは捨てない。なので律儀なお母さんは、ここ数年前から実家に置いてあるわたしの私物をわざわざエアメールで送ってくる (笑)。幼い頃の工作品、小学校の校庭から掘り出したタイムカプセルの中にあった未来の自分への手紙、、もう絶対いらないし (笑)、毎年末に実家に帰るのだから、送っていらんくね? (ヒドイ娘 笑)。でも自分への手紙を読んで 「これ、傑作でしょ?」と感動し (笑)、 大切に保管してるわたしがいます (笑)。
|
 |
|
 |
Eメールやテキストを使うようなって、徐々に手紙を書くことが減っていった。日本の家族とは毎日ラインでテキストしたり、直接話をしているし、友達や仕事関係もラインかEメールだ。その結果、どうせ郵便受けに入っているのは、請求書、広告、スーパーのチラシくらいだろうと、心当たりがある時以外は郵便受けを確認しなくなった。うっかりすると2週間ほど確認しないことも・・。怠けてチェックしていなかったため、去年のクリスマス頃に親類のおばさんが娘たちに送ってくれたクリスマスカードに、年が明けてから気づくというとんでもない失礼をしてしまった。日本から確認の電話が来て、家族にこっぴどく叱られた。当然だ。急いで受け取ったカードはとても可愛らしく、優しさのこもったクリスマスカードだった。やはり人が書いた字には温度や感情が感じられる。パソコンで打っただけの文字は、どんなに丁寧な言葉を選んでも、思いは伝わりにくい。時間をかけて心を込めてしたため、郵便局に足を運び、投函するという手間の掛かることも、相手がそうして、自分のために時間を割いてくれたと思えばこそ、大事に取っておこうとする。日々の忙しさに追われ、便利なツールに慣れてしまった今、忘れかけていた古き良き時代を、時々は足を止めて振り返るべきだと思った。(IE) |
(2020年8月16日号に掲載)