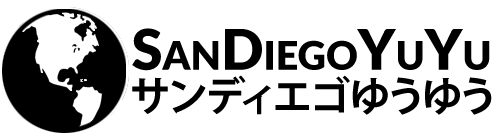ゆうゆうインタビュー 大田 幸人
 |
| ステータスシンボルとしての1960年代の寿司、70年代のヘルシー志向ブーム、80年代の第1次寿司旋風、そして90年代の創作寿司と、今や日本の寿司文化はすっかりアメリカに定着しました。そして一流と呼ばれる寿司店には必ず、江戸の昔から伝わる技を、静かに確かに継承している生粋の職人がいます。 —— 板前への憧れ 実家はみかん農家で、男6人女2人の末っ子として熊本県天草の静かな山やまあい間の村に生まれました。14戸余りの小さな集落でしたが、村自体が大きな共同体で、慶び事や憂い事があると庭先にカマドを設しつらえて皆で膳を用意する慣わしがありまして、そんな時に私の親父は決まってプロ顔負けの見事な腕前を披露しました。大根で鶴を飛ばし、人参で亀を這わせ、蕎そ ば麦を打ち、大鰻の蒲焼き、刺身、焼き物、揚げ物…。土間には、柳刃、出刃、舟行と10種類以上の包丁が天草砥石を使って見事に研ぎ上げられていました。ですから、母親や姉が作る家庭料理とは一味違う 「和食の粋」 を親父の背中に感じながら育ちました。 「板前になろう」 と思ったのは、中学1年の時に見た寿司屋を舞台にしたTVドラマが機縁でした。画面に映った握りの技といなせな職人の世界に憧れを抱いたんです。それで中学卒業と同時にこの道に入ろうと決めました。国語や英語など元来勉強はあまり好きではなかったし、進学には大分お金も掛かります。当時は中卒で就職というのも少なくありませんでしたから、両親もすんなりと許してくれました。私は尼崎で寿司店を開いていた同郷の人の元へ弟子入りしました。 ——丁稚奉公 尼崎の寿司屋 「さなみ」 はカウンター席が7つほどのこじんまりとした店で、職場から歩いて10分程の木造平屋のアパートに店を手伝っている親方のご兄弟2人と一緒に住み込ませてもらいました。眠い目をこすりながら親方と一緒に尼崎の中央卸市場へ行き、店に戻って掃除、仕込み、出前持ちと、早朝から深夜まで飛び回っていました。最初の3年間は寿司を握らせてもらえませんでしたが、近くの豆腐屋でおからを譲ってもらい、沢庵をネタにして隠れて練習をしていました。親方はそれを黙認してくれていましたし、お客さんは 「チビ、チビ」 と可愛がってくれました。「あぁ…ぎゃんすっとよかっですね」。九州弁丸出しの田舎坊主だったので、お客様に対する言葉使いに関しては本当によく注意されました。叩き上げの修業の中にも温かいぬくもりが感じられる家庭的な職場でした。 ある日、常連さんがいらして、僕がお茶くみに出たら「大将、ちょっとチビに握らせてよ」 と言って下さったんです。ハタさんというタイル施工会社の社長さんで、それで親方が代わってくれて初めて寿司を握りました。付け台を挟んで直にお客様と接する、その所作を全て顧客の目の前で行わなければならないという非常に緊迫感のある仕事の恐さをその時初めて知って、もう本当に緊張しましてね。ブルブル震える手でお出しした寿司は今でもよく覚えています。 —— 板前修業  追い回し (雑用) 3年、シャリ切り3年、焼き場、向こう板 (補佐)、煮方、脇板 (調理長)、花板 (板前・看板料理人) と、一人前の板前になるには 「10年旅立ち」 と言って、それなりの年季と板場の段階を経なければなりません。親方には4人の兄弟がいて、皆それぞれ独立して神戸近郊に寿司屋を構えていましたので、「さなみ」 を皮切りに11年間に渡って各店を回り、いろいろ勉強させてもらいました。マニアルなんてありませんし、誰も何も教えてくれない。自分で 「盗んで」 覚えていく。与えられた仕事の中で知恵と技を磨いていくワケです。 追い回し (雑用) 3年、シャリ切り3年、焼き場、向こう板 (補佐)、煮方、脇板 (調理長)、花板 (板前・看板料理人) と、一人前の板前になるには 「10年旅立ち」 と言って、それなりの年季と板場の段階を経なければなりません。親方には4人の兄弟がいて、皆それぞれ独立して神戸近郊に寿司屋を構えていましたので、「さなみ」 を皮切りに11年間に渡って各店を回り、いろいろ勉強させてもらいました。マニアルなんてありませんし、誰も何も教えてくれない。自分で 「盗んで」 覚えていく。与えられた仕事の中で知恵と技を磨いていくワケです。それでも、一度だけ店を辞めようと思ったことがありました。血気盛んな27歳の主人がなかなか手厳しい人で、気に添わないと私の頭を突いたり、足を蹴ったりするんですね。こちらも小僧のくせに負けん気だけは強かったので、買ったばかりの50ccの単車を飛ばして国道2号線を一路熊本に向かいました。17歳のささやかな反抗という行動でしたが、次第に涙が溢れてきました。ところが、頼みのカブが姫路あたりで壊れてしまい、意気消沈して単車を押していたところを長距離トラックの運転手さんが拾ってくれて…。「陸送が終わったら翌朝またここを通るから、その後で熊本でも神戸でも何処へでも送ってやる」と̶̶̶。「逃げたら終わりだ。とにかく、一つ一つ今出来ることを真剣に取り組むしかない」。それが一晩だけ野宿をして考えた末の結論でした。 毎日毎日寿司を握るだけの生活でしたが、数年が過ぎると季節を肌で感じることができ、寿司というのは板前の感性で創ってい0000く0ものだということが次第に分かってくるんです。ある程度任せられるようになると、責任の重さに押し潰されそうになる一方で心地良さも感じて、 回りもチヤホヤしてくれて、知らず知らずのうちにいい気になってしまうものです。22歳になった頃、天狗になっていた僕の鼻を圧へし折ってくれたお客さんがいました。飲み屋のマスターで、食道楽を自認するご仁でした。未熟さを知らされ、頭から冷水を掛けられたような心持ちでした。それで親方から6か月程の許しを頂き、東京の寿司屋で修業をさせてもらいました。 —— サンディエゴの青空の下 25歳の頃、兄弟子に誘われて大阪の店に移ったのですが、独立に関してその兄貴と店の旦那がもめて、私がげんなりしているところに知人から渡米の話を持ちかけられました。サンディエゴの 「神戸みその」 という鉄板焼ステーキの店が寿司バーの立ち上げに板前を探しているというお誘いでした。それからトントンと話がまとまって、4か月後にはサンディエゴの青空の下で働いていました。ただ、「さなみ」の親方はそんな僕をまるで相手にしてくれず、その点では辛い旅立ちとなりました。 1982年当時、サンディエゴには寿司店と呼べる店は 8軒程しかなかったんですが、時はまさに第 1次寿司ブームがアメリカに到来した時期で、見た目の美しさとヘルシー志向が相まって、寿司は急速に注目を集めるようになりました。職場では面倒見の良い先輩や楽しい同僚に恵まれて、本当に伸び伸びと仕事をさせてもらいました。こちらの人は板前に寿司を握ってもらうことに最大限の好意を示してくれます。僕の拙つたない英語にも耳を傾けてくれて、喜び方が半端じゃない!! この反応は日本では味わったことのない体験でした。 そして、カリフォルニア米も魚もまんざらじゃない。特に、サンディエゴ近海で捕れるウニに惚れ込みました。これなら日本人のお客様にも十分満足して頂ける寿司をお出し出来ると確信して、段々とサンディエゴを自分の住すみか処と宣言できる気持ちになりました。「寿司大田」を開店したのは1990年ですが、お客様がずっと応援して下さったことと、その頃に女房と出会ったことが契機となりました。 ——巡り合いが紡ぐ人生 独り立ちするまでは会ってはくれないと分かっていましたから、開店して初めて 「さなみ」の親方にもご挨拶に伺うことができました。元々無口な方ですから何も言ってくれませんでしたが、帰りしなに黙って柳包丁を1本渡してくれました。嬉しかったですよ、本当に。 「開業から13年。後ろを振り返る余裕も無いほど無我夢中で突っ走ってきて、何とか暮らしている」というのが正直な感想です。親父は27年前、私が21歳の時に66歳で他界していますし、母は5年前に82歳で逝きました。齢よわいを重ねて自分が人生の折り返し地点を過ぎてみると、人間の一生はそれほど長くないと感じます。それでも、自分が生きていることを確かに感じさせてくれるものがあります。それを言葉にするなら 「邂かいこう逅=めぐりあい」 とでも言いましょうか…。私にとってそれは寿司であり、親方であり、サンディエゴであり、女房であり、従業員であり、そして私を叱しった咤激励してくれる多くのお客様なのです。 (2003年7月16日号に掲載) |