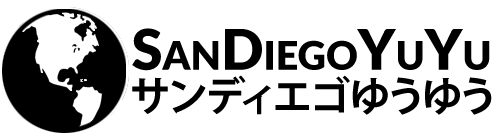ゆうゆうインタビュー レーン・ニシカワ
 |
| —— 現在の仕事に就いた発端を話して下さい。 大学に通っていた頃、脚本の執筆、自由詩や口語体の創作に興味を抱くようになりました。それは片手間で始めたことでしたが、地道に続けていましたね。演劇と執筆活動をしながら、UPS、空港、駐車係などの数多くの仕事に従事しました。長く続いたのは電器店のセールスマンで、私は販売員と倉庫係として働いていました。当時の私は、脚本家として成功するとは想像もしていませんでした。 アジア系アメリカ人劇団を紹介されたことが機縁となり、脚本だけでなく演技にも興味が向くようになりました。彼らは早いうちから「この作品を上演したい。オーディションを開いてはどうか」と私に提案するので、どうなるかと不安ながらも、オーディションを設定してキャストを集めました。その後で「次は何をすればいいのだろう」と思案していました。この初めての体験を通して、仲間である俳優、監督、脚本家から舞台や演技について多くを学んだのです。私はあらゆることを注意深く観察し、できる限りのことを頭の中へ叩き込みました。詩歌の創作も続けていましたが、舞台での演技が影響してか、その内容は人物描写に重点を置くようになりました。例えば、第442連隊戦闘団の一員であった叔父をモチーフにした人物が第二次世界大戦時代を追体験するなど、 登場人物たちがそれぞれの人生を語り始めたのです。 ——日系人として受け継いだ遺産を自ら活用したのですね。 
Two of the real heroes from the 442nd Martin L. Ito (C-Company) and Jimmy Matsumoto (K-Company) along with the cast of“Only the Brave”at its screening in San Diego. Cast L-R: Mike Hagiwara, Greg Coatanabe, Tamlyn Tomita, Gina Hiraizumi, Lane Nishikawa, Yuji Okumoto, Mark Dacascos, Jason Scott Lee, Trace Murase, Michael Sun Lee, Ken Narasaki.
そうです。大学生だった私はこれらの事柄について常にリサーチを行い、多くのことを学んでいたのです。アジア系アメリカ人に関する内容は、全て私の執筆によるものです。当時の私は著書も出版して作家としても活動しており、サンフランシスコ州立大学から創作文章クラスの講師として依頼を受けました。ですから、私の最初の創作劇“Life in the Fast Lane”が上演を迎えるまでの数セメスターは教壇に立っていました。“Life in the Fast Lane”はアジア系アメリカ人の作家が出版を実現するまでの苦労を描いた作品です。作家とは如何なるものかをテーマに、私は登場する全てのキャラクターを演じました。この作品は全米19都市をツアーで巡ることになり、この時点で私は大学を辞めました。その後、再び大学へ戻って学位を取得しましたが、両親は当時の私を見て「息子は一体何をするつもりなのだろう」と不安に思っていたはずです。 —— 会計士のお父様から実務的な道を歩むように説得されましたか。 勿論、それは当然です。私の父は「ミスター・プラクティカル」とも呼ぶべき人物で、「学校へはいつ戻るのか」「会計や不動産業を目指したらどうか。とにかく、生きていく術を身に付けなさい」と常に言っていました。父は俳優や作家の道が厳しいことを知っていました。私は“Life in the Fast Lane”のツアーに膨大な時間を費やしましたが、相応のギャラも支払われ、どうにか自分で生計を立てていました。父は私を心配しながらも劇場へ足を運んでくれました。作品を観賞することで、私への理解を深めてくれたと思います。他界した私の祖母を扱ったシーンが序幕にあり、それはどこにでも見られる典型的な祖母像でしたが、父は台本のコピーが欲しいと言うのです。それを日本語に訳して、日本に住む親族に送ろうとしていました。父は私に経済的な安定を望む一方で、私の仕事に敬意を払い、誇りに思っていたのです。 —— “Life in the Fast Lane”のツアー後は。 4年を費やしたツアーから戻ると、アジア系アメリカ人劇団から芸術監督就任の要請があり、私はそれを引き受けました。その時点で、私は演出家としても役者としても数多くの舞台を経験していました。劇団の運営において、私たちが尽力したことの一つは連合体を形成して俳優の生計を助けることでした。例え、予算が3倍に膨らんでも俳優たちにギャラを支払い、福利厚生さえも得られるよう努力しました。それは実に困難な道のりでしたが、その努力が実って今では正式な劇団となり、注目を集めるようになりました。私たちは10シーズンに渡り、俳優労働組合と契約を結んで作品を製作してきました。私はこの実績をとても誇りに思っています。この間、私は寝食を忘れて、俳優、脚本家、演出家らの育成に没頭していたので、私自身が為すべきことを考える暇がありませんでした。劇団運営が軌道に乗り、ようやく自分のワンマンショー “I’m on a Mission from Buddha”を製作しました。この作品もツアーを行い、KQEDチャンネル(サンフランシスコ)のPBSで全米放映されることになりました。この時期から、私は徐々に舞台の任務から離れていきました。 —— ツアーの間、使命を感じていましたか。 誰もが独自のスタイルで創作活動を行いますが、私は自分の観点からアジア系アメリカ人の体験を考察し、歴史的、政治的、社会的に伝えたい内容をテーマに舞台を制作してきました。これらの作品を観た客は、アジア系アメリカ人男性に対して、それまでとは異なる見方・視点を獲得して劇場を去っていきます。私は真実への探求を心掛け、それに皮肉、風刺、ユーモアを絡めながら人々に伝えようとしたのです。使命というものがあるなら、真の姿を観客に見せるということだったと思います。“I’m on a Mission from Buddha”は私が長年積んできた演劇経験を通して、チャンスが与えられた時に役者は何ができるのか ̶̶ということを描いています。 その後のワンマンショー“Mifune and Me”では、今ではビジネスになった映画や舞台の世界で私が長年観察してきたイメージをベースにしています。メディアが私たち日系アメリカ人をどのように捉えているのか、三船敏郎をヒーローとする私がなぜこの国では彼のような存在になれないのか ̶̶ ということを検証しています。実際、三船敏郎は私にとってのジョン・ウェインでした。私は彼の全作品を観ていますが、それでもテレビで『七人の侍』が放映されていると、チャンネルを合わせて「また100回くらい繰り返して観なければ」と思ってしまいます。それほど、彼のキャラクターは飽くことのない時代を超えた存在です。そして、アメリカでは彼のようなヒーローが誕生することはないのです。 ——ハリウッドにおけるアジア系アメリカ人俳優の状況についての見解は。 
Lane Nishikawa at the San Diego Asian American Film Festival last October.
かつて、ハリウッドでは年間400本の映画が製作されていました。現在では独立系を除いても、それ以上の作品数だと思います。しかしその中で、格闘技の師匠でもなく、敵でもなく、売春婦でもないアジア人男性や女性が主演している作品は片手で数えられる程度だと思います。私たちが目指すべき路線がそこにありました。 私が“Life in the Fast Lane”のツアーでロサンゼルスを訪れた時、友人が彼のエージェントを紹介してくれたのです。私との契約を望んでいた彼らは、遠くベイエリアに住んでいた私を考慮してか、短いセリフで終わるような端役を紹介することはありませんでした。でも、これは20年前の話です。当時はアジア系アメリカ人が登場する作品は極少でした。今で言う “Lost”、“Crouching Tiger”、“Law and Order SUV”のような作品は皆無で、唯一知られていたのがブルース・リーくらいのものでした。 そんなある日、エージェントが「お勧めの役がある」と私に電話をしてきました。私はハリウッドまで駆けつけ、最初の台本読みに臨んだ後、今度は監督から連絡が入ったのです。「プロデューサー向けにもう一度台本読みをしてほしいのだが、その前に少し考えてくれないか。そこには大勢のプロデューサーがいて、彼らは既に君のテープを見ている。私は君を推薦しているが彼らはそうではない。なぜなら君の声は低すぎるんだ。それに逞しすぎる。君には俳優が欲しがる舞台での威厳を備えている。でも、プロデューサー達はそれが嫌いなんだよ。筋肉を落として、ダサいスーツを着て、細いメタルフレームの眼鏡をかけるんだ。そして、声を何とかするんだ。君の声は深すぎる」。私は「分かりました、やってみます」と答えましたが、言うまでもなく、その役を手に入れることはできませんでした。結局、私の友人が獲得することになりました。彼は私とは全く異なるタイプの男で、高めの声の持ち主でした(笑)。とにもかくにも、これがロサンゼルス、いわゆるハリウッドなのです。 —— 初の長編映画“Only the Brave”には多くの優れたアジア系アメリカ人俳優が出演していますが、どのようにして彼らを集めたのですか。 私は、今まで積み上げてきた実績や学んだことは、全てこの映画のための準備だと感じていました。脚本、演技、演出、製作、劇団運営、資金調達、予算管理、デザイナーとのやり取り、締切調整など全ての経験がこの映画に役立ったのです。舞台では低予算で如何にやり繰りするかを苦慮しなければなりませんでしたが、“Only the Brave”は2003年にカリフォルニア市民の自由公共教育プログラムより助成金を受けてスタートしました。その後、全米日系人歴史協会と共に寄付キャンペーンや民間情報源を通しての資金調達を行い、同時に私は脚本の執筆を開始。脚本は間もなく完成しましたが、資金調達は困難を来たしました。 キャストに関しては、先ず希望リストを作成して最初のオーディションを開きましたが、それは中断することになりました。私たちは誰を起用したいのかが明らかだったのです。第100歩兵大隊と第442連隊戦闘団をベースにした作品の内容を耳にすると、誰もが製作に参加したがりました。皆がこのプロジェクトの重大性を感じていたのだと思います。こうして、私はキャスト募集を掛ける必要もなく、キャスティングを行うと言葉にした途端に450人が集まり、オーディションを始めることになりました。 最初のグループで私たちが目星をつけたのは、タムリン・トミタや当初は私の父親を演じる予定だったジョージ・タケイなどでした。そして、ユージ・オクモトが契約した後、マーク・ダカスコスも「オーディションをしてほしい」と電話をしてきました。私は「とんでもない、君にオーディションの必要はないよ。どの役を望んでいるんだ」と言って彼に脚本を送り、登場人物の中のある軍曹に注目してくれと伝えました。実は、彼が作品に興味を持っていると知った時点で私は脚本に手を加え、混血の民族性を持つ彼が快適であるように「ハッパ」という新しいキャラクターを登場させたのです。彼はこのアイデアにひどく感激していました。同じ頃、私たちはジェイソン・スコット・リーからの返答を待っていました。そして、彼から承諾を受けると、私は彼の役を中国人ハーフに設定しました。彼のキャラクターは先陣を切って一団をリードする役に最適でした。こうして、時折先が見えなくなりながらも、私たちは全てをやり遂げたのです。 —— 作品には当時の記憶や体験が盛り込まれていると思いますが、ご自身が演じたタカダ軍曹役の着想は誰から。 私の伯父と父です。ジミー・タカダのファーストネームは私の父から、ラストネームは第100歩兵大隊で初の犠牲者となった1人の兵士に敬意を表して用いました。彼の名を耳にすれば、第100歩兵大隊員全員がタカダ兵への親愛の情を示すと思いますが、それは戦友として最初に命を落とした者に対する表敬と哀悼に他なりません。私は自分の作品の中で、私なりに彼ら全員に畏敬の念を示そうとしました。例えば、腹帯の話ですが、私の伯父が亡くなった時、私は伯母から彼の腹帯を手渡されました。「これは何?」と尋ねると、彼女はちょうど映画の中のシーンと同じように説明してくれました。それは兵士だけでなく、彼らと共に戦ってきた妻、母、姉妹など全ての家族の姿を象徴しているのです。 —— 作品の内容と史実とのバランスには苦労しましたか。 
The staff of the SDAFF celebrates another successful festival and a job well done on closing night.
常に悩みました。私たちは歴史に忠実であろうとしたのですが、様々な障害から内容の変更を余儀なくされることが何度かありました。また、沢山の逸話と多くの人物が実在する中、どのようにして物語を編み出すのかが問題となりました。例えば、ある戦闘は実際には午後2時半に起こりましたが、私たちはそれを夜の出来事として撮影することで映像範囲を調整しました。また、作品の中で、私たちはブリュイエールについて言及しませんでした。その理由は、実際にフランスではベルモンテ、ビフォンティーヌ、ブリュイエールの3都市で戦闘が繰り広げられたものの、全てを作品に組み入れることが不可能であり、それらを象徴的に描きたかったのです。 また、ハワイ出身の日系人兵士による第100歩兵大隊や、日系人志願兵で組織された第442連隊戦闘団の両方を登場させたいと思いました。そのため、出演者を第100歩兵大隊兵士と第442連隊戦闘団出身とに振り分けたのです。私たちは作品の細部に至るまで気を配りました。それぞれの隊には少しずつ異なるユニフォームやジャケットがありました。退役軍人たちの話によると、誰もが442連隊のジャケットを欲しがったそうです。それには多くのポケットが付いて、弾薬や食料を多めに詰めることができたからだそうです。私たちは第二次世界大戦で使用された本物の武器から軍用時計、コンパス、巻き煙草、ライター、眼鏡に至るまで、全て当時の物を使用しました。特に、その時代を体験した観客にはウソが通用しないため、制作側としては最大限の準備をしなければならないのです。 —— 舞台や映画の演出と経営を成功させる秘訣は。 頭を素早く切り替えることと、すべきことは手を抜かないということです。早い時期に私が学んだことは、何が起ころうとも、常にスタッフが仕事を継続できる状態を維持するということでした。舞台では問題が起こると何週間もかけて対策を立てられますが、映画撮影では数時間で解決しなければなりません。そして、毎日必ず何らかの問題が発生するのです。 私たちは85名のクルーを抱えており、皆が私の決断を待っていました。場面を変更するなり、脚本を手直しするなり、何をしてでも問題を解決し、全てを進行させなければなりませんでした。如何に綿密なプランを立てていようとも、避けることができないような困難もありました。例えば、森の中での激しい銃撃シーンの初日に撮影中断という非常事態も起こりました。私たちは許可を得ていたにも関わらず、警察署は報告を受けていなかったのです。間もなく、警察官、ヘリコプター、消防車が送り込まれてきました。私たちは騒音を聞きながら「一体、何事だろう」と話していました。何か重大な事件が起きていると思っていたのですが、実はその原因が私たちだったのです。このような出来事にいつでも対処できるように準備しなくてはなりませんでした。 ——作品上映の時を迎え、観客の表情や反応を見てどう感じましたか。 最初に感銘を受けたのは、ハワイのブレイズデイル・コンサート・ホールでの上映会でした。私たちは1,000座席を設け、200人の退役軍人ほか、現在イラクで戦っている第100隊、第442隊の両親、祖父母、子供たちが来場してきたのです。退役軍人の側に座った私たちは、誰もがただ圧倒されている様子を感じ取ることができ、それは素晴らしい体験でした。私は友人に作品の配給会社を探すという次の段階について話していましたが、「次へ進めなくても、今日という、この驚くべき素晴らしい日があるじゃないか!」と言いました。作品に関わりを持つ人々、しかも私たちが感謝の念を伝えようとしている退役軍人が観賞し、感激しているのです。自らの体験が描かれたこの作品が映画史の一部に残り、今後も彼ら自身の物語として語り継がれることを思い浮かべながら…。この作品が劇場公開となるか、テレビ放映の形を取るか、DVDで販売されるのか、現時点では分かりませんが、作品を継承していくという事実が大切なのです。 —— 第100歩兵大隊、第442連隊戦闘団の退役軍人に伝えたいことは。 心の底からの感謝の意です。私が手掛けた多くの舞台や映画の脚本は、彼ら退役軍人の話が中心となっています。私は何年もの時間をかけて多数の退役軍人と会い、質問を投げ掛けました。そして、彼らは必要以上の答えを返してくれました。過去の記憶を分かち合ってくれたことに対する深い感謝の気持ちで一杯です。作品を通して、彼らにこの気持ちが伝わればと願っています。彼らの努力と犠牲があったからこそ、私たちの世代、そして未来のアジア系アメリカ人の全世代にも素晴らしいチャンスと自由が保証された豊かな人生が与えられています。そう思うと、私はとても誇らしい気持になり、自分の夢や希望も実現可能であることに思いを馳せるのです。それが先代の残した功績に負うものであることも ̶̶ 。 ——これらの全てを成し遂げた今、次の目標は。 私は始めたばかりなのです。また新しいスタートを切りますが、言ってみれば、今は初作品を作り終えたような気分ですね。これからも舞台と脚本家の道を突き進んでいきます。映画のアイデアも結構あるので、その計画も具体化していきたいと思っています。“Only the Brave”に出演した俳優全員が「次はどうするのか」と私に尋ねてきます。彼らは意義深いストーリーが語られる作品に関わりたいと願っているのです。ですから、彼ら全員に「次の作品にも是非出てくれ」と言い続けています。次作には巨額の製作費を投じることになりそうです。そうすることで、より多くの素晴らしい人々に参加してもらえますから ̶̶ 。 (2005年11月16日号に掲載) |