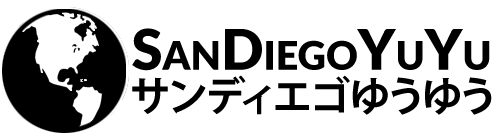ゆうゆうインタビュー 金井紀年
 |
| —— 現在のお仕事について話して下さい。 共同貿易(Mutual Trading Co., Inc.)という、日本の食品とその関連雑貨を取り扱う食品商社を経営しています。現在、社員は250名を数え、7,000点の食品と9,000点の雑貨を扱っています。日本の食品の輸出入に携わっているほか、酒、味噌、海苔、うどんなどの商品を現地で生産しています。私は1964年に就任した3代目の社長です。 
戦地より自宅に戻って両親と。戦死を疑わなかった息子の帰還で母・くにさんは号泣。その直後に自宅の焼跡で撮影した写真。右は父・十郎平さん (1946年7月28日)
中学 (現在の都立北園高校) になって自分の進路についてあれこれ考え始めたのですが、その頃の日本は海外進出が盛んで、将来は貿易商人になろうと思いました。私に「貿易の道へ進め」と言ってくれた親父の影響もありましたね。貿易商人になるには東京商科大学 (現在の一橋大学) の経済学部がいいだろうと思い入学しました。 ところが、大学在学中に学徒出陣を命じられたのです。私はシンガポールで経理を学び、その後でビルマに赴きました。ビルマの戦地では経理を担当し、現金出納、食糧補給と仕入管理、さらに衣類補給と管理を任されました。戦地での3年間は、食糧をどのように調達し、どこで調理をするか、どんな方法で兵士たちに食事を提供するかという難題を解決する役目、つまり兵站 (へいたん) の任務に就いていたのです。 終戦を迎えて、屋根瓦製造、住宅建材やディーゼル自動車の部品を製造する事業に手を染めました。本格的に貿易事業を始めようと思った時に「商社には行きたくないが、自分で貿易をしたい。一体、何をやればいいだろう」と悩んでしまい、親父に相談したところ、約30年の滞米生活を終えて日本へ引き揚げていた石井忠平さんという知人を紹介してくれたのです。石井夫人が私の母と群馬女子師範の同級生でした。 やはり貿易の対象はアメリカという思いが強く、私は石井さんの家を訪ねました。石井さんはアメリカで食料品店 (グロサリーストア) を経営した経験を持っていました。「アメリカには大勢の日本人が生活していて日本食に飢えているから、日本の食品をアメリカに輸出する仕事の準備をしている」と言うのです。そこで、石井さんと一緒に貿易会社を設立することにしました。自分が出資する40万円と石井さんの60万円を合わせた計100万円の資金で、日本の食品を扱う商社、東京共同貿易を創業したのです。 軍隊で食糧補給の仕事をしていたので食品に関しての知識は備えていました。戦時中に500種類に及ぶ料理方法やカロリー計算などを勉強したこと、それに食糧輸送に関わった経験は食品商社を経営する上で役に立っていますね。 
東京商科大学予科時代。19歳の時に親友と。右端が金井氏 (1942年)、このうち2人は戦死。
日本が戦争に突入していった時代に少年期、青年期を迎えたわけです。当時の旧制中学 (高校も含む) や大学では教練が週に2時間ありました。教練というのは「兵隊ごっこ」のようなもので、走り回り、這い回るという訓練を通して兵役の基礎を叩き込まれたのです。法律が変わり、教練を受けた学生は兵士として戦地へ送られることになりました。近眼の私も強制的に召集されました。 戦地で海外事業についてのヒントも得ており、その意味での戦争体験は有益でしたが、一方で人間不信に陥りました。終戦直前に死守命令 (お国のために死を賭して戦うこと) が下りたのですが、その時に命令を出した上官 (日本軍の司令官) は私たち部下(将校)を見殺しにして、全員が転進 (退却)してしまったのです。自分たちは逃げたくせに、部下たちには命を捨てろというわけです。部下を見捨てた上官を目の当たりにして、権威というものが信じられなくなりました。当時の私は20歳で純真だったこともあり、ショックは大きなものでした。 終戦を迎えて、私はビルマの首都ラングーン (現在のヤンゴン) から命からがら撤退してきました。捕虜生活を1年間経験、帰国して両親との再会を果たした時、私が既に戦死したと思っていた母は号泣していました。戦争が終結した喜び、そして命が救われた喜びを強く感じました。大学にも復学しましたが、卒業して企業に入社するという身の振り方には抵抗がありました。軍隊で嫌というほど権威というものの正体を見てきましたからね。つまり、体制や既成組織の下で働くことが馬鹿馬鹿しくなっていたのです。これからは自分の意思と才覚で生きていこうと思いました。戦争で友人も亡くして何も残っていなかった私は、もう一度自分の人生を考えてみたかったのです。 —— 渡米するまでの経緯は。 日本の食品をアメリカ向けに輸出していた東京共同貿易の社長時代に、アメリカの共同貿易の社長を務めていた石井さんが亡くなり、私がロサンゼルスに赴くことになりました。石井さんの死が渡米の契機になりましたが、遅かれ早かれ、私はアメリカに来ていたと思います。戦争に負けたからといってアメリカが憎いと思ったことはありませんでしたし、日本食をアメリカに広めたいと強く思うようになっていましたから̶̶。妻、息子、娘を連れてロサンゼルスへ移住したのは1964年のことでした。海外で事業を始めるには、自分がその土地に行って物事を考えなくてはいけない。異国で骨を埋める覚悟が無いと成功しません。私はその覚悟を胸に秘めて41歳で渡米し、82歳の現在に至っています。 
家族4人で渡米。羽田空港から飛行機に乗り込む (1964年)
当初は、主に日本の缶詰製品をアメリカに輸入していました。いわゆる日本人向けの「望郷食品」です。その現状を変えようと、様々な日本の商品を導入しました。日本人のマーケットは規模が小さいので、アメリカ人の間に日本食を広めていこうと考えたのです。アメリカ人に何を売ろうかと考えあぐねた結果、先ずハーベストクッキーと薄焼きせんべいに目を付けました。これは売り上げが好調で非常に儲かりましたが、3年ほどしてアメリカの会社が製造した類似品に市場を荒らされてしまいました。次に思い付いたのは、アメリカの家庭用品の缶切りやステーキ用ナイフなどを日本へ輸出することでした。これもよく売れました。 その頃にユダヤ系アメリカ人のハリー・ウルフと知り合い、彼を雇い入れたのですが、自分自身を売り込んだ彼の言葉がユニークでした。「アメリカで事業に成功したいのなら、優秀な弁護士、医者、そしてユダヤ人の友人を持つことだ。僕を雇ってくれ」と言ったのです。事実、ウルフは有能なコンサルタントとなり、私の右腕として働いてくれました。 ウルフと日本に出張した時、神田の寿司屋に彼を連れていったところ、「これはアメリカには無い食べ物だ。次は寿司でいこう!」と熱っぽく私に言うのです。その当時、アメリカでは坂本九の『上を向いて歩こう』が『スキヤキ』という題で大ヒットし、すき焼き、照り焼き、天ぷらなどの料理を中心とした日本料理店が数軒ありました。しかし、ロサンゼルスでは江戸前の握り寿司を出す店は皆無に等しく、むしろウルフのアイデアは斬新で成功の可能性が高いと確信したのです。早速、寿司のネタ(刺身)を日本から空輸し、寿司職人も招いて、当時のリトル東京を代表する料亭「川福」に本格的な寿司バーを開くことになりました。「栄菊カフェ」と「東京会館」にも寿司コーナーを開設しましたが、その時に「東京会館」で寿司職人として腕を振るった真下一郎さんが現在のカリフォルニア巻きを考案しています。 —— アメリカから学んだことは。 本格的に渡米する前の約10年間は出張で日本とアメリカを頻繁に往復していました。初めてプロペラ機でロサンゼルスに降り立ったのが1956年11月でした。その時に見た光景にびっくりしました。日本の車とは比較にならない高速度で行き交う自動車の波。公衆トイレは水洗で、しかも手拭き用ペーパータオルまで備えられているし、洗面所ではふんだんにお湯が出る。ダウンタウンの通りは清掃が行き届いていつもピカピカ。郵便ポストの脇には小包みと一緒に送料と郵便局員へのチップが置いてある…何て豊かな国だろうと思いました。 たまたま飛行機で隣席だった人が私を自宅に招いて、食事までご馳走してくれて、そればかりか共同貿易のオフィスまで送ってくれました。「へぇ、アメリカには親切な人がいるもんだ」と感激したものです。親切であること、精神的余裕を備えることの大切さを学びましたね。アメリカの豊かさの源はこのエネルギーだと思いました。日本に足りないのはこれだと直感したのです。 
共同貿易 (当時の建物) の前で森茂氏 (現副社長) と。左が金井氏 (1964年)
終戦後、学生時代に屋根瓦製造の事業を興して軌道に乗せたのですが、学生ビジネスの未熟さからか売掛金の回収が滞り、180万円(現在の10億円に相当)の借金が生じてしまい、一生かけても返せないと落胆していました。結果的に2年半で返済できたのですが、あの時の苦しみは生涯忘れることができません。自殺を考えたほどでしたから。 渡米した当時は、英語もできるし、食品に関しての知識もあったので自信満々でしたが、ロサンゼルスに住む日系人から「アメリカの日系人は日本食をあまり食べないから、市場としては小さいですよ」と言われ、厳しい現実を目の当たりにしたこともありました。 —— 人生の中で印象に残っている出会いは。 ビルマで食糧補給を担当していた時に出会った1人の中国人が鮮明に記憶に残っています。30年の歳月をかけて育てたゴムの木を日本政府の命令で伐採しなければならなくなったのです。これからゴムの木の樹脂を取り、事業を開始するという展望が開けた矢先のことでした。日本軍の計画はゴムの木を倒し、その土地に兵隊の食糧となるタピオカの木を植えるというものでした。「成長している木なのに惜しいことですね」とその中国人に話し掛けると、意外な反応が返ってきたのです。「日本政府の命令だから仕方のないことです。だけど、戦争は長く続かない。終戦を迎えたら、またゴムの木を植樹すればいいのです」と平然としている。「でも、あなたが生きている間にゴムの木は育たないでしょう」と私が言うと、「私の子孫の時代にゴムの木で事業ができます」と恬淡 (てんたん) としているのです。目先のことではなく、何世代も先の時代に希望を託している彼のスケールの大きさに私は驚かされてしまいました。 その時に、海外で生きている人間はスゴいと思いました。その土地に骨を埋める覚悟で、ビジネスの理想を掲げて国外に進出していくということ…それは人生を意気に感じる生き方だと思いました。戦争という災難に遭遇しても、決してその運命に逆らわずに冷静に物事に対応する姿勢が大切だと、この中国人から学びました。彼から受けた薫陶が私のアメリカでの生活に役立っています。 また、これまでの私の人生に重大な影響を与えてくれた人物の1人として、父の十郎平を挙げないわけにはいきません。74歳で生涯を閉じましたが、常に「自分にできる仕事をしろ」と言いながら、私の人生の節目節目に貴重なアドバイスを与えてくれました。言うまでもなく、ビジネスパートナーだった石井さんと参謀役のウルフも我が人生に多大なる影響を与えています。 —— 座右の銘は。 「原点に戻る」です。私は自分の信念に基づいて、独自の方法論で海外事業を進めてきたので、様々な障害に直面してきました。言い換えれば、試行錯誤を重ねながら学んでいくという行動を貫いているので、予期せぬ問題が生じることが多いのです。そういう時に原点に戻るのです。 例えば、借金をした時は「返済する」ことが原点になります。 何よりも、如何にして完済するかを考えなければならない。つまり、現実的に物事に対処するわけです。「先ずは、負債をゼロにして出直す」ことを念頭に置くことで発展性が生じてきます。ハーベストクッキーで失敗した時も原点に戻りました。アメリカ人が好んでいる米国風の商品を売り込んでも将来性が乏しいので、日本の食品文化で勝負するという考えに至ったのです。アメリカ人が真似できない寿司をこの国に普及させようと考えたのも、まさに原点に立ち返ったからです。 
ペルーのアルベルト・フジモリ大統領を表敬訪問した時。中央は妻の富佐子さん (1991年)
私は常に幸せです。他人を批判したり非難することもほとんど無く、全てに対して有難さを感じているからでしょうね。やはり、戦争体験からこういう気持ちが生まれていると思います。先日、ロサンゼルスの講演会で「思い出に残る旅行」というテーマで話をしたのですが、皮肉にも出征経験が私の心に残る旅になりました。終戦の知らせを聞いて、友達と手を握り合ったあの時が至福を感じた瞬間ですね。命が救われたという歓喜に近い悦びが全身に沸き上がっていきました。この時から私は性格が一変したように思います。世の中の森羅万象に感謝の念を抱くようになったのです。生きていることが本当に有難いと思えるようになりました。 ——新しい夢は何ですか。 未だ実現していない計画は、最高の味を誇る日本の魚をアメリカに輸入することです。アメリカでは口にできないサンマやアジ、そしてカツオなどをとびきり新鮮な状態で食卓に運びたいのです。ー65℃で冷凍して運び込むことで、それが可能になります。新鮮さと美味しさを保つにはこの温度が最適なのです。昨年11月にー65℃の超低温冷凍庫と倉庫が完成したので、今後、日本の家庭で食べている魚をどんどん輸入していくつもりです。近い将来、この夢も必ず実現します。 1923年生まれ。東京府豊多摩郡落合村 (現在の東京都新宿区下落合) 出身。元教員で文部省に勤務していた父・十郎平さん、同じく教員だった母・くにさんの間に生まれる。東京商科大学予科 (現・一橋大学) 経済学部を卒業したが、戦争中にシンガポールの経理学校で経理を学び、学徒出陣でビルマ (現在のミャンマー) へ出征。終戦後に大学へ復学。在学中に屋根瓦製造会社のテラ・セメント工業を設立したが、多額の借金を抱えて閉鎖。負債返済のために、住宅建材事業と ディーゼル自動車部品の製造販売を行う。借金返済後、1952年に富佐子さんと結婚。父の紹介で国際的事業家の石井忠平氏と出会い、食品商社の東京共同貿 易を2人で設立。ロサンゼルスの共同貿易 (1926年創立) の日本側窓口だったが、後に石井氏が共同貿易の社長に就任。石井氏の病後、1964年より妻と1男1女の家族4人でロサンゼルスへ渡り、共同貿易3代目社 長に就任、現在に至る。南加日本商工会議所会頭、日米文化会館理事、パンアメリカン日系協会会長、ロサンゼルスの東京会、群馬県人会、県人協議会顧問、裏 千家LA協会副会長など、数多くの役員を務める。「海外選挙を実現する会」の会長でもあり、在外選挙活動でも活躍し目的を達成した。 (2005年2月16日号に掲載) {sidebar id=29} |