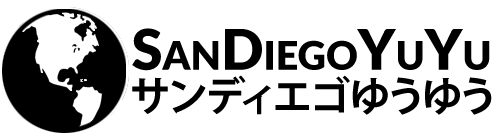ゆうゆうインタビュー 福田光代
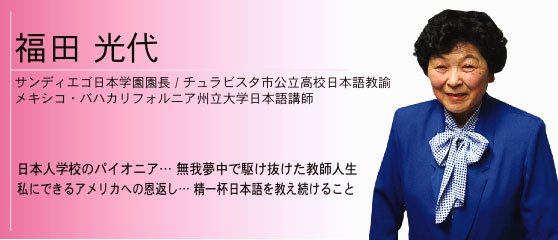 |
| —— ご自身が園長を務めるサンディエゴ日本学園について教えて下さい。 1974年2月2日、日系企業進出に伴って増加する日本人駐在員家族、並びに米国籍やメキシコ籍の子供達への日本語教育の場として、非営利法人サンディエゴ日本学園を創立し、日本語を家庭語とする子弟たち、英語、スペイン語を家庭語とする子弟たちのグループに分けて指導を始めました。現在は毎週土曜日に小・中・高校に分けて日本語教育を行っています。生徒たちが日本の言語、文化、習慣、情緒を身に付けると同時に、他民族の言語や文化をも尊重するという心を育み、豊かな情操と思いやりの心を持ち、幅広い国際人として成長することを目標に、教師一同、日夜努力を続けています。 ——学園創立の経緯は。 牧師をしていた主人の仕事の関係で1968年にサンディエゴへ来ました。私は、日本の小学校やブラジルの日本人学校で教師の経験がありましたので、アメリカでも小学校教諭に挑戦してみようと思いました。ところが、アメリカで教えるには、歴史と憲法はこちらの大学で新たに学ぶ必要があると言われ、「それなら全教科英語で学び直そう」とサンディエゴ州立大学へ入学し、カリフォルニア州 (8年生までの) 教員免許を取得しました。そして、地元の小学校教諭となって数年が経過した頃、日本人駐在員家族や日本語に興味を持っている人々から「日本語学校を開いて欲しい」と依頼されるようになりました。そして、今まで日系人の方々が築き上げてこられた努力に倣ってサンディエゴ日本学園を創立しました。 —— 学園設立の際に苦労したことは。  一つの学校を建てるには大変な努力を必要としますが、経営面では特に苦労しました。開校された学校に自宅にあったピアノを運んでくるなど、必要最小限の物を集めて教室を作りました。主人も私も学園の運営資金のために外で働いているような状態でした。サンディエゴへ渡る前はブラジルに7年間滞在しており、そこで日本人学校の創立に携わっていましたので、その経験を生かして学園作りに奔走してきました。そして、私達の話を聞いて下さる方々も徐々に現れ、ロータリークラブ、海上自衛隊、国際交流基金などから多くの支援が寄せられるようになりました。笹川財団からは10年間に亘り御援助を頂き、1980年にはサンディエゴ日本学園図書室を開設することができました。また、サンディエゴ在住の日系人、友和会の方々、アメリカ人の方々の御支援にも感謝しております。 一つの学校を建てるには大変な努力を必要としますが、経営面では特に苦労しました。開校された学校に自宅にあったピアノを運んでくるなど、必要最小限の物を集めて教室を作りました。主人も私も学園の運営資金のために外で働いているような状態でした。サンディエゴへ渡る前はブラジルに7年間滞在しており、そこで日本人学校の創立に携わっていましたので、その経験を生かして学園作りに奔走してきました。そして、私達の話を聞いて下さる方々も徐々に現れ、ロータリークラブ、海上自衛隊、国際交流基金などから多くの支援が寄せられるようになりました。笹川財団からは10年間に亘り御援助を頂き、1980年にはサンディエゴ日本学園図書室を開設することができました。また、サンディエゴ在住の日系人、友和会の方々、アメリカ人の方々の御支援にも感謝しております。—— ブラジルに滞在していた頃の話を教えて下さい。 1961年に主人のミッショナリー派遣に伴い、娘と息子を連れてブラジル南東部のミナスジェライス州の奥地へ赴任しました。リオデジャネイロから列車で9時間も掛かる何も無い山岳地帯の町でした。現地人は大人でも裸足で歩いているような所でした。米は食べられても農作物はほとんど無く、幼い息子が家の前に生えている雑草を指差して 「あの草が食べたい」と言う程でした。 私達がブラジルに着いた後間もなく、町の周辺に日本の出資による南米一の製鉄所となるウジミナス製鉄所の建設が始まりました。平均3年の任期で駐在する日本人家族が増加し、子供達を野放し状態にはできないということで、世界初の全日制日本人学校 (小・中・高校部) となったウジミナス日本学園の経営を委嘱されました。1962年に開校しましたが、当初はアパートの1軒分を借りて授業を行いました。生徒は常に30~40名を数えていましたが、教師は私達とブラジルに移住していた日本人女性の合計3人のみでした。そのうち、八幡製作所や富士製鉄所に務める駐在員の方がボランティアで科学を教えたり、生徒の母親で英文科を卒業している方が英語を教えてくれるように なりました。教科書は日本から送られてきましたが、それ以外のものは容易に手に入りませんでした。物資は無いながらも、子供達も父兄も皆で一生懸命頑張りました。音楽発表会、学芸会、運動会と何でも徹底的に行いました。1967年には美智子妃殿下より御植樹を賜りました。 ブラジルで過ごした7年間は私達にとりまして生涯忘れ難い思い出となっています。 ——教師になろうと思った動機は。 私達が学生の頃は日本は経済的にまだ大変な時期でしたので、女性の大学進学率も低く、職業も限られていました。父から「女性は教師になるのがいい」と常に言われていましたので、大学の教育学部へ進学して卒業後は横須賀市内の小学校に勤務しました。クリスチャンの家庭で育った私は、後に主人と日本の教会で出会いました。主人は牧師になる目的でケンタッキー州ルイビル長老派神学校へ留学。私も1956年に同市のルイビル南バプテスト神学校へ留学し、教会音楽と指揮法などを勉強しました。 —— 渡米の夢は昔からお持ちだったのですか。  幼い頃から一度は訪れてみたいという気持ちはありました。それは父をクリスチャンに導いたアメリカの宣教師婦人ミス・エステラ・フィンチ (帰化名は星田光代) の素晴らしい人となり、生き方を常に父から聞いていて、そんな立派な人を輩出した国に行ってみたい、それにエレナ・ポーター作の 『少女パレアナ』 の通うような教会にも行ってみたいと夢のように思っていました。実は、私の祖父は1905年に単身渡米して亡くなるまでアメリカで暮らしていました。不幸にも日米開戦を迎えて帰国できなくなってしまったのです。終戦後のある日のこと、「日本に帰りたい…」との思いが綴られた手紙が父のところに届きました。父が「どうぞ帰って来て下さい」と伝えようとした矢先に肺ガンで亡くなったという連絡を受けました。そういう経緯もあり、何となく幼い頃からアメリカを身近に感じていましたし、祖父が暮らしていた国を見に行きたいとも思っていました。 幼い頃から一度は訪れてみたいという気持ちはありました。それは父をクリスチャンに導いたアメリカの宣教師婦人ミス・エステラ・フィンチ (帰化名は星田光代) の素晴らしい人となり、生き方を常に父から聞いていて、そんな立派な人を輩出した国に行ってみたい、それにエレナ・ポーター作の 『少女パレアナ』 の通うような教会にも行ってみたいと夢のように思っていました。実は、私の祖父は1905年に単身渡米して亡くなるまでアメリカで暮らしていました。不幸にも日米開戦を迎えて帰国できなくなってしまったのです。終戦後のある日のこと、「日本に帰りたい…」との思いが綴られた手紙が父のところに届きました。父が「どうぞ帰って来て下さい」と伝えようとした矢先に肺ガンで亡くなったという連絡を受けました。そういう経緯もあり、何となく幼い頃からアメリカを身近に感じていましたし、祖父が暮らしていた国を見に行きたいとも思っていました。—— 現在はサンディエゴ日本学園の運営以外にも活動されているのですか。 平日にはヒルトップ高校、ボニタ・ビスタ高校、そしてバハカリフォルニア州立大学の日本語講師を務めるようになり、かれこれ16年になります。考えてみれば、サンディエゴ日本学園があったからこそ高校や大学で教えるチャンスに恵まれたと思っています。当時私が所有していた教員免許は高校で5年間は日本語を教えることができたのですが、それ以上継続して指導するためには高校の教員免許が必要でした。5年が過ぎた時に、私は更にカリフォルニア州の高校免許証を取得するために、ロサンゼルス州立大学で研修しました。週2回、高校の授業が終わってから3時間掛けてアムトラックでロサンゼルスへ向かいました。授業終了終、夜8時45分の最終列車に飛び乗って車内で勉強や食事をしていましたから、今でもあの 「ポー」 という汽笛が聞こえてくると懐かしくなります。試験で遅くなり最終便に間に合わない時は、バスでサンディエゴまで帰ってきました。卒業までに2年半を要しましたが、自分でもあの頃はよく頑張ったと思います。 —— 教師の立場から日米における文化の相違を感じることは。 日本生まれで日本語を母国語とする私のような者でも、資格さえあれば一市民として平等に仕事が与えられ、しかも年齢に関係無く仕事を続けられるのは素晴らしいことだと思います。日本では50歳を過ぎた頃から「肩叩き」なんて聞きますよね。私も不安になって高校の人事部に尋ねたことがありました。すると、「あなた、耳は聞こえるんでしょ? 2本足で立てるんでしょ? それならいつまでも働いて下さい」と言われたのです。教師という職業に限らず、やはりアメリカという国は建国の精神に基づいているんだなと感じますし、私はこの国の伝統文化を心から尊敬しています。 —— ご自身が至福を感じる時は。 そうですね。日本学園の園長としても、高校の一教諭としても、卒業生の成長を見るのは楽しいものです。先日もエール大学に進学した女生徒が、大学名の入ったTシャツを着て遊びに来てくれました。誇りに思えるほど嬉しかったのでしょう。レベルの高い学校に進学することだけが良いという訳ではなく、どの生徒であっても立派に自立している姿を見ると嬉しくなります。数年前にホートンプラザ内のベーカリーに行った時、何を買おうかとケースを見ていると、突然店の奥から「ミセス・フクダ!」と叫ぶ声がしました。見ると、真っ白な作業服に身を包んでパン職人として働いている高校の教え子でした。彼は高校時代はフットボールの選手でしたから元気のいい子でしたけれども、勉強をしない生徒でね…。でも、その彼が「先生、僕の作ったパンだから是非持っていって!」と言ってくれたんです。あの子が立派に働いて、しかも自分に声を掛けてくれたと思うと、本当に嬉しかったですね。 1人の人間として、またこうしてアメリカで安心して生活させて頂いている恩返しとして、精一杯日本語教育に尽くしていく覚悟です。教育活動の結果は直ぐに分かるものではありませんが、いつの日か活動の成果が現れることを信じて、若い人達の成長に寄与していきたいと思っています。 (2003年12月1日号に掲載) |