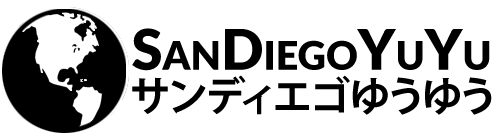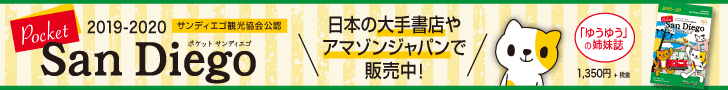Featured

(2024年3月16日号に掲載)

 |
▽私が通った小学校は明治政府が近代学校制度 (学制) を公布した翌年 (明治6年) に建てられ、60年前に入学した時点で90年以上の歴史を刻んでいた。谷崎潤一郎が著書『陰翳礼讃』で「日本美の核心は影の深みにあり」と絶賛したように、古色蒼然たる校舎には風趣があったものの、朽廃が進んで修理が連日続いていた。階段の上部には、巨大なゼンマイ式時計が故障したまま10時25分を指していた。修理不能で放置されていたが、真夜中にボーンボーンと鳴り出すこともあり、宿直の先生が肝を潰したらしい。修理の域を超えた校舎は私が卒業した数年後に取り壊された。現存していれば、国指定重要文化財の旧遷喬 (せんきょう) 尋常小学校 (岡山県真庭市/明治40年築) にヒケを取らぬ国家遺産になっていたはず。▽昭和初期に建てられた私の生家は格式を備えていたが、無理な増築と修理を重ねて不気味な内部構造になっていた。三階建てなのに「中二階」 が二階下にあり、実際には四階建て。一階から最上階に直通する急勾配の長い階段は、踏み外せば命を落としかねない。各部屋を結ぶ廊下が枝葉のように分かれていて、そう簡単に戻れない。遊びに来た友達全員が帰ったはずなのに、誰かが迷子になり、日が暮れてから台所にヌッと現れて、母が「うわっ!誰!?」と仰天することも一度ならず。旧家は30年前に解体された。(SS) |
 |
|
 |
▽「納得いかない…」。 昨年末、長く愛用してきたウォシュレットから水が漏れ出した。YouTubeで調べたところ、パーツ交換で直せると知るも、メーカーは撤退済み。問い合わせた他の会社も対応してくれない。「どんなウォシュレットも修理OK」という業者に依頼したところ、彼らにトイレの全交換を勧められてしまった。小さなパーツ交換で済むはずなのに…。納得できず、修理を諦めて止水栓を操作して使用している。▽「思わず、ウルウル…」。日本の友人が、お父様の遺品である40年前のビデオカメラを修理し、懐かしい映像を復活させた。この奇跡を起こしたのは、三重県の山奥に住む「修理の神様」こと今井和美さん。販売終了の家電を95%以上の成功率で修理する今井さんを、友人はテレビ番組で知ったそうだ。中学卒業後、独学で修理技術を習得した今井さんには、全国から依頼が殺到している。彼の手によって、多くの人々の貴重な思い出が蘇っている。▽「もっと貯筋しよう…」。齢を重ねるにつれて、友人・知人との会話の中で、健康に関するトピックがグッと増えてきたことに気づく。家電製品は 「修理/修繕」によって長く使い続けることができるが、人間の体はそう簡単にはいかない。日常のメンテナンスの重要性を深く実感するようになった。 (NS)
|
 |
毎日暮らしていると、いろいろなものが壊れて修理が必要になるものだ。△今の家に移り住んだとき、元の住人の冷蔵庫と洗濯機がそのまま残されていた。どちらもかなり年季が入っていたが、順調に作動するので、そのまま使うことにした。2、3年経った頃、まず調子が悪くなったのが冷蔵庫。片方の扉の取っ手が外れかかり、ダクトテープで応急処置。一時しのぎのはずが、それでも案外大丈夫で、結局、その後1年ほど使い続けた。次にガタが来たのが洗濯機。夫がどこかをいじったら動くようになり、それを何度か繰り返しているうちに全く動かなくなってしまった。そこで、ようやく新しい洗濯機を購入。節水機能で静かだし、大容量でたっぷり洗えるという感動ものだった。△ここ最近の大雨続きで、我が家もついに雨漏りを体験。この家に住んで十数年、問題なかった屋根にもついにガタがきたようだ。屋根にタープを敷いて雨漏りは一応ストップしたが、そろそろ屋根の修理を決断しないといけない。築70年近くの歴史ある(?)家なので、やはり、あちこち修理・修繕が必要なところが出てくる。古くて小さくても愛着ある我が家。これからも暮らしやすく整えていきたい。(RN)
|
 |
現在の住まいに引っ越して20数年。サンディエゴに移住する前は、東京は世田谷区の築20年の集合住宅を入居前に改装し15年間住んでいた。以来、サンディエゴに来るまでの間、外装の大掛かりな修繕工事は一度だけだったが、内装の修理修繕を行った記憶はない。とりあえず、物事は順調に進んでいた。現在の住まいもそれなりに年数を重ねている物件だが、前居と違い、入居以来、キッチン、バスルームなど何度となく修理修繕を重ね、その度に、より快適な住まい空間への道を歩んでいる。それらの最初の修繕工事がまさに悪夢だった!! 普通、アメリカの住宅にウォシュレットはない。それを使い慣れていて、それなしでは快適な生活が送れないことを日本人はよく知っている。ということで、この住まいに引っ越すなりウォシュレットを買ってきた。で、経費をケチりたい私は自分で取り付けることに。それがそもそも大間違い! とにかく築年数が経っているので、水道栓のレバーがこびりついている。無理やり動かして何とか自分で取り付けた。その深夜、階下の住人から苦情が入り、水漏れしているという。ひえ~、うっそ~! なんと、その修繕費は約6,000ドル。当時、住宅保険に加入することをすっかり忘れていた私。全額が自分のポケットから。結果、世界一高価なウォシュレットとなった。ウンに見放された話である。あ~めん! (Belle)
|
 |
|
 |
実家は愛知県だけど、年始に初めて横須賀市を訪れた! 今回の帰省で、お母さんは“家族ルーツを辿る”にハマッていた。特に気になっているのは、お爺ちゃんが建てて自分が生まれ育った家のこと。家で撮った1940年代の写真を見ながら「この家はまだあるのかなぁ」とブツブツ。そんなのGoogle Mapで確かめればいいじゃんと思い、探してみたらすぐ見つかった 笑。で、Google Mapを頼りに、その家を目がけて、わたし一人横須賀へ。家は割と簡単に発見できたけど、わたしのミッションは家に入ること 笑。見つけただけでは帰れない 笑。不法侵入はするなと注意されてたけどピンポンがない。ちょうど近所のおばちゃんがいて頼んだら、居間にいた住人の方を呼んできてくれた。事情を説明すると、快く庭を案内してくれた。お母さんが言っていた鯉がいた池とプールは埋めたそう。縁側の向こうに居間の障子が見えた。これって、お母さんが見せてくれた写真と同じじゃん!となり、住人の奥さまに「わたしここの写真持ってます!」と興奮して伝えたら、家に上げてくれた 笑 (ミッションクリア! 笑)。お爺ちゃんが転居してすぐこちらのご家族が入居。4世代が住み続けている。屋根は修繕、内装はそのまま大事に維持されてきたそう。奥さまと連絡先交換、すっかり仲良しに 笑。次回は、まるで実家に帰るように堂々と遊びに行くよー! 笑。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
夫は何でも自分で修理したがる。現在住んでいる家に来て1、2か月経った頃だっただろうか、私は子供を学校に送ろうとして、車庫から車を出すためにバック発進したところ、まだシャッターが上がりきっておらず、なんと車で押してブッ壊してしまった。それからはシャッターが開閉不能となり、修理する羽目になった。普通なら、すぐにプロの修理屋さんに来てもらうところなのに、夫は自分で修理しようと試みた。まずYouTubeで検索…。ちょっと待って! 私が破壊しておいて申し訳ないけれど、とっとと修理屋を呼ぼうよ。労力や時間を考えると、費用は掛かっても、業者さんに任せるのが最善策と思うのだ。餅は餅屋に頼むのが一番という考えの私は、夫が何かと家の修理をしようとする度に、心の中で「プロに頼んでよ」と思ってしまうのだ。しかし、ナンダカンダと自分で直して、結構しのいできたので、それもスゴイとは思うけど…。子供が蹴り抜いた壁の丸い穴もキレイに修繕したし、キッチンのシンクに焼酎グラスが落ちているのを知らずに、ディスポーザーを回して動かなくなった時も回復したし。・・・考えてみると、結構、私と子供たちで自宅を破壊しているかも? どうもすみません。(SU) |
(2024年3月16日号に掲載)
Featured

(2024年3月1日号に掲載)

 |
▽長年使用していた furnace が故障したので高額な暖房システムを導入した。セントラルヒーティングなので家中が暖かくなっても、光熱費の上昇ペースはスカイロケット級。そこで1人に1枚ずつ、LED表示のタイマー付き電気ブランケットを買い入れ、furnece を稼動させずに冬の日々を過ごした。節電効果は大成功! 見事なまでに家計を助ける省エネとなった。微力ながらも、各家庭がエコ生活を実践すれば地球温暖化対策に貢献できる。▽「省エネ」は「省力」にあらず。子供の頃、私と弟は10日間ほど知り合いの寺に預けられ、そこから小学校へ通った。日課は朝夕の「落ち葉掃除」。掃き清めても、翌日には枯れ葉が境内に落ちてくる。「2日に一度でいいのでは?」と先延ばしを願い出た私たちに、若いお坊さんが柔和な笑顔で「心を掃くんだよ」と一言。毎日、苦もなく俗事を続ける平常心が大事。やがて魂が浄化されて往生できる。明日死のうが、百歳まで生きようが、人生の質を高めたいなら「心の省エネをするな」ということらしい。▽多忙を極める人気俳優 T・Kさんの名言が光る。「手を抜いた仕事は、より疲労感が残る」。悟られないように適当に仕事を切り上げても、真剣に取り組まなかった不全感/罪悪感が自分を苦しめて精神的に数倍も疲れてしまう。「省エネ」と「省力」を履き違えてはいけない。(SS) |
 |
|
 |
▽日本にいる姪は、昨年、コンロや給湯機を電気からガスに替えたそうだ。ひと月の電気代が10万円を超え、オール電化住宅を諦めたとのこと。サンディエゴの友人は、セントラル空調をやめて、部屋用エアコンを取り付けた。自分は電気代が半額になる「スーパーオフピーク」の時間帯を狙って料理や洗濯をしている。▽仕事の省エネや時短は不可欠だが、最近、断られた → 返信しない「メール1往復主義」を採用する人が増えている気がする。「またよろしくお願いします」という「一往復半」に慣れている自分としては、何となく寂しい気分になる。▽急激に食事量を減らすと、人間の体は飢餓から身を守ろうとして「省エネモード」に切り替わるらしい。この状態で食事を摂ると余ったエネルギーが脂肪として蓄えられてしまう。リバウンドしちゃったけど、またダイエットすればいいや!と、安易に考えていたら、相撲部屋の新弟子検査に合格できる体重に近づいていた。▽人間の脳は「省エネ」を好むらしい。脳はとても小さいけれど、体が消費するエネルギーの20%も消費するので、時々「サボりたい」と思うらしい。だから、大切なことに集中することを心がけて、他のことは習慣にしてしまうと、脳が疲れにくくなるそうだ。何もしたくない時でも、とりあえず、何かを始めて10分ほど続けていると、不思議とやる気が出てくるという。(NS)
|
 |
省エネで思いつくのは、エアコン停止、使わない部屋の消灯、誰も見ていないテレビを消す、こまめに家電のプラグを抜く——などかな。我が家はエアコンを全く使わない。蒸し暑いときはシーリングファンを回し、それでも暑いとドアを開け、扇風機の風でしのぐ。冷え込むときは厚着をして、まだ寒ければ先日買ったミニヒーターを使う。不要照明の節電は普段から心がけている。私は一人でテレビを見ることがほとんどない。映画やTV番組はタブレットで楽しむことが多い。たまに子供たちがテレビをONにしたままタブレットやパソコンを使っているので、見かねて消すように言っている。節電とはいえ、冷蔵庫、オーブンなどのプラグを抜くことはできない。トースター、電子レンジも使用頻度が高く、抜くのが面倒なので付けたまま。アマゾンのスマートスピーカー Echo はプラグを抜くと作動しないので、もちろん繋ぎっぱなし。TV、DVD Player は、使用しないときはプラグを抜いた方が良いとは思うけれど、とても煩わしくて実行できない。とはいえ、数日間も家を空けるときは、待機電力カットと安全のために、電子レンジ、トースター、TV などのプラグを抜くようにしている。私の家族にとって、これ以上実行できる省エネはないかも——。 (YA)
|
 |
日本のTVバラエティ番組の中でも、『情熱大陸』や『ガイアの夜明け』などの過去に放送された情報番組をネットでよく見る。最近見た番組で、日本最大手の小売チェーン店イオンの省エネに取り組む姿勢が紹介されていて、とても興味深かった。番組によると、イオンの電力使用量は日本全体の0.8%を占めているそうだ。いかに節電をするかが日常の課題。その電力を必要とする最たる設備がターボ冷凍機という冷房機器で、その使用量を下げるため、春と秋は館内を自然換気方式に変更。自動で窓を開閉させ、AIで空調をコントロールして、2022年5月は7.4%、10月は7.5%減に成功したという。また、エリアごとの照明の明るさやエレベーターの稼働数を調整するなどして、徹底的な省エネ対策を実施し、それらの電力使用量を50%オフにまで実現した——と番組は報じていた。ごリッパ! 今や、省エネの意識は企業だけでなく、個人レベルにもかなり浸透している。私は海外へよく行くが、そこで出会った人たちに「私は米国サンディエゴに住んでいる。美しい街のみならず、気候的にもパラダイス。年間を通じて冷暖房不要な、世界でも稀 (まれ) な場所」と、我が地の素晴らしさを得意げに紹介する。実際に、昨夏は扇風機さえも使わなかった。これこそ究極の省エネタウン。万歳!! サンディエゴ!! (Belle)
|
 |
|
 |
姪っ子のりさ子は、千葉県の実家に住んでいるんだけど、家に帰ってくるのはなぜか月に2〜3回 笑。都会の事情は分からんが、勤務地が東京駅付近なので、1時間の通勤は面倒というのが理由らしい。確かに時短になるし、満員電車のストレスからも解放される。これ、自分への省エネだわ! 「じゃあ、残り28日間ほどは、どこに泊まってんの?」と尋ねたら、3軒の鍵を持っていて 笑、2つは友達の家、1つは社内恋愛が最近バレてしまった彼氏宅 笑。どういう順番で回っているかというと、その晩に飲みに行く店に近い家に泊まるんだとか・・笑。あやつは、♪ 彼氏といつも一緒がいいーっ ♪ ていう女子ではなく、彼氏の家へ行くのも己れの酒飲みの都合! 笑。それも自分自身のエネルギー節約? ♪ たまーに顔を合わせるのが丁度いいーっ ♪ てなもんで、リタイア後の老夫婦みたい 笑。「ご飯はどうしてんの?」と聞くと、その家にいる子に作ってもらうんだって! 笑。そーいえば、わたしが年始にあやつの実家 (お兄ちゃんの家) に宿泊したとき、「うゎー! X子 (わたしのこと 笑)、ゲストなのにご飯作ってる! スゴーい!」と叫んで、さっさとテーブルに座り、缶ビールを飲み始めるではないか! 思わず「あんたは、わたしにビールをつぎなさい」 と指示したけど、一度だけついで、後はご飯ができるのを待っていた。う、動かない、、。省エネすぎんでしょ! 笑。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
私は普段から可能な限り省エネに気をつけているつもりでいる。使用していない部屋の電気を消す。バスルームで、シャンプーを使い体を洗っている時はシャワーを止める。子どもの送り迎えのついでに、必要な買い物などの用事を済ませるなどして、なるべく車の運転を控える。これはガソリン代の節約にもなる。自慢できるほどの省エネ実践ではないけれど、一応は心がけてはいる。でも、考えてみれば、パソコンはいつもON状態、電気ポットも点けっぱなし。温かい飲み物が欲しい時に、いちいちプラグを入れて湯が沸くのを待つのはイヤというのも人の常。暖房はいつも稼動中。寒いのは苦手だし、家の中で厚着をするのも億劫なので、温度設定も特に低めにしていない。洗濯機は毎日2回ほど回している。4人家族なので、連日結構な量の洗濯物が出る。夫からは「毎日しなくてもいい」と言われるが、2〜3日も溜め込むワケにもいかないし、溢れるばかりに詰め込むのも気が引けてしまう。繰り返しになるけれど、基本的な私の省エネといえば、不要照明の消灯と照度の見直し、シャワーの水量節減、燃料費のセーブを兼ねて車利用の回数を減らすことくらいかな。・・すみません。(SU) |
(2024年3月1日号に掲載)
Featured

(2024年2月16日号に掲載)

 |
▽方言とお国訛 (なま) りに悩んだのは、福島から東京の私立高校に入学した頃。新入生の内訳は、附属中学からのエスカレーター組4割、首都圏組4割、地方組2割。悲惨なのは地方出身者で、私は福島弁 (がおる → 疲れる、くさし → 怠け者) を標準語と勘違いして笑われた。何よりも、言葉の節々に出るアクセントの違いが一番の悩み。現代国語の教師が秋田出身で、福島出身の私と山形出身のF夫を朗読役に指名して「懐しい響きだなぁ」と喜ぶ姿にゾッとした。F夫は苦笑いしていたが、内心は傷ついていた。私は秘かに『NHKアナウンス読本』を買い求めて発音・抑揚の矯正に勤 (いそ) しんだ。そんな15歳の努力を誰が知るだろう。私の訛りは大学時代に消えた。▽東北でも各県の訛りには特徴がある。岩手は抑揚にメリハリがあり日常会話も「日本昔話」になる。仙台は都会で訛り度は低い (それでも少し残る)。福島はモノトーン。青森は早口だと理解不能。津軽弁の響きはフランス語よりコクがある (笑)。▽サンディエゴでプロを目指していた日本人 (19歳男子) からテニスの指導を受け、私の腕前もアップ。彼は “若者言葉” を連発していたが、アクセントに微妙な違いがあった。「東北出身?仙台あたり?」と尋ねたら、激しく狼狽 (ろうばい) しながら「何で分かるんですか!!」(泣)。東北人には分かるんだよ。ゴメン。 (SS) |
 |
|
 |
▽学生時代、山岳部には日本各地から集まったメンバーがいたので、方言にまつわるユニークなエピソードで思わず吹き出したことが何度もあった。例を挙げると、茨城出身の先輩が喫茶店で「マッチ」を所望したところ、運ばれてきたのは抹茶! その時、名古屋生まれの後輩が「先輩、 えっらそうやなぁ」とコメント。名古屋弁の「えらそう」は「疲れてる」という意味と分かった途端、固まっていた皆が爆笑。山行中に転んだ私に、沖縄出身の先輩が 「ヤマシタカ~?」 と声をかけてくれて 「いいえ、佐藤です」と返答。実は「怪我はないか?」という意味だった。そして、青森生まれの同期は津軽弁で自慢げに「桃太郎」を披露してみんなを笑わせた。「鬼ヶ島さ行くはんで きびだんごば こへでけねべが」。▽その昔、沖縄には「方言札」が存在していたことを先輩から聞いた。沖縄が琉球王国から日本の一部になった時、学校で方言を話した者は、次に話す人が現れるまで、罰として木板で作った「方言札」を首からぶら下げたとか。言葉に関する悲しい過去を伝える話だ。▽「さすけねぇ、さすけねぇ」 が祖母や母の口ぐせだった。福島県の会津弁で 「さしつかえない」「大丈夫、大丈夫」というニュアンスで使われている。相手を温かく、大きく包みこむような響きが好きだ。考えてみれば、人生の大半を 「さすけねぇ」 で生きているような気もする。 (NS)
|
 |
▷小学校に上がるとき、東京から茨城に引っ越した。「そうだっぺ」「いがっぺ」「かっぽれ」「ごじゃっぺ」・・。早口の尻上がり調に加えて、独特の強い響きを持つ茨城弁。生粋の茨城っ子の同級生や先生たちのやり取りは、最初の頃はケンカをしているようにも聞こえたのを覚えている。私はその後、ずっと茨城で暮らしていたのに、島根出身の父と東京育ちの母だったせいか、茨城弁に郷愁は感じても、駆使するまでには至らなかった。▷父の実家の島根県出雲に帰省すると、祖父母や親戚の言っていることが理解できす、父に通訳してもらったっけ。「そうだにゃー」「あのにゃー」と、にゃーにゃー可愛かったのもよく覚えている。父の親戚がそうだったのか、出雲の人の特徴なのか分からないが、皆、おっとりと喋るという印象も残っている。▷アメリカに住み始めて数十年。英語の方言の違いも何となく区別できるようになってきた。アメリカのいわゆる南部訛りの英語も、最初の頃はただの英語としてしか耳に入っていなかったと思う。オーストラリア英語、南アフリカ英語もごちゃ混ぜになることもあるけれど、どことなく違うのが分かってきた。それにしても、典型的なイギリス英語の人も南部訛り英語の人も、歌う時は皆が同じように聞こえるのはなぜだろう?(RN)
|
 |
私の人生初のボーイフレンドは津軽の人だった。彼の口グセが「津軽の女と恋愛はできない」。彼の田舎の言葉は津軽弁、通称「ずうずう弁」である。そんなずうずう弁で「わさ、おめぇさのこと、好きだべさ」とコクられても、ちっともロマンチックなムードにはなれない、というのだ。分かる。また、津軽弁とフランス語は発音がよく似ていると言っていた。寒さゆえ、口を大きく開けると、冷気が口に流れ込んでくる。それを防ぐため、言葉数はできるだけ少なく、しかも口を小さく開けてしゅわしゅわっと声に出しただけで相手に通じなくてはいけない。究極ともいえる二人の会話がこれ→「どさ」「ゆさ」。あ?って感じだが、標準語通訳をすると「どこへ行くんですか」「お風呂へ」。双方の会話がたった4文字で用が足りる。確かに便利だ。話は変わって、私は映画が好きでよく観る方だ。映画は日本各地が舞台になっているので、役者さんはその地方の方言を制覇しなくてはいけない。そんな中で、私の記憶に永く留まっている方言でのフレーズがある。「なめたらいかんぜよっ!」。任侠映画『鬼龍院花子の生涯』(1982) で若くして他界した夏目雅子が切ったタンカだ。土佐弁。「甘く見てたらダメだよ」と標準語で言われるより、スゴ味のある方言で吐き捨てられると遥かに威圧を感じる。まさに方言パワー。方言を「軽う見とったらいけんよ」(広島弁)。 (Belle)
|
 |
|
 |
わたしは名古屋で育ち、米国に来て標準語を覚えた (笑)。昔、米国では意識的に標準語を話すようにしてた私だけど、ここずっと、友人H部長に名古屋弁で話し続けていたら、いつの間にか彼に伝染した (笑)。人間って学習能力あるよねーと感心 (笑)。お母さんは神奈川県横須賀の生まれ育ち。大人になって名古屋弁を覚えたから近所のコッテコテのおっちゃんたちとは違う。お母さんと一緒に地元を歩いていたら、畑仕事をしてた幼なじみのお父さんが「いつアメリカに帰るか?」とネイティブの名古屋弁で尋ねてきた。あろうことか、名古屋弁自慢のわたしなのにリスニングができなかった!! お母さんが “通訳” してくれた (笑) けど、わたしの名古屋弁がヘタになったとも指摘され大ショック (笑)。これはいかん (ダメ) (笑) と気力を持ち直して、お母さんの生まれ育った土地と家を探しに初めて横須賀市を訪れた。ここでは標準語モードに切り替え。住所は知らなくても、母方のお爺ちゃんが建てた家が見つかった (笑)。見つけただけでなく、現在住んでらっしゃる方に会って立ち話をして (笑)、家にも上げてもらい (笑)、連絡先を交換し、お土産も戴いて帰ってきた (笑)。すっかり意気投合してしまい、不完全な?わたしの名古屋弁が止まらなかった。あのお方、わたしの喋ってる意味、せめてわたしが元家主の孫ってこと、分かってくれたかな (笑)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
長い間、標準語だと信じていた自分の言葉が、静岡県特有の方言だと知ったのは20代になってから。他県の友達ができるようになり、会話中に方言を指摘されたことがきっかけだった。「〜だっけか?(〜でしたか?)」「〜だもんで(〜だから)」「〜じゃん(〜だよ)」など。日本列島のほぼ中央に位置する静岡なので、自分はてっきり標準語を使っていると思っていたのに、実は、とてもクセのある方言を連発していたとは・・。「靴」や「服」のアクセントも標準語とは違う。標準語は「くつ」「ふく」と後ろにアクセントがあるが、静岡は前に付く。何十年にもわたり、これも標準だと思っていた。一方で、静岡方言だとよく言われる「〜だら」や「〜ずら」は、父方の祖母が口にしていた記憶はあるものの、私の両親の世代では父だけが使っていたような気がする。今はさすがに日本の方に対しては気をつけて標準語を使っているつもりだが、ほぼ毎日、母と LINE で話をしていると、方言がついつい出てしまう。「しょんないね(しょうがないね)」、「〜だけん(だけど)」、「〜するだよ(〜するんだよ)」など。つい最近、娘が「去年行ったのは、ディズニーランドだっけ? あれ? シーだっけか?」と言っていた。アメリカ育ちのはずの娘なのにベタベタの静岡弁・・。間違いなく私が原因だな。(SU) |
(2024年2月16日号に掲載)

 |
▽日本のサラリーマン時代。過労気味だった20代の私は会社を休んで、ブラリと房総半島南端の景勝地「平砂浦 (へいさうら)」を訪れた。心は和 (なご) んだが、無為な1日を過ごした罪悪感を拭い切れずに帰途につく。追い打ちをかけるように「お急ぎの方は、急行列車に乗り換えてください」とのアナウンス。条件反射的に移動しようとした刹那 (せつな)、相模湾の彼方に浮世絵のように美しく映える富士山を目撃する。忙 (せわ) しく動き回る乗客をよそに、私だけ普通列車の座席に戻り、見事な景観に見惚 (と) れていた。ここで覚醒。「1時間早く家に着いて何をする? 夕食を取り、朝起きて、いつものように出勤する。その繰り返しの果てには、死あるのみ」。「それだけだろ」と妙に合点が行って、バカバカしいほど清々 (すがすが) しい気持になった。▽「80対20の法則」(パレートの法則) も無駄を肯定している。稼働時間の実質20%で仕事の80%が終わっているとか。言い換えれば、実務時間の8割は効率が上がらない。集中力が最大効果を発揮するのは短時間で、残りの長時間は必然的に要領が悪くなる。無駄の極意ここにあり!意味のない無駄もなし!▽江戸中期の臨済宗僧侶、慧端禅師 (えたんぜんじ) も言ってるね。「一大事と申すは今日、唯今の心なり」。肝心なのは今、この瞬間。無駄と思える営為こそが将来への豊かな糧 (かて) となる。そう説いている・・ような気がするけど。 (SS) |
 |
|
 |
▽私の故郷、福島県会津柳津 (あいづやないづ) は日本でも有数の豪雪地だ。そこにあった生家は、黒光りする梁や柱を持つ頑丈な茅葺 (かやぶ) き屋根の家屋で、米農家として、ごく当たり前に、自給自足の生活をしていた。土間の釜戸、囲炉裏での食事、縁側での日向ぼっこ、屋根裏での蚕 (かいこ) の飼育。味噌、納豆、ぬか漬け、たくあん、干し柿、干し芋、番茶、わさび漬け、和菓子など、何でも自家製だった。保存食を保管するための部屋もあり、今でも、その独特の香りが記憶に残っている。冬は、脱穀した藁 (わら) で草鞋 (わらじ) や蓑 (みの)、正月飾りを作り、残りは田んぼや家畜の飼料に。幼い頃はイヤだったそんな生活も、都会暮らしに身を投じてみると、自然と共生する、実にムダのないものだと感じるようになった。▽子どもの頃は「ボーッとするな」と叱られたものだが、最近の脳科学によると、実は「ボーッとする」ことが脳には良いとされている。この時間は、脳が活発に働いてエネルギーを回復し、情報を整理し、ストレスを減らし、何と、過去の記憶をつなぎ合わせて新しいアイデアまで生み出してくれるらしい。スマホ、パソコン、TVから離れて「ボーッとする」ことで、脳は疲れにくくなり、集中力やパフォーマンスを向上させてくれるという。タイパやコスパを良しとする、今の忙しい時代に「何も考えずにボーッとしたい」という思いは、実は、創造性を高めるための脳からのメッセージなのかも——。(NS)
|
 |
アメリカではペーパータオルを大量に使う。日本に住んでいた頃、手を洗った後は、自分が持っているハンカチかミニタオルで拭いていた。アメリカに来た当時はハンドドライヤーも少なかったが、パブリック・バスルームには必ずペーパータオルが用意されていた。最初の頃は「便利だな」と感心していたが、ゴミ箱に山盛りになった使用済みのペーパータオル (勿体ない!) を見るにつけ、複雑な気持ちになった。勿論、自宅でもペーパータオルは常備している。が、私には贅沢に思えてちびちび使う or 何かを拭いてもまだ汚れていなければ、キッチンカウンターの隅に置いてまだまだ使う。反対に夫はどんどん使ってすぐに捨てる! 1枚で足りるところを何枚も使ったり、手拭きのタオルがあるにもかかわらず、わざわざペーパータオルを使って平気でいる。“勿体ない” という言葉は彼の辞書にはなさそうだ。あっという間に1ロールがなくなる。「我が家にそんな余裕はないのに、どうして!?」と夫が理解できなかった。だが、夏休みにお義母さんの家に行って理解した。そこでは家族全員が際限なくペーパータオルを消費して、無くなるとガレージに大量にストックされている予備をどんどん出してくる。あぁ・・文化が違うんだなと思った。 (YA)
|
 |
過去に何度か書いたと思うが、私は無駄というものが大嫌いな人。私が家庭教師として7〜8年通っている裕福な家庭は、生活のほとんどが私と真逆で、節約という精神は微塵 (みじん) もなく、家中が無駄だらけという生活。シーツを1週間に2回換え、タオル類は毎回。結果、家族4人の洗濯物は、掃除婦さんが週3回来て、朝から晩まで洗濯機を回しているという始末。電気・水道・洗剤料金の「大無駄大会」だ。それだけでなく、暑くない日もクーラーを朝からつけっぱなし、ほんの少しだけ口をつけた食べ物もすぐにゴミ箱へ。私から見たら「やめてくれ~」。そんな無駄だらけの生活。その彼女、日本語を全く解しないのに「もったいない」という言葉だけは知っている。笑える。この女性がアメリカの代表かどうか知らねども、私がこの国に来て「アメリカ経済は、アメリカ人の無駄で成り立っている」と感じている。例えば、そんな無駄大好き彼らの性格を利用して機能しているクレジットカード。余裕もないのに、どんどんカードでモノを買い、毎月返済する最低金額を払い、後は高利貸し同然の利子を払い続け、時には延滞料のおまけまで払っている。私から見たら、こんな無駄はない。「翌月払えるからカードを使い、その利便性に浴する」のと、「所持金がないからカードに頼り、高額利子を払う」。この差に気が付かないのかなぁ〜アメリカ人は。 (Belle)
|
 |
|
 |
お正月は愛知県春日井市の実家に帰った。2024年の “新年企画” で浮上したのは「お母さんの家系探訪/母方のルーツを辿る」というテーマ。先ずは母系出自 (しゅつじ) を調べて、一族のルーツを探ることに。お母さんの兄弟4名+ウチら兄弟4名の計8名で、岐阜県の大垣城に行ってきた。出発前夜に「なぜ大垣城?」とお母さんに尋ねてみた。よく分からない説明を簡単に言っちゃうと 笑、お母さんの曽祖父 (ひいおじいちゃん) が大垣城で生まれた・・と 笑。え? それって・・わたしは姫?! 笑。早速、帰省していた友人のH部長に話す。大垣城も資料館もお正月休み。「外から見る限りでは、家紋が同じ」とか「城主様の肖像画が自分にそっくり」 という 笑 オジちゃんの話とかで盛り上がる 笑。「憶測より、ネットで分かるわ」 と思って調べたけど、男子の名前からして直系ではない 笑。翌日、釈然としないまま、大垣城資料館の館長に電話。私「あの〜、母親の旧姓が戸田というのですが、歴代の城主様に “梅ノ条” のような名の人がいるそうで、家系図に載ってます?」。館長「おらんよ 笑。戸田采女正 氏共 (とだうねめのかみ うじたか) の “うねめのかみ” のことでは?」。私「それだわ」笑。館長「NHKの徳川家康ドラマで、問い合わせ増えたんだわ」笑。・・ウチは家臣だったかもね~。このリサーチは無駄じゃない。だって地元や家族にとって、わたしはすでに「お姫さま!」 笑。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
「無駄」って何だろう。ポジティブな印象はあまりなかった。辞書にも「役に立たない (余計な) こと。効果・効用がないこと。無益」とある。時間、お金、行動・・。多くの人が効率良く何かをするために無駄を省き、時間や金銭を余計に消費しないようにしているはず。私も日常の中で「この時間って、結構、もったいないな〜。だったら他のことやりたい」などと思うことがよくある。だが、無益と思えた行動が “思うほど無駄ではない” ことも事実。最近、こんなことがあった。若い歌手グループのファンである娘が、そのユニットの YouTube を私と一緒に見たいという。ウィークエンドの夜に母親の私と見るのが楽しいらしい。私はそんな若者のグループなんて興味なかった。メンバー全員が同じ顔にしか見えないし、誰が誰だか分からないので、正直、気が進まなかった。しかし、娘から1週間のトレーニングを受けて、グループ全員の顔と名前を覚えた。全く関心のなかった若手歌手の面々なのに、今では娘と楽しんで見られるようになった。ほぼ強制的にさせられていたトレーニング中は「どうして、私、こんなことしているの?」と、本当に無駄だと思っていたが、今では娘に感謝している。だって、夜のひとときに、娘と一緒にソファーに並んでゆっくりTVを観られるのも、あと数年かもしれないしね。短い人生、そんなに無駄なことなんてないのかも。(SU) |
(2024年2月1日号に掲載)