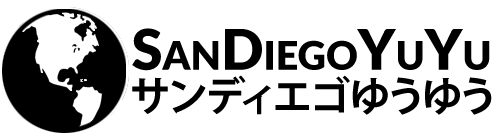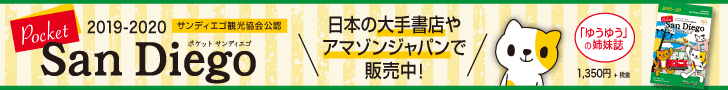Featured
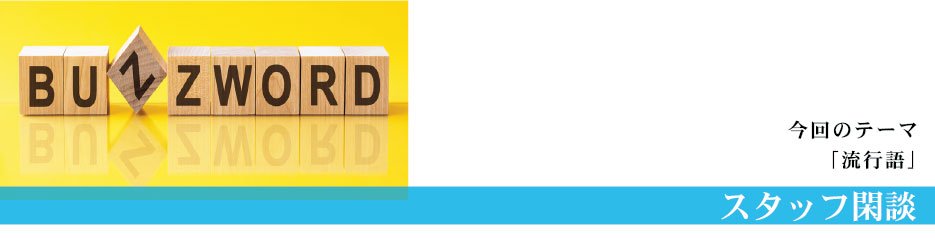
(2024年12月1日号に掲載)
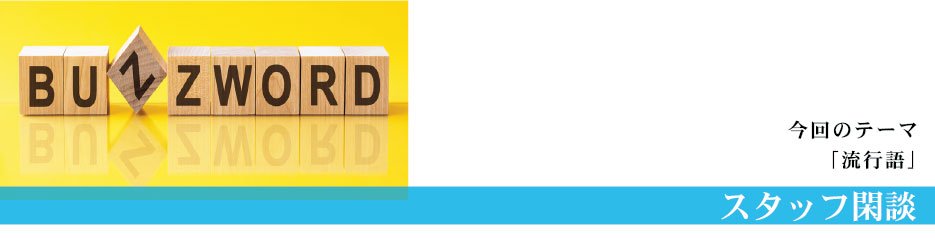
 |
小学校低学年の頃、日本発祥の「行軍将棋」 (別名:軍人将棋) が男児の間で流行していた。流行といっても、オリジナル版は日清・日露戦争に勝利した明治後半に考案され、改定後の昭和初期~戦時中に隆盛をみたボードゲーム。その名残りが昭和40年代前半まで続いた。60代以上の男性ならご存知と思うが、元帥 (王将) を筆頭に大将から少将までの将校駒のほか、大尉、砲兵、工兵、戦車、地雷、スパイなどの駒で対戦する盤上遊戯。敵の元帥を先取するか、総司令部を占領してしまうか、または相手を全滅させた側が勝者となる。駒の正体を伏せて裏返しに配置し、審判役を付けて3人で遊ぶというのがルール。戦後20年も経過していた時代に、そんなゲームが子供の娯楽として玩具店で売られていた事実を考えると、何とも奇異な感じがする。なぜなら「原爆」 という駒も含まれていて、極めて不謹慎な遊びだったのだ。行軍将棋には、サイコロを振ったり、手元に巡ってくるカードによって優劣が左右される “運の要素” が一切なく、駒を伏せてパワーを公開しないという意味では、突発的なスリルとサスペンスに満ちた模擬戦争ゲームと言えた。いつしか、仲間の容貌、性格、風格、印象に最も近い駒の名を選んで呼び合うように−−。なぜか元帥よりスパイと呼ばれると鼻高々だった。その当時の人気No.1流行語。(SS) |
 |
|
 |
▽2024年に世界で最も話題となった言葉は「AI Revolution」らしい。人工知能の急速な進化により、さまざまな産業でAIの導入が進み、まさに革命的な変化が起きている。私自身も、仕事の質が大きく変わり、自分の職が脅かされるのではないかと感じている。また、オフィスや自宅に限定されず、自分の好きな場所で働ける「ワークフロムエニウェア(WFA)」や、地球環境への配慮を重視した「サステナブルファッション=Sustainable Fashion」も注目を集めている。確かに、デジタルノマドビザ (リモートワーク滞在許可査証=Digital Nomad Visas) を取得し、世界を旅しながら仕事をしている知人、古着やレンタルを活用している友人も増えた。▽日本では「2024ユーキャン新語・流行語大賞」のノミネート30語が発表された。個人的には、大谷くんが50本塁打/50盗塁を達成した「50-50」を推したい。でも、知らない流行語も多く、少し凹んだ。例えば、Z世代が「仲間」という意味で使う「界隈」、TikTokで流行した「飛び跳ねる猫」の「猫ミーム」、加工なしの写真共有アプリ「BeReal」、昭和世代が共感するタイムスリップドラマ「侍タイムスリッパー」、社会の生きづらさを歌った楽曲「はいよろこんで」などなど。今年はどんな言葉が大賞に輝くだろう。楽しみだ。(NS)
|
 |
日本で生活していた頃も流行語には疎かった。アメリカでも流行語やスラングを使いこなすほど英語が上達していないので、やっぱり疎い。ただ、プリティーンの子どもたちは、学校やYouTubeなどでいろいろ覚えてくる。10歳の娘がよく口にするのは「Slay! (スレイ)という「カッコイイ」「素敵」を意味する言葉や、Bestie (ベスティー)という 「親友」を指す表現。Baddie (バディー)という 「魅力的な人」、そしてDelulu (デルル) という「現実離れしている」もある。最初は「?」と戸惑ったが、今ではすっかり慣れてしまった。他にも、Sigma (シグマ) : You're so sigma! 格好いい)、 Skibidi (スキビディ) : クールで面白い、 Rizzler (リズラー) : 自信たっぷりの人、GOAT (ゴート) : 最高、Cap (キャップ) :嘘、 Bet (ベット) : イエス、Crusty (クラスティ) : 散らかった、 Bussin (バシン) :素晴らしい−−などなど。私が子どもの頃、流行語は主にテレビ番組やCMから生まれていた。ところが、今はインターネットがその発信源となり、小学生でさえ、ファッションから所持品まで最新トレンドに詳しいのだから驚くばかりだ。そのうち、娘に
「ママは流行に鈍感ね〜」と言われてしまう日が来るのかもしれない。(YA) |
 |
今年の漢字、サラリーマン川柳、創作の四字熟語、現代学生百人一首などと並んで、現代の世相を反映する一つの指標として取り上げられている流行語大賞は1984年に創始された、とある。1984年といえば、私が当地に移住する10年前のことだ。ということは、この流行語大賞が設定されて10年は日本に住んでいた訳で、毎年12月発表の流行語大賞に選ばれた言葉は少なからず耳にしていたはず。と思うのに、調べてみても、記憶に残っている言葉に馴染みがない。せいぜいが新人類 (86年)、オバタリアン (89年)、ちびまる子ちゃん (90年)、百歳の双子姉妹 きんさん、ぎんさん (92年) くらいだろうか。以降はサンディエゴ住まいとなった身。現在でこそYouTubeで日本の番組は視聴可能だが、当時は日本の情報を瞬時に得るなどほぼ不可能。その頃に比べると、随分と便利な世の中になったものだ。私は家にいる時は、日本の情報源である動画ニュースを見ながら昼食を取るのが通例。そんな状況下で、渡米以来30年の中で最も印象に残っている流行語大賞に選ばれた言葉といえば、中国人が挙って日本へ買い物に訪れていた現象を語った「爆買い」(15年)。中国人の恐ろしきパワーを見せつけられた社会現象だった。裏を返せば、日本経済発展に貢献?した中国人の皆様、ありがとうございました!。(Belle)
|
 |
|
 |
最近、ニッポンがアメリカで流行っていることを知って驚いた。友達の楽団サイン会で“Shikishi”を持参するよう表示があった! もしかしてコミコンで作家が使ってたから、当地でも広まったのだろうか? (これは私の勝手な想像だけどね!) North Parkのホテルのロビーで、突然、私でも歌詞が分かる曲がBGMとして流れ始めた。なんと1980年代の日本のシティポップ! 耳を疑いながらも、歌詞がすべて理解できてしまい「ウソでしょ?」と心の中で叫んだ。ニッポン大好き!というアメリカ人の知り合いは、驚くなかれ、アメリカ人同士のテキストメッセージをわざわざ日本語で打っているらしい! それを聞いて笑ってしまった。逆に、最近の日本のドラマを観ていると、やたらとカタカナ英語が多くてビックリ。「サステナブル」「インセンティブ」「エビデンス」−−−私の両親や兄弟には全く理解できない単語が飛び交っている。こんな調子だと、そのうち外国人の方がきれいな日本語を話し出すんじゃないか!? アメリカ人の友達とLa Mesaにある珈琲屋さんに行った時のこと。メニュー 「Grilled Cheese Sando」と書かれているのを見て、「Sando?」と尋ねたら「そうよ、日本の“サンド”のこと。今、流行ってるよ」と来たもんだ! これまた驚いた。そこのニッポン人のあなた! お互いにアメリカ人に負けないキレイな日本語を話していこーねー! 笑。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
『新語・流行語大賞』 は、その年に活躍した人の名言や、ニュースで話題になった言葉が選ばれているが「本当に流行っていたのかな?」と疑問に思うことがある。自分の記憶を頼りに1990年代の流行語を調べてみた。コギャルの間で流行した言葉「チョベリバ」や「チョべリグ」などはよく覚えている。「超ベリーバッド(very bad)」や「超ベリーグッド(very good)」を略したものだ。私は少しコギャル世代から外れていたため、知っていても使う機会はなかった。「アウト・オブ・眼中」なんていうのもあった。「眼中にない」「問題外」「論外」といった意味が含まれ、興味のない異性に対して使うことが多かったらしい。「ウーロン茶」という言葉も見つけたが、これには驚いた。女性が男性に言い放つ言葉で、「ウザイ(ウー)、ロン毛の(ロン)、茶髪男子(茶)」を指しているらしい。「ナウい」も懐かしいが、これは1979年頃の流行語らしい。4歳だった私が、どういうつもりで使っていたのかは謎のまま。今では死語になっているが、現代風に言い換えると「イケてるね~」「おしゃれだね~」になるという。私はまだうっかり使ってしまいそうだ。時代が変わっても、流行語には独特の面白さがあるものだ。(SU) |
(2024年12月1日号に掲載)
Featured
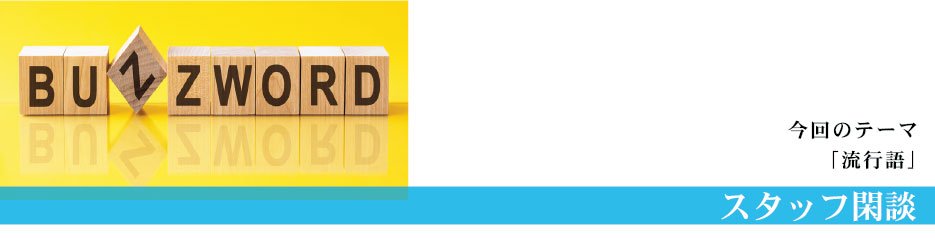
(2024年12月1日号に掲載)
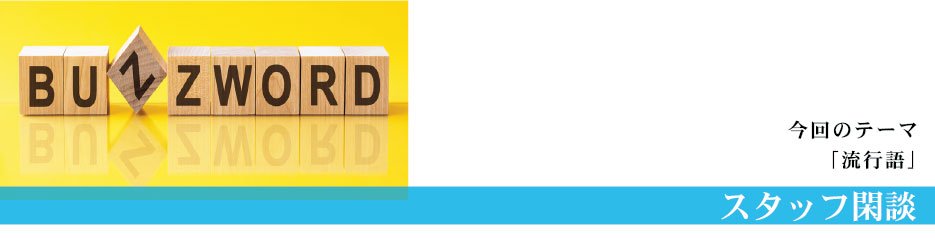
 |
小学校低学年の頃、日本発祥の「行軍将棋」 (別名:軍人将棋) が男児の間で流行していた。流行といっても、オリジナル版は日清・日露戦争に勝利した明治後半に考案され、改定後の昭和初期~戦時中に隆盛をみたボードゲーム。その名残りが昭和40年代前半まで続いた。60代以上の男性ならご存知と思うが、元帥 (王将) を筆頭に大将から少将までの将校駒のほか、大尉、砲兵、工兵、戦車、地雷、スパイなどの駒で対戦する盤上遊戯。敵の元帥を先取するか、総司令部を占領してしまうか、または相手を全滅させた側が勝者となる。駒の正体を伏せて裏返しに配置し、審判役を付けて3人で遊ぶというのがルール。戦後20年も経過していた時代に、そんなゲームが子供の娯楽として玩具店で売られていた事実を考えると、何とも奇異な感じがする。なぜなら「原爆」 という駒も含まれていて、極めて不謹慎な遊びだったのだ。行軍将棋には、サイコロを振ったり、手元に巡ってくるカードによって優劣が左右される “運の要素” が一切なく、駒を伏せてパワーを公開しないという意味では、突発的なスリルとサスペンスに満ちた模擬戦争ゲームと言えた。いつしか、仲間の容貌、性格、風格、印象に最も近い駒の名を選んで呼び合うように−−。なぜか元帥よりスパイと呼ばれると鼻高々だった。その当時の人気No.1流行語。(SS) |
 |
|
 |
▽2024年に世界で最も話題となった言葉は「AI Revolution」らしい。人工知能の急速な進化により、さまざまな産業でAIの導入が進み、まさに革命的な変化が起きている。私自身も、仕事の質が大きく変わり、自分の職が脅かされるのではないかと感じている。また、オフィスや自宅に限定されず、自分の好きな場所で働ける「ワークフロムエニウェア(WFA)」や、地球環境への配慮を重視した「サステナブルファッション=Sustainable Fashion」も注目を集めている。確かに、デジタルノマドビザ (リモートワーク滞在許可査証=Digital Nomad Visas) を取得し、世界を旅しながら仕事をしている知人、古着やレンタルを活用している友人も増えた。▽日本では「2024ユーキャン新語・流行語大賞」のノミネート30語が発表された。個人的には、大谷くんが50本塁打/50盗塁を達成した「50-50」を推したい。でも、知らない流行語も多く、少し凹んだ。例えば、Z世代が「仲間」という意味で使う「界隈」、TikTokで流行した「飛び跳ねる猫」の「猫ミーム」、加工なしの写真共有アプリ「BeReal」、昭和世代が共感するタイムスリップドラマ「侍タイムスリッパー」、社会の生きづらさを歌った楽曲「はいよろこんで」などなど。今年はどんな言葉が大賞に輝くだろう。楽しみだ。(NS)
|
 |
日本で生活していた頃も流行語には疎かった。アメリカでも流行語やスラングを使いこなすほど英語が上達していないので、やっぱり疎い。ただ、プリティーンの子どもたちは、学校やYouTubeなどでいろいろ覚えてくる。10歳の娘がよく口にするのは「Slay! (スレイ)という「カッコイイ」「素敵」を意味する言葉や、Bestie (ベスティー)という 「親友」を指す表現。Baddie (バディー)という 「魅力的な人」、そしてDelulu (デルル) という「現実離れしている」もある。最初は「?」と戸惑ったが、今ではすっかり慣れてしまった。他にも、Sigma (シグマ) : You're so sigma! 格好いい)、 Skibidi (スキビディ) : クールで面白い、 Rizzler (リズラー) : 自信たっぷりの人、GOAT (ゴート) : 最高、Cap (キャップ) :嘘、 Bet (ベット) : イエス、Crusty (クラスティ) : 散らかった、 Bussin (バシン) :素晴らしい−−などなど。私が子どもの頃、流行語は主にテレビ番組やCMから生まれていた。ところが、今はインターネットがその発信源となり、小学生でさえ、ファッションから所持品まで最新トレンドに詳しいのだから驚くばかりだ。そのうち、娘に
「ママは流行に鈍感ね〜」と言われてしまう日が来るのかもしれない。(YA) |
 |
今年の漢字、サラリーマン川柳、創作の四字熟語、現代学生百人一首などと並んで、現代の世相を反映する一つの指標として取り上げられている流行語大賞は1984年に創始された、とある。1984年といえば、私が当地に移住する10年前のことだ。ということは、この流行語大賞が設定されて10年は日本に住んでいた訳で、毎年12月発表の流行語大賞に選ばれた言葉は少なからず耳にしていたはず。と思うのに、調べてみても、記憶に残っている言葉に馴染みがない。せいぜいが新人類 (86年)、オバタリアン (89年)、ちびまる子ちゃん (90年)、百歳の双子姉妹 きんさん、ぎんさん (92年) くらいだろうか。以降はサンディエゴ住まいとなった身。現在でこそYouTubeで日本の番組は視聴可能だが、当時は日本の情報を瞬時に得るなどほぼ不可能。その頃に比べると、随分と便利な世の中になったものだ。私は家にいる時は、日本の情報源である動画ニュースを見ながら昼食を取るのが通例。そんな状況下で、渡米以来30年の中で最も印象に残っている流行語大賞に選ばれた言葉といえば、中国人が挙って日本へ買い物に訪れていた現象を語った「爆買い」(15年)。中国人の恐ろしきパワーを見せつけられた社会現象だった。裏を返せば、日本経済発展に貢献?した中国人の皆様、ありがとうございました!。(Belle)
|
 |
|
 |
最近、ニッポンがアメリカで流行っていることを知って驚いた。友達の楽団サイン会で“Shikishi”を持参するよう表示があった! もしかしてコミコンで作家が使ってたから、当地でも広まったのだろうか? (これは私の勝手な想像だけどね!) North Parkのホテルのロビーで、突然、私でも歌詞が分かる曲がBGMとして流れ始めた。なんと1980年代の日本のシティポップ! 耳を疑いながらも、歌詞がすべて理解できてしまい「ウソでしょ?」と心の中で叫んだ。ニッポン大好き!というアメリカ人の知り合いは、驚くなかれ、アメリカ人同士のテキストメッセージをわざわざ日本語で打っているらしい! それを聞いて笑ってしまった。逆に、最近の日本のドラマを観ていると、やたらとカタカナ英語が多くてビックリ。「サステナブル」「インセンティブ」「エビデンス」−−−私の両親や兄弟には全く理解できない単語が飛び交っている。こんな調子だと、そのうち外国人の方がきれいな日本語を話し出すんじゃないか!? アメリカ人の友達とLa Mesaにある珈琲屋さんに行った時のこと。メニュー 「Grilled Cheese Sando」と書かれているのを見て、「Sando?」と尋ねたら「そうよ、日本の“サンド”のこと。今、流行ってるよ」と来たもんだ! これまた驚いた。そこのニッポン人のあなた! お互いにアメリカ人に負けないキレイな日本語を話していこーねー! 笑。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
『新語・流行語大賞』 は、その年に活躍した人の名言や、ニュースで話題になった言葉が選ばれているが「本当に流行っていたのかな?」と疑問に思うことがある。自分の記憶を頼りに1990年代の流行語を調べてみた。コギャルの間で流行した言葉「チョベリバ」や「チョべリグ」などはよく覚えている。「超ベリーバッド(very bad)」や「超ベリーグッド(very good)」を略したものだ。私は少しコギャル世代から外れていたため、知っていても使う機会はなかった。「アウト・オブ・眼中」なんていうのもあった。「眼中にない」「問題外」「論外」といった意味が含まれ、興味のない異性に対して使うことが多かったらしい。「ウーロン茶」という言葉も見つけたが、これには驚いた。女性が男性に言い放つ言葉で、「ウザイ(ウー)、ロン毛の(ロン)、茶髪男子(茶)」を指しているらしい。「ナウい」も懐かしいが、これは1979年頃の流行語らしい。4歳だった私が、どういうつもりで使っていたのかは謎のまま。今では死語になっているが、現代風に言い換えると「イケてるね~」「おしゃれだね~」になるという。私はまだうっかり使ってしまいそうだ。時代が変わっても、流行語には独特の面白さがあるものだ。(SU) |
(2024年12月1日号に掲載)
Featured

(2024年11月16日号に掲載)

 |
「締切」という重い枷 (カセ) を負わされた出版業務を38年続けた。時間に「追われる」日常が加速して、たちまち時間に「追い抜かれ」、いつしか時間を「追いかける」 ようになった。平日と休日の境界線がなくなり、本能的に時間の効率化を図る因果な日々。始終、何かにムチ打たれ、何かに駆られている焦燥感がある。▽生来、短気でせっかちなので、とびきり評判の良い料理店で食事をしようとしても、お客さんの長い列を目撃すると意欲がなくなり、近くの空いている店に飛び込んでしまう。コンビニのキャッシャーに美人の店員さんがいると、男はそのラインを目掛けて並ぶらしいが、私は美人だろうが不美人だろうが、男だろうが女だろうが、若かろうが老けていようが、地球人だろうが火星人だろうが、ガラ空きのキャッシャーに直行する。時短最優先。▽還暦を過ぎて早起きになった。1日の始まりは、明け方に前庭に出て、仁王立ちで朝刊を待つこと。配達時刻が10分以上遅れて、待ちぼうけを食わされると不愉快になるが、腕組みをしながら、朝靄 (あさもや) の薄明かりの中でひたすら待ち続ける。「弁慶か? 薄気味悪い」と妻。▽一度決めたことは変えたくない性分。その傾向に拍車が掛かり、加齢とともに「頑固ジジイ」路線をまっしぐらに突き進みそうなので、改善しなければならない。時間がかかりそうだ。(SS) |
 |
|
 |
▽年を重ねるごとに1年が短く感じるのは、多くの人が経験することだ。小学生のころは一年が終わりのないほど長く感じたのに、今ではあっという間に年末が近づいていると感じる。子供のころは毎日が新しい発見や楽しい出来事でいっぱいで、そのたびに「新しい!」と感じ、脳がたくさん働くため、時間がゆっくり流れているように思えるのだそうだ。▽友人や親戚の子供たちがどんどん成長していく姿を見ると、彼らが未来に向かって「足し算」のように時間を生きているのに対し、大人は過去が増えていく「引き算」の時間を生きていると強く感じる。もし私に子どもがいれば、子育てを通して、もう一度この「足し算」の時間を体感できたかもしれない。▽猫を動物病院に連れて行ったとき、「ペットと人の年齢早見表」を見て、猫が一年で人間の二十歳に相当する成長を遂げ、その後は一年ごとに人間でいうプラス四歳ずつ加算されることを知った。人や動物によって時間の流れ方や感じ方は異なるが、みんなそれぞれの時間を感じながら、同じ場所で一緒に生きていることで、つながっているように思う。▽毎日にちょっとずつ新しいことを取り入れると、1日1日が特別に感じられ、時間がゆっくり流れているように感じられるそうだ。通る道を変えたり、新しい料理に挑戦したり、旅行に行ったり、テニスやゴルフも再開してみたいと思う。(NS)
|
 |
家族で過ごす時間、友人と過ごす時間、自分ひとりで過ごす時間、どれも私にとって大切な時間だ。先日、夕食後に美味しいスナックを求めて、夫と娘と私の3人で車に乗って少し離れたマーケットへ夜の買い物に出かけた。道中、娘が学校での出来事や友達とのあれこれを話してくれるの聞いたり、日々のたわいのないことを喋り合いながら過ごす時間が心地よかった。高校3年生の娘は、最近友達と過ごす時間が多くなってきた。自分で車を運転するようになったら、家族揃ってこんなふうに一緒に行動する時間がもっと減るのだろうなと思ったら、なんだか寂しくなった。お互い虫の居所が悪くて、険悪な雰囲気になると、こういう感傷的な気持ちはどこかに吹き飛んでしまうのだけれど(笑)▽若い頃の私はよく一人で買い物に行ったり、映画を観に行ったり、ご飯を食べに行ったりしていたなと思う。友達と一緒に出かけるのももちろん楽しかったけれど、自由気ままに自分の好きなことを自分のペースでする時間が定期的に必要だったのだと思う。夫も好きなことは一人でやるものが多い。チームスポーツが苦手なのも私に似ている。一緒に過ごす時間はもちろん、ひとり時間をちゃんと楽しめるって大切だなと思う。(RN)
|
 |
世の中には時間が守れない人、人種がいるようだ。約束に10分、20分遅れてきても悪びれる様子もなく、謝りもしない。かつて友達だと思っていた人も、必ず遅れる人だった。あまりに約束の時間にいい加減な態度に呆れ果て、「〇〇さん、普段から5分くらい前に着くように家を出ない?」と、やんわりと言ったところ、「出られるワケがないでしょ!」と逆切れされたことがあった。珍しい日本人だ。時間はそこにあるものではなく“作る”もの。作ろうとしなければ、ただ悪戯に過ぎていくだけ。日本人は一般的に時間を守る国民だ。列車の発着時間でも、わずか2、3分の遅延にアナウンスが流れる。こんな国は世界中探してもそうはない、と思う。一方、ラテン系の民族は特に時間にルーズな人が多い。パーティーに平気で遅れてくるのは序の口。自分のウェディングに1時間も遅刻したメキシコ人カップルもいた。かつてのイタリア大使が書いた本に、イタリアのある都市の道路沿いに4つの時計が掲げられていたが、そのどれもが示す時刻が異なっていた、と。そんな時間の差など全く気にならない国民性なのだ。しかし、こんなに時間にいい加減な国でも、公共交通機関の出発時間は「お見事!」と、声を大にして称賛したいほど定刻に出発する。お国が違えば、我々には普通のことをしただけで誉められる。日本の常識は世界の非常識 !? (Belle)
|
 |
|
 |
楽しい時間はあっという間に過ぎるもの。例えば、先週の日本への帰省もそうだ。二週間があっという間に過ぎて、まるで三日間のように感じられた(これって年取ったってこと?笑)。実家に帰る前にあちこち観光して回り、奥州平泉を初めて訪れたときには、まるで時が平安時代に戻ったかのようだった。金色堂は今年建立900年。きゅーひゃくねん?どんだけ時間経ってんの?しかし岩手県民は口数が少ないからか(笑)もっとこの世界遺産のことをエバれば良いのに、京都にもひけをとらないこの街のことを多くのニッポン人が知らないと思う。名古屋の実家に帰って知ったことだが、父も同じ時期に中尊寺にいたらしいのだ(偶然すぎて笑ってしまった)。米国に帰ってすぐロサンゼルスで開催されたアニメOver the Garden Wallの10周年記念コンサートに行った。友人がサイン会を開いているのを見てびっくり。10年前には想像もできなかった光景だ。舞台には有名俳優も登場し、あいさつをしたが、家に帰って検索して初めて、あの小柄な人物が『ロード・オブ・ザ・リング』のフロドだったことに気づいた。時間は誰にも止められない、スターでさえもね(自分も!笑) (りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
朝の時間は1時間があっという間に過ぎる。家族で一番早く起きるのは自分。自分の身支度をしてから子供たちのランチを作りと朝食の用意をする。時間を見ながら子供たちが起きたかどうか確認するため電話をかるが、電話に出ない時は2階に行って無理やり起こす。また1階のキッチンへ戻り朝食の支度を続ける。その後、キッチンに戻り朝食を仕上げ、子供たちが食べ終えたら学校に送り届ける。30分ほどすると、夫が起きてきて仕事の準備をして出かけるので、コーヒーを作って送り出す。30分ほどすると夫が起きてきて、仕事の準備をするので、コーヒーを入れて見送る。ここでようやくひと息。自分のためにコーヒーを入れ、適当に朝食を済ませ、ニュースをチェックする。その後は仕事と家事に取りかかり、気づけば子供の迎えの時間だ。毎日がこんな調子で、案外無駄にしている時間もあると感じる。子供の迎えから夕食の準備までの間は、体力が切れるため1時間ほど昼寝をするようになった。最近はジムにも行けず、会費がもったいないと思いつつ、どうしても行く元気がない。朝の時間もあっという間だが、1年もあっという間なのだ。年を取るのも早い!もっと時間を大切に使わねば。(S.U) |
(2024年11月16日号に掲載)
Featured

(2024年11月16日号に掲載)

 |
「締切」という重い枷 (カセ) を負わされた出版業務を38年続けた。時間に「追われる」日常が加速して、たちまち時間に「追い抜かれ」、いつしか時間を「追いかける」 ようになった。平日と休日の境界線がなくなり、本能的に時間の効率化を図る因果な日々。始終、何かにムチ打たれ、何かに駆られている焦燥感がある。▽生来、短気でせっかちなので、とびきり評判の良い料理店で食事をしようとしても、お客さんの長い列を目撃すると意欲がなくなり、近くの空いている店に飛び込んでしまう。コンビニのキャッシャーに美人の店員さんがいると、男はそのラインを目掛けて並ぶらしいが、私は美人だろうが不美人だろうが、男だろうが女だろうが、若かろうが老けていようが、地球人だろうが火星人だろうが、ガラ空きのキャッシャーに直行する。時短最優先。▽還暦を過ぎて早起きになった。1日の始まりは、明け方に前庭に出て、仁王立ちで朝刊を待つこと。配達時刻が10分以上遅れて、待ちぼうけを食わされると不愉快になるが、腕組みをしながら、朝靄 (あさもや) の薄明かりの中でひたすら待ち続ける。「弁慶か? 薄気味悪い」と妻。▽一度決めたことは変えたくない性分。その傾向に拍車が掛かり、加齢とともに「頑固ジジイ」路線をまっしぐらに突き進みそうなので、改善しなければならない。時間がかかりそうだ。(SS) |
 |
|
 |
▽年を重ねるごとに1年が短く感じるのは、多くの人が経験することだ。小学生のころは一年が終わりのないほど長く感じたのに、今ではあっという間に年末が近づいていると感じる。子供のころは毎日が新しい発見や楽しい出来事でいっぱいで、そのたびに「新しい!」と感じ、脳がたくさん働くため、時間がゆっくり流れているように思えるのだそうだ。▽友人や親戚の子供たちがどんどん成長していく姿を見ると、彼らが未来に向かって「足し算」のように時間を生きているのに対し、大人は過去が増えていく「引き算」の時間を生きていると強く感じる。もし私に子どもがいれば、子育てを通して、もう一度この「足し算」の時間を体感できたかもしれない。▽猫を動物病院に連れて行ったとき、「ペットと人の年齢早見表」を見て、猫が一年で人間の二十歳に相当する成長を遂げ、その後は一年ごとに人間でいうプラス四歳ずつ加算されることを知った。人や動物によって時間の流れ方や感じ方は異なるが、みんなそれぞれの時間を感じながら、同じ場所で一緒に生きていることで、つながっているように思う。▽毎日にちょっとずつ新しいことを取り入れると、1日1日が特別に感じられ、時間がゆっくり流れているように感じられるそうだ。通る道を変えたり、新しい料理に挑戦したり、旅行に行ったり、テニスやゴルフも再開してみたいと思う。(NS)
|
 |
家族で過ごす時間、友人と過ごす時間、自分ひとりで過ごす時間、どれも私にとって大切な時間だ。先日、夕食後に美味しいスナックを求めて、夫と娘と私の3人で車に乗って少し離れたマーケットへ夜の買い物に出かけた。道中、娘が学校での出来事や友達とのあれこれを話してくれるの聞いたり、日々のたわいのないことを喋り合いながら過ごす時間が心地よかった。高校3年生の娘は、最近友達と過ごす時間が多くなってきた。自分で車を運転するようになったら、家族揃ってこんなふうに一緒に行動する時間がもっと減るのだろうなと思ったら、なんだか寂しくなった。お互い虫の居所が悪くて、険悪な雰囲気になると、こういう感傷的な気持ちはどこかに吹き飛んでしまうのだけれど(笑)▽若い頃の私はよく一人で買い物に行ったり、映画を観に行ったり、ご飯を食べに行ったりしていたなと思う。友達と一緒に出かけるのももちろん楽しかったけれど、自由気ままに自分の好きなことを自分のペースでする時間が定期的に必要だったのだと思う。夫も好きなことは一人でやるものが多い。チームスポーツが苦手なのも私に似ている。一緒に過ごす時間はもちろん、ひとり時間をちゃんと楽しめるって大切だなと思う。(RN)
|
 |
世の中には時間が守れない人、人種がいるようだ。約束に10分、20分遅れてきても悪びれる様子もなく、謝りもしない。かつて友達だと思っていた人も、必ず遅れる人だった。あまりに約束の時間にいい加減な態度に呆れ果て、「〇〇さん、普段から5分くらい前に着くように家を出ない?」と、やんわりと言ったところ、「出られるワケがないでしょ!」と逆切れされたことがあった。珍しい日本人だ。時間はそこにあるものではなく“作る”もの。作ろうとしなければ、ただ悪戯に過ぎていくだけ。日本人は一般的に時間を守る国民だ。列車の発着時間でも、わずか2、3分の遅延にアナウンスが流れる。こんな国は世界中探してもそうはない、と思う。一方、ラテン系の民族は特に時間にルーズな人が多い。パーティーに平気で遅れてくるのは序の口。自分のウェディングに1時間も遅刻したメキシコ人カップルもいた。かつてのイタリア大使が書いた本に、イタリアのある都市の道路沿いに4つの時計が掲げられていたが、そのどれもが示す時刻が異なっていた、と。そんな時間の差など全く気にならない国民性なのだ。しかし、こんなに時間にいい加減な国でも、公共交通機関の出発時間は「お見事!」と、声を大にして称賛したいほど定刻に出発する。お国が違えば、我々には普通のことをしただけで誉められる。日本の常識は世界の非常識 !? (Belle)
|
 |
|
 |
楽しい時間はあっという間に過ぎるもの。例えば、先週の日本への帰省もそうだ。二週間があっという間に過ぎて、まるで三日間のように感じられた(これって年取ったってこと?笑)。実家に帰る前にあちこち観光して回り、奥州平泉を初めて訪れたときには、まるで時が平安時代に戻ったかのようだった。金色堂は今年建立900年。きゅーひゃくねん?どんだけ時間経ってんの?しかし岩手県民は口数が少ないからか(笑)もっとこの世界遺産のことをエバれば良いのに、京都にもひけをとらないこの街のことを多くのニッポン人が知らないと思う。名古屋の実家に帰って知ったことだが、父も同じ時期に中尊寺にいたらしいのだ(偶然すぎて笑ってしまった)。米国に帰ってすぐロサンゼルスで開催されたアニメOver the Garden Wallの10周年記念コンサートに行った。友人がサイン会を開いているのを見てびっくり。10年前には想像もできなかった光景だ。舞台には有名俳優も登場し、あいさつをしたが、家に帰って検索して初めて、あの小柄な人物が『ロード・オブ・ザ・リング』のフロドだったことに気づいた。時間は誰にも止められない、スターでさえもね(自分も!笑) (りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
朝の時間は1時間があっという間に過ぎる。家族で一番早く起きるのは自分。自分の身支度をしてから子供たちのランチを作りと朝食の用意をする。時間を見ながら子供たちが起きたかどうか確認するため電話をかるが、電話に出ない時は2階に行って無理やり起こす。また1階のキッチンへ戻り朝食の支度を続ける。その後、キッチンに戻り朝食を仕上げ、子供たちが食べ終えたら学校に送り届ける。30分ほどすると、夫が起きてきて仕事の準備をして出かけるので、コーヒーを作って送り出す。30分ほどすると夫が起きてきて、仕事の準備をするので、コーヒーを入れて見送る。ここでようやくひと息。自分のためにコーヒーを入れ、適当に朝食を済ませ、ニュースをチェックする。その後は仕事と家事に取りかかり、気づけば子供の迎えの時間だ。毎日がこんな調子で、案外無駄にしている時間もあると感じる。子供の迎えから夕食の準備までの間は、体力が切れるため1時間ほど昼寝をするようになった。最近はジムにも行けず、会費がもったいないと思いつつ、どうしても行く元気がない。朝の時間もあっという間だが、1年もあっという間なのだ。年を取るのも早い!もっと時間を大切に使わねば。(S.U) |
(2024年11月16日号に掲載)