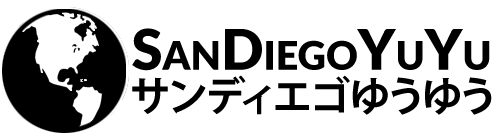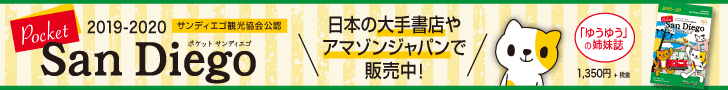Featured

(2023年11月16日号に掲載)

 |
▽40年を超える米国滞在。思い返せば、自分の生活空間には必ずと言っていいほど猫がいた。近所の飼い猫が垣根を飛び越えて “食客” になるケースがほとんど。実在の飼い主を無視するほど居心地が良いのか、帰らずに居候を決め込んでしまう。猫に縁があるものの、譲渡されたことはなく、私たちも来客を迎えるようにエサや簡易寝床を提供するだけ。隣家は保護猫が集まっているのか、複数の猫が定期的に住み替わり、遊びに来る猫種も様々だった。こんな状況だから、自分たちがペットを飼わなくても動物の “癒し効果” を享受できた。なぜ、我が家に移動してくるのか? 隣りは訳アリの雑居家族で、不協和音が絶えず、朝な夕なに怒号が飛び交っている。猫たちはそんな生活環境から避難してきたのかもしれない。▽日本では10代前半にコーギーの子犬を飼っていたが、明確な主従関係の構築、規則正しい散歩の日課など、求められるルーティーンに負担を感じるようになっていた。やがてネコ派に鞍替え。飼い主としては、犬の「依存性」 より猫の「無頼性」 が気楽だ。生まれながらの独立独行ぶりが、何とも心地良い。「元気か?」「まぁね!」のアイコンタクトで済むからね。▽“家族” として迎えたメス♀のオレンジタビーとは7年2か月を共に暮らしたが、3年前に最期を看取った悲しさが癒えることはない。暫くはネコなしで生きる。(SS) |
 |
|
 |
▽パソコンの画面に向かうと、愛猫がやってきては、好奇心旺盛な瞳でモニターを覗き込んで、時にはキーボードを自らの寝床にしてしまう。そんな彼らの行動に、苛立つことなどできず、まぁ、何をされたって、許してしまうのが、猫を愛する下僕の日常だと思う。締切りが迫るほど、我が家の猫はその魔性をますます発揮する。▽子どもの頃、実家には常に猫がいた。「ミー」と「ブー」、愛くるしい親子猫は、昭和30年代のシンプルな「ねこまんま」で育ち、キャットフードやトイレ用の砂、獣医の手も必要とせず、健やかに暮らしていた。毎晩、私と一緒に眠り、小学校への道すがら、跳ねるようにして見送ってくれた。▽アメリカへの移住を経ても、猫との不思議な縁は切れることがない。ワシントン州の学生寮で出会った「マサヨシ」は、冬のある日、雪をかぶって窓辺に現れ、私の心を暖かくした。サンディエゴで迎えた野良猫「ピピ」は、すぐに我が家の一員となり、福猫となった。彼女とともに昼寝をする時間は、日々の忙しさを忘れさせてくれる至福のひとときだ。耳の後ろを優しく撫でれば、ピピは満足げに喉を鳴らし、その穏やかなゴロゴロ音が周囲の喧騒を遠ざけてくれる。猫との時間は、幸せが温かく、柔らかいものであることを教えてくれる。彼らは、言葉を超えて、生きとし生けるものにとって、大切なことを伝えてくれてきた気がする。 (NS)
|
 |
▽最初に我が家にやって来たのは、つがいのセキセイインコ。ブルーのメスとグリーンのオス。2羽はとても仲が良かった。一緒に東京の狭い団地から田舎街の一軒家に引っ越して、鳥小屋も大きくなり、のびのびと嬉しそうだった。開放的な場所に移住して、両親は自分たちの夢を少しずつ実現。うさぎ、鶏、羊が一家のメンバーとして次々と迎え入れた。一時期は、子豚2匹の里親も引き受けるなど、我が家の庭は小動物園状態になった。田舎とはいえ、住宅街の一角にあった実家。物珍しいのもあって、近所の子供たちがよく庭に遊びに来ていた。▽私が高校生の時、初めて犬を飼った。ブリーダーの家に最後に残っていたゴールデンレトリバーのオス。やんちゃな子犬時代は手を焼くこともあったけれど、優しい子で、受験勉強で疲弊していた私の癒しでもあった。大学進学で家を出て、その後、アメリカに渡ってしまい、愛犬の世話を両親に任せることになり、最期を迎える時も一緒にいられなかったことが今でも悔やまれる。▽現在、我が家には2匹の猫がいる。高齢のお婆ちゃんと年齢不詳男子。喧嘩もせず、くっつきもせずのニュートラルな関係。人間が大好き。そして2匹とも、とても優しい性格。多少手荒に遊ばれても怒らない。私の体のどこかに触れながら、気持ちよさそうに寝る姿を見ていると、ほんわかとあたたかな気持ちになれる。(RN)
|
 |
アメリカに来て驚いた。ほとんどの家にペットがいる。私は18歳まで福山市で暮らしたが、実家には多くのペットが飼われていた。犬猫はもちろん、ウサギ、金魚、鯉、熱帯魚・・。しかし、東京の下宿生活から始まってアパート暮らしでも、ペットを飼うことは論外だった。自分の生活空間で動物の世話をする、という時間と心の余裕が全くない。勤めた出版社は締切り前の2週間は深夜に近い帰宅が当たり前。もしくは会社の机の上で仮眠を取り、仕事を続けるという日常なので、自分の面倒を見るのがやっとこさ。ペットが居ようものなら、何匹殺しただろうか(!)というほど髪を振り乱しての生活だった。やがて、忙殺される生活に見切りをつけた。会社を辞めて糸の切れたタコ状態となった私は、世界をうろついた。ますますペットどころではない。結局、私の生活にペットが存在するというオプションは有り得ないまま今日を迎えている。友達が「ペットに現を抜かしている人の気が知れない。動物に費やす時間とエネルギーがあるなら、人間に注いだ方が価値がある」と豪語していた。私も常々、彼女の意見に賛同していたものだが、同様に子を持たぬ彼女が、最近猫2匹を飼い始めた。すると、話題が猫のことに集中する。私は親でもないし、里親?でもないので、そういう話題にはついていけない・・・。ゴメン! (Belle)
|
 |
|
 |
最近、犬と散歩してる人が多い。そして、ほとんどの犬は吠えることがない 笑 それはいいんだけど、とても迷惑なことがあって、、犬のうXこが、歩道に落ちまくってる! (キタナーい!)。お隣のメヒコでは「あるある」だけど、あちらは野良犬も多いから仕方ない。しかし、こちらは滅多に野良犬を見かけない (というか、いない 笑)。飼い犬ばかりなのに、なぜ、うXこが散乱してる? 楽しいお散歩タイムも、うXこ踏みそうになるので、緊張しまくり 笑。ひどい時は2Mごとに1つはある (!!)。なぜ? この街は親切にも、犬のうXこ用のビニール袋まで用意してあるのよ。ある日のこと、現行犯を目撃してしもた! 大柄なおじさんのチワワが他家の人工芝にうXこした (!)。彼はどうするのかと振り返ると、、うXこは放置。おじさんは袋も持ってなく、そのまま過ぎ去っていくではないか! (怒!)。これがほんとのくXじじぃ! (?) 笑。目の前で大型犬を押さえて、わたしが通り過ぎるのを待ってくれた女性が「今から袋を取りにいくけど、あそこにわたしの犬のうXこ落ちてるから気をつけて」と親切に教えてくれた。・・のはいいけど、そのワンちゃん以外のも10個くらい落ちてた 笑。飛び石ゲームみたいに歩道を歩くってどーいうこと? 笑 犬飼ってる人にお願い! 「うXこは拾ってね」。でないと、くXじじぃ・ばばぁって呼ぶからー! (マジ笑!)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
私が子供の頃(小学生くらい)は、道端で放し飼いの犬に遭遇することが多かった。当時は、私の家にもオスの柴犬がいたが、なぜかその柴犬は、私のことを自分よりも下だと思っていたのか、私にはよく「ウゥ〜」と怖い顔をして威張っていた。父には従順でおとなしかったのに・・。その名はポチ。誰が付けたのか知らないが、とても安直な名前・・。まぁいいか。とにかく、後から来た新参者の私が気に食わなかったのかも。そんなワケで、私は犬がとても苦手だった。放し飼いの犬に出くわすと、半べそかきながら、走って家まで逃げ帰ったものだ。昭和の頃は、外で犬を飼っている家が多かったのだと思う。最近は、人間の子供のように大切にしている家族が大半だけど、当時、我が家にいた犬は、ドッグフードではなく、味噌汁をかけたごはんを食べ、台風だろうが猛暑だろうが、ずっと外にいた。そんな環境にもかかわらず、17年も長生きしてくれた。いつからか、犬もほとんどが室内で飼われるようになったせいか、放し飼いを見かけることもなくなった。私も犬は怖くなくなったが、大型犬はまだちょっと苦手。怒らせたら、間違いなく大ケガさせられそうだから・・。チワワくらいなら勝てるかも。飼い主と散歩している犬を眺めながら、「勝てそう」「負けそう」を区別している自分がいる。犬が怖かった頃の記憶がそうさせているのだろうな。(SU) |
(2023年11月16日号に掲載)
Featured

(2023年11月1日号に掲載)

 |
▽日本滞在中に観ていたTV番組が47都道府県の「カテゴリー別・最下位ランキング」を発表していた。「流行鈍感 No.1」の不名誉な栄冠が与えられたのは、私の故郷である福島県 (調査方法は知らず)。長期米国生活者には、県民性がどうの、各県の優劣がどうの——なんてのは重箱の隅を突つくナンセンスとしか思えないが、最悪のファッションセンスに福島が選ばれてしまい、さすがにショックを隠せなかった。▽若い頃の自分はブランドに全く興味がなく、流行オンチを地で行く、野暮天を絵に描いたような青年だった。それが還暦を過ぎ、老年世代の仲間入りをしてからは、オシャレは Quality of Life の重大要素と思えるようになった。自分にどれだけ余生が残されているのだろうか? 計測できない「寿命のマジックナンバー」を恐れず、可能な限りファッションセンスにこだわって死を迎えたい——そう考えている。▽大層なことを言っても、私は今でも黒/紺系統に身を包むくらいで、流行オンチに変わりはない。誰の言葉か忘れたが、ファッションとは人間の本質を露出する覚悟を伴う勇気ある行動らしい。シンプルな服装でも自己の特質を表出できたなら、それこそが見事なオシャレ。三島由紀夫氏が生前に「私らしさのファッションは10年前の流行を着ること」と言っていたが、なるほど・・妙な説得力があった。 (SS) |
 |
|
 |
▽黒いタートルネックとジーンズ。アップルの創始者、スティーブ・ジョブズはいつも同じ服を着ていた。「服を選ぶための時間を、仕事に使いたい」というのがその理由らしい。ジョブズだけでなく、オバマ元大統領、マーク・ザッカーバーグ、経営コンサルタントの大前研一さんも毎日同じ服を着ているとのこと。作家の向田邦子さんは、「同じ服」を「色違い」で、店から在庫がなくなるくらい大量に購入していたという。▽日本に里帰りする度に、街の人たちのおしゃれな服装に驚かされる。それに対してアメリカのファッションは、テキトーだ。流行という概念がなく、安くて良ければそれでOK。自分さえ気に入っていればよく、他人と違うことがむしろ良いとされる。▽私の定番は、ジーパンとTシャツ。かつてはさまざまな服を購入し、クローゼットに溜め込んでいた。痩せたら再びその服を着ることを夢見ていたが、購入した服は長い間、そのままの状態で眠っている。リモートワークが主流になってからは、ヨガウェアが私の定番となった。動きやすく、リラックスでき、そのまま散歩やジム、買い物にも行くことができる。もともと面倒くさがり屋だった私の性格は、長いアメリカ生活によって、さらに磨きがかかった。(NS)
|
 |
十代でファッションに興味を持ってから、ずっと服&小物好きだ。今でも、自分の服を選んで着ることを楽しんでいる。娘が生まれてからは、その興味が更に増した。彼女が小さかった頃、娘は私の買ってくる花柄やピンク、ユニコーンやフリルの付いた可愛い服を喜んで着ていた。でも、7歳ぐらいから急に可愛らしい服を拒否するようになった。それから毎日、ジーンズにTシャツ、黒やグレーのフーディしか着なくなった。つまらないと思いつつ、彼女が好きそうな服しか買わないようにした。ところが9才になると、急にファッションに興味持ち始めたようで、流行りのクロップトップや私が来ているようなカーディガンやトップスが欲しいと言い出した。最近は、おそろいっぽいカーディガンを着たりして、娘とファッションを楽しんでいる。ちなみに11才の息子は全く着るものに興味がないらしく、毎日同じショートパンツにジップアップパーカー(中のTシャツは違う)を着て、1週間を過ごす。翌週は違う色のショートパンツと違うジップアップパーカーに変えて、また1週間。。。毎日いろいろな服を着て、ランドリーバスケットに入れる娘と反対に、なるべく洗濯物を少なくしようとしてくれる孝行息子だ。 (YA)
|
 |
日本で出版社勤めをしていた頃は、スーツやワンピース、もしくはそれなりにフォーマルな恰好で出社していた。そして靴、バッグ、アクセサリーもかなりトータルコーディネートされていた。今でこそ、フォーマルっぽいジーンズもあるが、かつてのジーンズは “スーパー普段着” のコンセプト。そんなジーンズで初めて故郷・福山に帰省した際、姉に「あんた! その身なりで新幹線に乗って帰ってきたのか。それほど洋服を買うにも事欠く生活をしているのか?」と驚かれ、呆れられ、嘆かれたことがあった。大昔の話。やがて時は過ぎ、ジーンズは洋服の中で市民権を得て、日常ファッションとしての地位を確立し、生活に密着した洋服になっている。特にアメリカでは。銀行員などのお堅い職場以外、仕事にも遊びに行くのもジーンズにスポーツシューズがお定まりファッション。毎年、私はヨーロッパに出かけるが、やはり彼の地でもジーンズ族を見かけるには見かけるが、アメリカとの決定的とも言える違いは、ヨーロッパではスポーツシューズではなく、スリップオンの革靴を履くのが一般的。それだけでジーンズもファッションの一部となり、普段着ではなく外出着に見えるから不思議。スラッとした紳士がジーンズ+素敵な靴で歩いている姿はとてもカッコいい! アメリカ人男性よ! 是非、見習ってほしいなぁ・・。 (Belle)
|
 |
|
 |
好きなようで面倒くさいのが、ファッション。髪型も服もアクセサリーも、はっきり言ってどーでもいい。 (笑) 寝癖があればドライヤーで直すのではなく、そこは切ってしまう。( 笑) 中学高校時代は、休みの日も着る服を考えるのがめんどーだったから、制服と部活のジャージで過ごした。(笑) だけどー、とっても目立ちたがり屋なので、人とは違うものを好む。矛盾のかたまり。(笑)。みんなが選ぶ無難な色やものはイヤで、サングラスは緑だったり、車は古いヨーロッパ車だったり、たま〜にあるパーティーで、いつもお洒落な格好をしているメキシコ人のお姉さんに“あなた、ファッションデザイナーになれるわ!”とお褒めのお言葉をもらうような格好をする場合もあ〜る。紺色のブレザーがいる時があって、そもそも大人サイズは大きすぎるので、小学生の制服コーナーで探し 笑、ふつーのデザインはイヤだったので、子供制服業界ではメジャーなFrench Toastというブランドでかわいいジャケットを10ドルで発見して、みんなの注目を浴びた!(んー、どの意味で浴びたかは、んー笑)。自分はどうでもいいけど、人のファッションを選ぶのは好き。ちなみに友人H部長がこじゃれた格好や帽子を被っているときは、すべてあたいがコーディネイト。やっぱ持つべき友は、こーでねーと!(古い?おやじギャグには流行り廃りはないの! 笑)(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
最近ジーンズとTシャツしか着ていない気がする。秋になって寒きなってくると、Tシャツの上に軽いジャケットを着る。もっと寒くなったらダウンジャケットを着るくらい。要するに、服を選ぶのもコーディネートを考えるのも面倒くさいのだ。基本的に動きやすくて家で洗濯可能、アイロンがけのいらない服ばかり着ている。オシャレはしたいが、どうしたらオシャレになるのか、店に行っても何を買ったらいいのかわからない。服を買いに行くのも嫌。私にとって服を買いにいく時というのは、破けたり、寒くなったのに長袖がないといった必要性があったら行くもので、用もないのにわざわざ服を見に店へ行くということはない。また、洋服を買いに行く時は、目的のものが売っている店に直行し、それだけを探す。試着はできる限りしたくないが、最近は店が空いていて、自分に試着する元気があればする。返品しに戻るのが面倒だから。すごく元気(体力?)がない時は、Amazonで適当に選んでとりあえず買う。家で着てみてサイズなどが合わなければ即リターン。私がこんなだからか、長女が同じように服選びが苦手になってしまった。気が付けば私と同じような服ばかり着ている。しかも、日本の中高生の制服を羨ましがっている。毎朝何を着ていくか悩まなくていいからだ。ホント、オシャレって難しい。(SU) |
(2023年11月1日号に掲載)
Featured

(2023年10月16日号に掲載)

 |
▽遠い昔の小学校時代。子供たちに豊かな情緒を涵養 (かんよう) せしめる目的から、文部省 (当時) 推薦作品など2本立てを楽しむ「映画教室」があった。驚くなかれ、教育映画の上映後に青年向けの恋愛映画も児童に見せていた! 舟木一夫、西郷輝彦、橋幸夫が (古くてゴメン) 自分のヒット曲と同名の映画に出演し、ヒロインも20代の吉永小百合、松原智恵子、和泉雅子と華やかな顔ぶれ。純愛がテーマなので、小学生にも無害と判断? 先生たちが見たかった? 私たちは口を半開きにして、大人の恋愛模様をボーッと眺めていた。舟木一夫『絶唱』の一節「♪ 愛おしい山鳩は~山越えてどこの空~名さえ儚 (はかな) い~淡雪の娘よ ♪」を耳にすると、今でもドキドキする。▽半世紀前の日本。男のエエカッコシーにロマンの香りが漂う新車のCMがあった。最終列車に乗り遅れた女を新車に乗せて、次の駅まで颯爽 (さっそう) と送り届ける男。女「お名前だけでも」。男「急がないと、また乗り遅れますよ」。会話はこれだけ。ナレーションが入る。「雪明かりに忘れられぬ、サファリブラウンのブルーバード。心に残る男のクルマ!」。見ていて冷や汗が流れたが、寡黙な男がモテるイメージ全開の新車は空前の大ヒット。ジュリーも歌ってたな。「♪ ボギー! あんたの時代は良かった! オトコがピカピカのキザでいられた ♪」。あの頃のダンディズムは消え失せた。今では、無口すぎる男は変質者に間違えられる。(SS) |
 |
|
 |
▽スマホやメールが普及する前、連絡は家の固定電話を使っていた。彼氏からの連絡を家族に知られぬように、電話の前でドキド待っていた記憶がある。渡米してからは、国際電話料金が高額で、用件だけを話してすぐ切っていた。ショルダーホンを購入した友人からは「電話するね」と前もって告知が来た。黒電話、プッシュホン、ショルダーホン、ポケベル、ガラケー、スマホと、連絡手段は進化してきた。今は好きな時に、いつでもどこからでも、すぐに連絡ができる。その昔、「真知子」と「春樹」のすれ違いの運命に、母とともに息をのんで見入っていたTVドラマ『君の名は』が懐かしい。▽高校時代、全商珠算検定で1ドル=360円と教えられた。しかし、社会人になる頃に変動相場制へ移行。80年代の留学時には1ドル=220円。1995年に姪の結婚式で里帰り。空港で1,000ドルを両替すると、なんと70,000円にもならない。銀行スタッフの「1ドル80円でも、実際のレートは・・」との言葉に驚愕 (がく)。日系2世の知人の奥さんは、以前、住み込みのお手伝いさん付きで横浜に暮らしていたそうだが、「今度は自分がお手伝いさんとして働かなくては」 と言っていた。そして今、1ドル=150円の円安。新たにアメリカへ移住した知人の驚きの表情が目に浮かぶ。為替の流れは予測不能。ビジネスをしている人は大変だ。歴史の中の円の動きに思いを馳せる。(NS)
|
 |
▽高校生の娘の話を聞いていると、自分の頃はどうだったか、思い返すことがある。娘と同様、友達関係、授業の課題やテスト勉強に追われて大変だったな〜。大体、何となく同じような感じだけれど、決定的に違うのはインターネット、スマホの存在。友達との会話、学校の連絡事項、成績のチェック、何でもスマホで済ませてしまう。分からないことがあれば、自分でササッとネットで調べてしまう。あの頃、スマホがあったら、どんなに便利だったことだろうか——。▽髪を切りに行ったら、若い日本の子がアシスタントとして働いていた。髪に色を塗ってもらっている間に、最近の若者言葉についていくつか教えてもらった。エモい、量産型、草、など。「それマジ草」 などは見かけていたけれど「マジソウ?」 で意味分からず。草はクサと読み、大笑いを意味するとは想像もしなかった。日本の言葉にとてもついていけない感覚は年々増している。そして、アメリカの若者がテキストのやり取りで使う省略語も理解できないものが結構ある。「I will do it rn」とか。rnって何? 娘に尋ねたらright nowと即答。最近は慣れてきたけれど、句読点の省略 (消却が正しいかも) もスゴい。最近の若い人の傾向らしい。私が若者だったあの頃、今の私のような年齢層は私たちを見て「訳わからん!」と、首を傾げていたのだろう。(RN)
|
 |
このテーマをもらって頭に浮かんだのは、かつて “ゴッド姉ちゃん” と呼ばれた和田アキ子が歌う「♪あの頃は~♪~ハッ♪」のフレーズだ。これ以外に歌詞もメロディーも何も覚えていない。歌い出しと、1フレーズ後に発せられる「ハッ!」があまりにも強烈な印象で、それが記憶に残っているだけの曲。曲名は何だったのか? 「あの頃は」とだけ書いてYouTubeでサーチすると、ホントにあんたはエラい! 即座に「古い日記」というタイトルが出てきた。へぇ~、そんな曲あったのか。全く覚えていない。発売は1974年とある。約半世紀も前の曲だ。あぁ、そうか。古い日記を読み返してみると「あの頃は」・・となるのだね。私といえば、日記を書く習慣は全く持ち合わせていないが、学生時代からカレンダー手帳にその日の出来事だけをきちんと書き記していた。良い機会だからと、その手帳を探したら、遥か昔、19歳の時の手帳が出てきた。開いてみたら、何と何と、初代ジャニーズのメンバー、飯野おさみのサインが目に飛び込んできて、一気にあの頃の感覚が甦った。私は中学・高校とジャニーズの追っかけをしていたのだ。ジャニーズ解散後、彼が木の実ナナと岡山に来た際、新幹線のホームに見送りに行った時にもらったサインだ。あぁ! あの頃は、こんな人生になるなんて・・・誰が想像しただろうか。 (Belle)
|
 |
|
 |
どのくらい昔のことを「あの頃」というのか分かんないけど、、先月、ふるさとの愛知県に帰ったとき、半年ぶりにお姉ちゃんの末娘・彩雲に会った。彼女は幼い頃から絵を描いたり、お菓子作りが好きなワタシ系の高校生。冬に再会した時は、お正月というお祭り騒ぎで人も多かったし、彼女と話す機会がなかった。今回はお土産として、ココナッツ・フラワー (ココナッツの粉) で何か作るかなぁ?と思ったので、試しにあげてみた 笑。そしたら次の日、そのココナッツ・フラワーでケーキとパンを作ってた! 結構ビックリ。聞くところによると、ググってココナッツ・フラワーを使ったレシピを探しても、日本語は見つからなかった。パッケージの裏に使い方が英語で表記されてるけど、読めないっ! 笑。適当に作ったらしい (ホント、わたしに似てる 笑)。そういえば、わたしも彼女くらいの歳に、裁縫したり、お菓子作りしてたよなぁ。お母さんの新車にシートカバーを縫って作ったり。・・・わたしってスゴくない? 笑。でも、ちょっと違うところは、写真を見ると、彩雲の周りには女子の友達しかいない。わたしが高校生の時は男子を家に呼んで遊んでいたわ。あの頃のわたしは、女子がすることも立派にしてたし、男子と対等に遊べる逞しいオンナでもあったってことねー。ちょっと待てよ。あの頃だけじゃない。現在も続いているわ 笑。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
子供時代を過ごした昭和が懐かしく、恋しく思う瞬間がある。今の時代が断然、何かと便利だが、昔と比べると、子供たちの自由が制限されている気がする。学校から帰宅すると、習い事だったり、塾だったり、とにかく忙しい。友達同士で遊ぶ場所も相手の家か自宅。子供は車で移動できないので、近くのコンビニやカフェで待ち合わせて、おしゃべり程度で切り上げる。私が子供の頃は、小学校低学年から近所の友達と駄菓子屋さんに寄ったり、公園や海岸へ行ったりと (実家の目の前が海)、放課後は割と自由気ままに遊んでいたものだ。そういえば、台風が近づいている海岸へ友達と2人で出かけ、荒波が土手に当たって波飛沫が舞い上がる様子を見たい一心で、大波が来るのを待っていた——なんてこともある。防波堤で波が砕ける音がすると、飛沫が土手を越えてくるのが分かるので、走りながら後方へ逃げる——というスリルを楽しんでいた。何とも危険な遊戯に興じていたものだ。今、子供たちがそれをやろうものなら、私は絶対に制止する。私の母は自分を野放しにしすぎたのだろうか? いずれにしても、便利な現代も良いけれど、規制が緩やかで、ほのぼのとして、何かと自由に恵まれていた昭和時代に郷愁を覚える。(SU) |
(2023年10月16日号に掲載)
Featured

(2023年9月16日号に掲載)

 |
▽1枚の古い写真。子供時代の家族旅行で羽田から九州へ飛ぶ前に、機内で撮影した初フライトの記念写真。機長さん、客室乗務員さんと一緒に私のファミリー4人が収まっている。よく承諾してくれたものだ。時代も大らかだったのか? 満面の笑みを湛える父母と幼い弟をよそに、私の表情だけが硬くこわばっている。実は、心の中で「無事に届けてください」と念じていた。半世紀が過ぎても、フライト恐怖症は続いている。航空事故の7割強は離陸時の3分間、着陸時の8分間に集中していると言われ、魔の11分間と呼ばれている。今は、着陸進入する旅客機に空港から誘導電波 (ILS) を送信しているので、安全性が極めて高い。それでも、離着陸時に襲われる緊張感は変わらない。妻が隠し撮りした私の顔は、昔の写真そのまま。▽ポートレートが苦手の私に写真家が秘策を授けてくれた。目立つモノ・・例えば、一房のブドウのような大きめの果物・・を携えてカメラの前に立つと、自分が被写体というプレッシャーから解放されるらしい。自意識が緩和されて、リラックスできるので、表情も柔和になるとか。良いことを聞いた。猫を抱いてみた。すると、撮影直前に暴れ出し、引っ掻かれるわ、噛み付かれるわで、普段は撮れないミラクルショットが手に入った。これは意外性もあって面白い。写真嫌いを克服できるかも。(SS) |
 |
|
 |
▽昔、カメラといえば、コダック一強だった。取材シーンでカメラマンを見かけると、彼らの手にはほとんどの場合、コダックが握られていた。フィルムも現像もコダックだった。でも、1990年代半ば、デジタルカメラの台頭とともに、その風景は一変した。家庭にパソコンが普及し、高性能のプリンターも登場。写真の印刷が少なくなり始めた。そして、2013年にコダックが破綻した。「カメラの歴史を牽引してきたあのコダックが・・」と、仲間うちで話題となった。さらに、2008年には高性能カメラを備えたiPhoneが世に出た。まさしく新時代の到来だった。▽先日、日本の友人からLINEが届いた。彼女が「自分の遺影撮影をしてきた」とのこと。写真館は「おばあちゃんの原宿」として知られる巣鴨にあり、メイクや髪のセットもしてくれるそうで、写真には彼女の魅力が溢れていた。そういえば、母の葬儀の際に「おふくろの良い写真あるか?」という兄の電話に焦った経験がある。手持ちの写真を探しても、集合写真で小さかったり、強風で髪がボサボサだったり。そもそも、どの写真も主役としては写っていなかった。でも「遺影撮影、しときましょうね」と、元気な時に提案するのは、どうも気が引ける。そう考えると、友人の行動は賢明だと感じる。私も日本に里帰りした際に、巣鴨に行ってみようと思う。(NS)
|
 |
この夏、数年ぶりに日本に帰省した際、叔母夫婦に会いに行った。「後期高齢者になっちゃったわよ」と愚痴 (グチ) る叔母だったが、まだまだ若々しく元気そう。夕食後、居間で寛いでいると「こんなにたくさんあるのよ、どうしよう」と、叔母が数冊のアルバムと大きな箱を抱えて現れた。私の母たちの子供時代から、若かりし頃の祖父母、曽祖父母、親戚、友人、近所の人たちなどの写真の数々。母と叔母の父(私の祖父)は写真撮影が趣味だったらしく、膨大な数の写真の大半は祖父が撮ったと思われる。母の母(私の祖母)は病気のため40代という若さで亡くなっている。私は会ったことがないのだが、10代頃の祖母の可愛い笑顔、看護師長として働いていた頃の凜 (りん) とした佇まいの祖母は素敵だった。アルバムの台紙に貼られた写真の配置や説明書きは祖父の作業らしいが、彼の几帳面な性格と子供への溢れんばかりの愛情がよく表れていて微笑ましかった。デジタル化してクラウドに保存しておけば、いつでもどこでも見られて便利ではあるけれど、こうやって、ペンで書かれた文字をなぞりながら手に取って見る写真は良いな・・と改めて思った。母たちが子供時代に使っていたというお茶碗とお皿と一緒に、数枚の写真をアメリカに持ち帰った。写真の中では、今は亡き私の母も、はにかんだ笑顔の少女として生きている。(RN)
|
 |
1999年に京セラが世界に先駆けてカメラ付きの携帯を発売した・・とある。当時はまだ、人々のニーズが熟していなかったようだ。2007年にアップル、2008年にアンドロイドが、所謂 (いわゆる) スマホを発売し、日常的に写真をすぐ誰かに送ることが手軽にできるようになり、徐々に普及の兆しを見せ始めたが、それでも2010年の普及率は40%、それが2022年には94%となり、さらに今年は98%を超えているそうだ。こうなると、スマホを持っていないのは乳幼児とスーパー高齢者だけ?と思ってしまうほど、老いも若きも「カメラ機能付き電話」を常に携帯しているのである。まさに一億総カメラマン時代。スマホはかつてのような紙焼きの手間も要らず、パネルをタッチした瞬間に写真が見られるという、夢のような技術を超!身近なものにした。世界中どこにいても、その地の情報が写真付きで瞬時に各地に届けられる。プライベートの楽しみだけでなく、時にはメディアで採用されたり、はたまた偶然、事件の近くにいた人が撮影した映像が犯人逮捕の情報に繋がったりと、社会でも大活躍。撮り続けた写真はスマホにドンドン貯まる。しかし、紙焼き写真もそうだったが、スマホ写真も撮影直後は見るけれど、時が経つと、それらを眺める機会はほとんどない。ま、う~んと年を重ねて、自分の若かりし頃を振り返る楽しみのために、せっせと撮り貯めておこうか! (Belle)
|
 |
|
 |
セルフポートレート→ 自撮り→ セルフィーって呼び方は変わったけど、それにしても、皆さん、セルフィーお好きよねぇー。そんなことしたらさ、遠近法で自分が一番不利 (誰よりも顔がデカく写る 笑) なのにねー 笑。自分の手や影は撮るけどね。それに自分より他の人を撮るほうが楽しいよ。今までの旅行の写真を見ると、他の人のばかりで、自分が写ってない 笑。よく考えてみたら、誰かに撮ってもらうしかない自分の写真をアルバム代わりに持っていた。なーんでしょう? それは、、これまでに交付されたパスポート、免許証、学生証&あらゆるID~。初めて原付免許を取得した16歳の写真に始まり、18歳から今までX回 (笑) 更新した全ての旅券。ただ、カリフォルニア州運転免許の写真は、ある時から昔の一枚を使ってくれるので、よく言えば、いい感じで時が止まっている 笑。でも、高校のときの写真が免許証だけなんて、寂しすぎるわー (ヤンキーすぎる? 笑)、と思っていたら、昨年末に実家に帰ったとき、お母さんの愛用しているコップに、、どうも見覚えがあるモノが・・。それは高校のクラス写真をコップに印刷したものだった 笑。しかも目立ちたがり屋だったので、クラス全員が並んでいる最前列のド真ん中に、エラそーに座っているのが、わたし・・ 笑。よかったー! 高校時代のわたしの写真、2枚はあるわー (1枚と1個? 笑)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
写真を撮るのは好きだ。家族で旅行に出かけても、大体カメラマンは私で、自分が写っている写真などほとんどない。それでも、新型コロナのパンデミック中、誰もがマスクをしているときは、顔がほとんど見えないので、写真にあまり抵抗なく入っていた。しかし昨年、姉と森山直太朗のコンサートに行ったとき、会場で写真を撮っていたら、直太朗ファンは優しい人が多いのか「お写真、撮りましょうか?」と声をかけてくれた。私たちはお礼を言って、マスク姿で撮ってもらったのだが、さらにその方は「マスクを外した一枚を撮りましょうか?」と提案してくれた。心遣いに感謝しつつ、私は内心「あ、マスクのままでいいんです・・」と思ったけれど、断ることもできず、再びお礼を述べてマスクなしの写真も撮影してもらった。その写真を確認したら、思っていたよりも不細工な自分にショックを受けた。マスクって、いい感じに顔のイヤな部分を隠してくれるんだよね〜。お化粧のとき以外、自分の顔を鏡で見ていないのも災いしたか。あれから1年が経ち、さすがに2023年ともなると、新型コロナ感染の規制は大幅に緩和され、マスクを外している人が絶対多数となった。今年の夏も日本へ帰省し、家族とあちらこちらに出かけたが、私はいつものようにカメラマンに徹した。これでまた、何年も写真に写ることはないだろう・・。(SU) |
(2023年9月16日号に掲載)