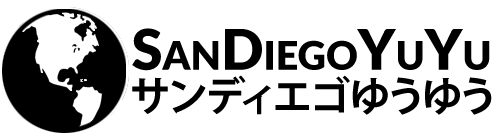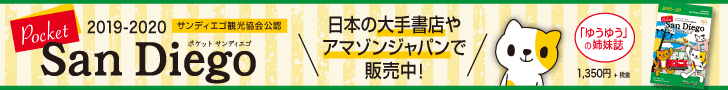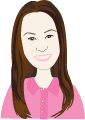▽私の初恋は7歳。小粋に着こなした柄の良いシャツ、端正に折り曲げた上着の袖口、都会的でスタイリッシュなベレー帽がチャームポイントという、ボーイッシュな魅力に溢れる少女だった。彼女宅の郵便箱の上にそっと “初恋文” を置いて (中に入れましょう!)、木陰から成り行きを見守る私。すると、手紙は一陣の秋風に吹き飛ばされ、優雅な弧を描きながら舞い落ちて、枯葉の中の「紙切れ」となった。そして、家から出てきたお婆さんに電光石火のごとく掃き捨てられてしまった。その絶妙なタイミングと手際の良さに呆然とし、この思いは通じないと確信。この失敗がトラウマになったのか、以来、私はラブレターというものを書いたことがない。
▽私が入学した私立高校は附属中学エスカレート組を合わせて首都圏出身者が約8割を占めていた。残り2割は私を含む地方出身者で、都会の事情に疎いばかりか、言葉の端々 (はしばし) に出る地方訛 (なま) りに気後れを感じていた。入学直後に有志が集まり、喫茶店で親睦会が開かれた。私には初めての喫茶店体験。皆がナポリタンやカレーピラフをオーダーする中、カツ丼を注文した私に 「ユーモアのセンスがスゴい!」 と一同大爆笑。これを機に人気急上昇。失敗転じて何とやら。本当にカツ丼を食べたかった私は、冷や汗をかいていた。 (SS)
▽私が入学した私立高校は附属中学エスカレート組を合わせて首都圏出身者が約8割を占めていた。残り2割は私を含む地方出身者で、都会の事情に疎いばかりか、言葉の端々 (はしばし) に出る地方訛 (なま) りに気後れを感じていた。入学直後に有志が集まり、喫茶店で親睦会が開かれた。私には初めての喫茶店体験。皆がナポリタンやカレーピラフをオーダーする中、カツ丼を注文した私に 「ユーモアのセンスがスゴい!」 と一同大爆笑。これを機に人気急上昇。失敗転じて何とやら。本当にカツ丼を食べたかった私は、冷や汗をかいていた。 (SS)