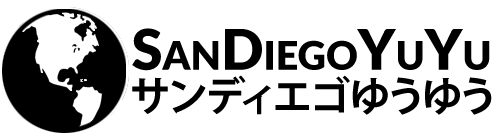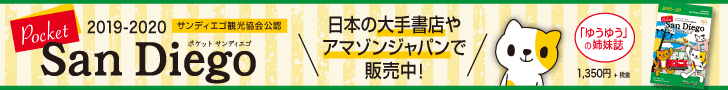ギリシャ悲劇『オイディプス王』を引用するまでもなく、父と息子は終生の否定的関係と思っていた。父が他界する半年前までは —— 。父は平気で感情を表に出す直情径行/大言壮語の人だった。ホテルのラウンジで歌う歌手に「ブラボー!」と叫んで立ち上がったり、赤の他人を怒鳴 (どな) りつけたり、誰もが驚く行動ばかりで、私は父との距離を置いていた。父は会社勤めをしたことがなく、祖父の遺産で生活していた。弁護士になる夢は果たせず、不動産鑑定士の資格を取得したが、仕事が性に合わず、50歳頃から引退生活のような日々を送り、生き甲斐を見つけられずに76歳で世を去った。酒浸りの晩年は傍目 (はため) にも哀れだった。父はカンツォーネを愛聴し、オペラやクラシックにも通じていた。彼の魂を救済したのは音楽。私は父の日に 『3大テノール世紀の饗宴』 (パヴァロッティ、ドミンゴ、カレーラス) を贈った。最初で最後の父へのプレゼント。すると、父が部屋に飾っていたニーチェの『断章』を額縁 (がくぶち) 付きで送ってきた。「大河と偉大な人間は悠然と曲がった道を行く・・曲折の如きは些 (いささ) かも彼らを怖れしめぬ」 (ちょっと待った! オヤジもオレの生き様も、そんな格好イイものじゃない!)。相変わらずの自画自賛。その年の暮れに冥界へ旅立った。(SS)

 |
|
 |
|
 |
▽社会人になった年の父の日に健康枕とリネンセットを贈ったら、「これは、正月になったら使おう」と、嬉しそうに父が微笑んでいた。軍隊仕込みなのか、朝、真っ先に行なう父のベッドメイキングは感動ものだった。パリッと糊のきいた、真っ白なシーツを毎朝はぎ取り、角をきっちり折りたたみ、シワひとつないほどピンと張り、シーツや毛布や枕カバーを整えていた。▽第二次世界大戦下の日本、19歳の春に大陸へ出征した父は、−40℃のシベリアで極限の飢えと寒さに苦しみ、戦友の墓標の前で涙を流した。復員後は、福島県会津の没落旧家を出奔して千葉に移り住み、母と一緒に八百屋を開いて寸暇を惜しんで働いた。▽「夫婦は人生の戦友」と言うけれど、父はその戦友を亡くして男やもめとなった。でも、朝一番のベッドメイキングに始まり、炊事、洗濯、掃除をひとりで丁寧にこなしていた。▽最近、ベッドメイキングを習慣化している人は、習慣化していない人に比べて「自分が幸福である」と感じているという研究結果 (Humch.com) があることを知った。「小さな達成感や自信 → 前向きな気持ちや行動」といった連鎖が幸福度を上げてくれるとか。遅まきながら自分も父を見習い、毎朝ベッドメイキングをするようになった。(NS)
|
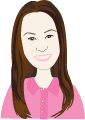 |
私の母国の台湾は他の国と違って、父の日は8月8日となっている。中国語では8と8の発音がパパに似ているからだ (笑)。お祝いしたい気持ちは母の日も父の日も同じなのに、何故か母の日に比べて父の日のお祝いはつい忘れてしまう、という話をよく聞く。でも台湾では、母の日よりも父の日8月8日のほうが逆に覚えやすく、忘れにくいと私は思う (^.^)。偶然にも、私の父の誕生日は台湾の父の日と同じ日! そのお陰で、私と妹たちは毎年一つだけのプレゼントでお誕生日+父の日も両方カバーできていて、超ラク! 父は周りの人に迷惑を掛けないし、本当に優しく、明るくてジョークが好きな人。今年83才になる父は先月、交通事故に遭い、車は廃車になったが幸い体は無事だった。それをきっかけに車の運転をやめることになった。今は、外出時にバスやタクシーを利用している。父とは毎週土曜日にLINEでいろいろな話をしている。こんなに仲良くなったのは不思議な感じだけど、幸せを感じる。父にはもっともっと長生きしてもらい、健康でいてほしい!! (S.C.C.N.)
|
 |
父親っ子だったと思う。母、私、妹の“家族” と一緒に過ごすよりも、無口で、ひとりで好きなことをしていることの多い父だった。父がひとりで映画を観ていたり、音楽鑑賞をしている部屋に行って、一緒に過ごすのが好きだった。私が参加すると、観ている映画の話やクラシック音楽、洋楽の話をしてくれた。洋画、洋楽が好きになったのも父が観ていた (聴いていた) から。海外に憧れて暮らしたいと思い始めたのも、元は父からの影響だ。「若い頃、いろいろな国に行って住んでみたかったけど、できなかったから、子供には好きにさせてあげたい」。アメリカに留学したいと話す私に、こう言ってくれた。今でも感謝している。父は私が日本を出た後、私たち家族から離れ、新しい家族を持った。年がかなり離れた “妹” と “弟” ができた。父の新しい家族はとても温かい人たちだ。里帰りすると会っている。数年前に甥っ子が生まれ、父もすっかりお爺ちゃんをしているみたいだ。幸せそうでなによりだ。「パパ、父の日おめでとう」 (YA)
|
 |
今年78歳になる私の父。若い頃に中学校の美術の教師を辞めてから、ずっと造形教室のようなものを自営で続けている。引退してもよい年頃になり、今は週に1〜2回だけの教室。週末や長い休みに、森の中で1日スクールや数泊のキャンプなどを実施している。教室をずっと前に卒業して、高校生、大学生になった子供たちもキャンプなどに参加しに戻ってきているらしい。ドラム缶に井戸水を入れて、焚き火でお湯にしたドラム缶風呂が大人気なんだよ、と嬉しそうに話す父。パン、タコス、すいとん入りの田舎汁、バームクーヘンなどなど、いろいろなものを作って、食べて、盛り上がっているようだ。数年前に娘を連れて帰省した際は、森に群生する竹を取ってきて、縦に割り、脚立 (きゃたつ) を動員して、みんなと流しそうめんを楽しんだ。今の一番の生きがいは、ライフワークとなっている版画の制作。数メートル四方の大きな木版に掘り出された作品は、父の頭の中を垣間見るような気がして興味深い。暇さえあれば、森の広場で一人、作品作りに取り組んでいるようだ。このパンデミックが落ち着いて、また父に会えるのを楽しみにしている。 (RN)
|
 |
|
 |
母の日は私が子供時代から既に存在していた (と言って、母に直接感謝の意を伝えた記憶がない不届きな娘だった) が、父の日の思い出は全くない…ので、調べてみたら、父の日は1910年にアメリカで誕生し、日本に入ってきたのが1950年頃。そして、実際に祝日となったのは1980年頃。母の日が市民権を獲得して70年後のことだ。やはり、子供を産む母の存在の方が大きい、ということか。それはともかく、18歳で故郷を離れた私は、6月の第3日曜と設定された父の日を家族で祝った、という思い出は全くない。東京の生活になってからは、その日は父と一緒にはいないし、その日を祝う習慣が自分の中に留まっていないので、まして「おや・・」という感じである。しかし、既に30年以上も前に他界した父だが、私の中に少なからず父の影響力が及んでいる。例えば、あの時代に趣味でクラリネットを吹いていた彼は、娘に楽器を嗜 (たしな) ませようとピアノを買ってくれたり (忍耐心のない私は、楽器を練習するより外で遊ぶことを好んだ)、映画やシンフォニー、はたまたサーカスやバー、キャバレーなど、娯楽の世界に数多く連れ出してくれて、私を彼同様の “必殺遊び人” に育てた。私はこの類希 (たぐいまれ) なる幼少時代をくれた父に、毎年やって来る父の日を「父への詫び状」の日として認識する。 (Belle)
|
 |
|
 |
ずっと離れているせいなのか、離れていることに慣れてしまったのか、実家の両親と話すのは、お母さんとは年に2回くらい+実家に帰った時に直接話すくらい。友達に言ったら、少なすぎると指摘されたわ。実家に電話しても、電話機が別の部屋にあって、聞こえないという理由で出てくれず、話せなかったことが何度もある。そのうち、お母さんがスマートフォンを持ち、ラインを使えるようになった。でも、わたしがラインを持ってなかった 笑。兄弟からのリクエストもあり、わたしもラインを使うようになった。それでも今年のお正月は、家電 (いえでん)、兄ライン、姉ライン、妹ライン、母ラインにつないでも誰も出ず、、笑。お父さんは?というと (やっと登場 笑)、なんと年に一度、家電で話せれば良いほう。または会って話すしか、ない (江戸時代か? 笑)。お父さんは「スマートフォンは持たない」宣言をしているので、ラインはムリ。コンピュータ系はダメ。家電しか通じないけど、それも怪しいので、、会って話すしかないのよー (21世紀とは思えん・・笑)。なのでー、父の日は、普段電話をしないわたしにとって、良いキッカケだわ! 電話しよーっと (電話に出てくれなきゃ、意味ないけどね 笑)。姉が家にいる時を狙って、電話するとか (・・だから、現代とは思えんのよ 笑)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
以前に述べたが、私の父は冗談言わない、融通も利かない、東京下町育ちの厳格な男性だ。小学生の頃、『8時だよ、全員集合』の裏番組『俺たちひょうきん族』 が大人気に。多くの友達は “ひょうきん族派” になった。ある日、私が『ひょうきん族』を見ていた時、リビングに登場した父。「何だ? このくっだらねぇ番組は? 消せ! 二度と見るな!」・・ということで、泣く泣く “ドリフ派” に戻る羽目に。地元のお祭りに友達と出かけた中学生の私。祭りの後、コンビニの前で夜11時頃まで話し込んでいたら、どこからともなく、肌着とステテコ姿の父が自転車で登場。「てめえら、何時だと思ってんだ! さっさと帰れ!」と怒鳴 (どな) られた。彼氏ができて、毎晩のように電話で話したい乙女心の高校生。当時はもちろん固定電話、子機なし。たまたま彼からの電話を取った父。「てめぇ、人んちに電話してくんだったら、名前を名乗れ!」と怒鳴り散らす。日本に帰省した時、妹夫婦の家に遊びに行った。夜9時を回った頃、妹の携帯に電話してきた父。「○○(私の名前)は、まだそこにいるのか? さっさと帰れと伝えろ!」と。私、いい大人なんだけど・・。まぁ、それでもいろいろ感謝。父の日には、おいしい焼酎でも贈ろうと考えている。(IE) |
(2021年6月1日号に掲載)

 |
▽試験答案にプラタナスの実 (スズカケノキの果実) を正確に描けば、出席不足でも合格点を与える風変わりな先生がいた。その人は一般教養科目の生物学を教えていた (植物学じゃない!)。満員電車に潰 (つぶ) されて早朝クラスに出るのは辛いので、先生の「温情救済」にすがることにした。授業の面白さを讃えるエッセイと欠席続きの “詫び状” を書いて、果実の外皮に整然と並ぶ突起1本1本を丁寧に描いたら、何と「A」をくれた。「C」の予定調和を超えた想定外の過剰報酬。その真意は・・? 自分の心に巣喰っていた「世の中こんなもの」という青二才の舐 (な) めた考えを覆す教育的効果が確かにあった。▽私がテニスの個人指導を受けていた先生は、サンディエゴでテニス留学をしていた20歳前後の若い日本人男性だった。教え方は上手い。レッスンを続けたお陰で私の腕前も磨かれてきたが、ひとつ困ったことが。先生は “若者言葉” を臆面もなく使いまくるので、しばしば理解不能に陥ることだった。私がサービスエースを決めると「それ、ま? レベチハンパねぇ〜! つ〜か、マジえぐいてぇ! 無理ゲーっすね」・・ホメているのは分かるけれど。レッスンが終わると「とりま、次は5時集合ということで、おつありです!」・・先生はプロテニスプレーヤーになる夢を叶えたのだろうか? (SS)
|
 |
|
 |
▽「バカとブスこそ東大に行け」。現在放送中の人気ドラマ『ドラゴン桜』の主人公、桜木先生 (阿部寛) がよく口にする言葉。原作はコミックとのことで、元暴走族で弁護士でもある教師が、偏差値の低い子どもたちを東京大学合格に導くストーリー。「スポーツとか、音楽とか、芸術とかは才能も絡むが、勉強は違う。努力が努力した分だけ返ってくる。だからお前は、勉強を頑張ったらいいんじゃないのか」。その言葉は型破りだが、理にかなっている気もする。▽自分は商業高校を出て銀行に勤めた。でも、人生のギアをチェンジをするために大学に入り直し、教育実習にも参加した。お好み焼き屋で先生たちが歓迎会を開いてくれた。「こんなドラマを放送するから生徒が勘違いするんだ」「現場がどれほど大変か分かっていない」と、武田鉄矢の『3年B組金八先生』を横目で見ながら、先生たちが顔を真っ赤にして怒っていた。1970年代末から80年代にかけて中学校に吹き荒れた校内暴力の嵐はすさまじかった。▽ドラマと現実は違う。でも、生徒が理想とする先生は概して、同僚から鼻つまみ者扱いされそうな破天荒な先生が多い。学校での立場など顧みない熱血漢。そんな教師だからこそ、1人の人間として教壇に立ち、生徒と立ち向かう姿が “最高の先生” として記憶に刻まれるように思える。 (NS)
|
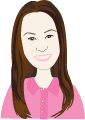 |
新型コロナウイルスのせいで、世の中がめちゃめちゃになっている。アメリカはワクチンのおかげで、少しずつ「普通の生活」に戻ってきているような気がするけど、完全にマスクなしの日常になるのは、もう少し時間がかかると思う。今から振り返ってみると、昨年3月からのロックダウンの時は、生活に必要不可欠な業種以外はいきなり全部クローズ! 毎日、家で仕事と近所で散歩ぐらいの「コロナ生活」を続けていた。ジムに通っていた私にはあまりにも運動量が少なかったため、オンラインエクササイズクラスを探していた。何と、フォローしていたジムの先生の何人かが オンラインクラス を始めた! 私はワクワクしながら オンラインクラス を取ることに。最初はラップトップの前で運動するのが慣れなくて、難しくて、右も左もなく混乱していた。でも、繰り返しているうちに段々と楽しくなってきた。今も、公園アウトドアとオンラインで同じ先生たちのクラスを受けている。この大変な1年間、精神的、肉体的にも、一緒に乗り越えてくれている先生たちに心から感謝! (S.C.C.N.)
|
 |
5月が始まった。今週の子供たちの学校は "Teacher and Staff Appreciation Week!" になっている。月曜日から木曜日まで、日替わりで "先生に感謝の気持ちを伝える" 催しが計画されている。月曜日は先生に賞状をあげる日、火曜日は先生にギフトを、水曜日はサンキューノートを贈る、木曜日は先生の好きな色を着る日。小学校らしいささやかなイベントだ。数年前に息子が学校に通い始めた時、ティーチャー アプリシエーション ウィークは、月曜日は花を、火曜日は手紙、水曜日はギフト.....というメニューだった。この「花」に困った覚えがある。結局、1年目は折り紙の花を息子に持たせ、2年目はフェルトを縫い合わせて花を作った。学校に着くと、高学年の子供たちが学校の周りに生えている草花を「先生に〜」って摘んでいたのが可愛かった。「あ、こんな感じでいいんだ〜」とも思った。アメリカの『先生に感謝の気持ち伝えよう週間』はとてもよい。私も、もっと気軽に先生方に感謝の気持ちを伝える機会があったらよかったのにと思った。(YA)
|
 |
△先日、日本に住む友達とテキストでおしゃべりしていたら「今週は子供たちの通う学校は家庭訪問ウィーク。コロナだから、玄関先だけで済ませるんだって」とのこと。家庭訪問!この言葉、すっかり忘れていた!アメリカの一般的な学校で、先生が生徒の家を訪れて親と面談する、という習慣はあるのだろうか。少なくとも、私たちの娘が通ってきた小学校、中学校では聞いたこともない。カンファレンスの時は、予約した時間に親が教室まで出向いて先生とお話しする、というスタイルにすっかり慣れてしまったので、先生がわざわざ生徒たちの家庭を訪れるということが信じ難い。思い出せば、家庭訪問の際、担任の先生が自分の家に来てくれるということが嬉しくて仕方なかったっけ。お茶菓子を食べながら、自分の親と話す先生はなんだか違う人のようにも見えた。先生たちも、生徒の家庭の様子を垣間見ることができて良いのだろうが、それにしても、結構大変な慣習だと思う。日本の学校の先生たち、お疲れ様です。△娘の通う中学校でも、今月は Teacher appreciation weekがある。このパンデミックで、オンライン授業実施など、先生たちも四苦八苦で頑張っている。先生方、お疲れ様です! (RN)
|
 |
|
 |
私は某大学の教育学部の附属中学、高校と同じ学校に6年間通った。この学校は私の入学時から、国立校では初の高校受験を廃止したり、英語の授業に LL (Language Laboratory) 教室を導入したりと、かなり革新的な学校であった。他の中学高校に比べると生徒数は遥かに少なかったが、その半数以上が将来の目標を「教師」と掲げているのに驚きを隠せなかった。まあ教育学部だから、将来は先生というのは頷 (うなず) けなくもないが、私は「絶対に先生にはならない」と決めていた。というのも、社会経験ゼロで大学卒業後に即先生となり、生徒の指導に当たる、という制度に疑問を持っていたからだ。教師たるものは学問だけを教えるのではなく、社会的経験から得られる知識なども含めて、子供たちを総合的に教育するというのが本来の姿という確固たる信念があった。社会的経験もなしに、昨日まで学生、今日から「あんたが大将」の先生。は? 故に先生にはならない、という持論が覆ったのはシンガポールで日本語教師として働いた経験から。指導対象は大人。私の人格や経験が彼らの成長に影響する訳もなく、日本語を教えることに集中すればいいというこの職は、実に見返りの多い仕事だということに気付かされたのだ。先生職に開眼した。以来、積極的にこの仕事に取り組んでいる。 (Belle)
|
 |
|
 |
中学生の頃、わたしにはお花とお茶の先生がいた。近所の幼なじみの家で、そのおがお寺なので、幼なじみのお母さんは “おくりさん“。和尚さんの奥さんのこと。だから、幼なじみのお母さんのことを先生じゃなくて、おくりさんって呼んでいた。お稽古に行くと、座敷に正座して、お花のお稽古。お花の後はお茶のお稽古。ここの先生がスゴいのは、これで終わりじゃないってこと。お寺だから、お稽古の座敷の周りはLの字に中庭に面してる廊下があって、なんと、そこの雑巾がけをするのが恒例。今思うとなんでわたしが、、?笑 棒が付いたモップじゃないよ。ブリキのバケツに水が入っていて、雑巾をカチカチに硬くしぼるタイプ 笑。寒い冬は指が、ちぎれる!それを、タッタッタッタって、一休さんのようになが〜い廊下を雑巾がけ。そんな時、ふっとおくりさんを横目で見ると、、あったかいお茶飲んで、さっきのお茶のお菓子食ってんじゃん!・・・さらに奥に目をやると、、ここの息子 (幼なじみ) は、、茶の間でリラックス? なんでわたしが雑巾がけで、坊主がコタツでテレビ? その後、おくりさんは師範種目を増やし、ご詠歌の先生となった。わたしが知ってる限り、さらに65歳ごろ、仏教短大に入学し、山道を車で通学してた 笑。こんなにバイタリティある先生、さすが昭和でしょ笑。 (りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
幼稚園の頃、先生が苦手だった。理由の一つは、給食を残さずに食べないと叱られた記憶があるから。ピーマンが苦手で、こっそり制服のポケットに入れてしまったのをおぼろげに覚えている。その後、ポケットから母が見つけたのか、自分で取り出したのか覚えていないが、「乾涸 (ひから) びたピーマン」の姿だけが写真のように記憶に残っている。母親になった今は、生徒の親として先生と接する機会が多くなった。最近、長女の成績に疑問があり、連絡を取ることがあった。一科目だけ成績がすごく悪かったのだが、長女が言うには、そんなに成績が下がった理由が分からないとのことだった。娘の勉強の様子はだいたい把握していたので、私もこれはないだろうと思い、思い切って先生に尋ねることにした。話をしたところ、先生も娘の普段のテストのスコアから考えても、何かおかしいと感じたらしく、再度成績を見直してくれた。その結果、テストのスコアを付け間違えていたことが判明した。娘を信じてくれて、私の説明を聞いてくれた先生に感謝。些細なことのようだが、ちょっとしたことが子どもにとってずっと記憶に残ることがある。私の 「乾涸びたピーマン」のように。娘の担任の先生も、きっと彼女の記憶に長く残るだろう。そして今、娘は、将来は学校の先生になりたいと言っている。 (SU) |
(2021年5月16日号に掲載)

 |
昨年の春、老齢の母が歩行中に転倒し、治療とリハビリのために入院を余儀なくされた。90歳を目前に負傷したので、寝たきり状態になることも覚悟していたが、幸いにも骨盤は折れておらず、4か月の入院期間を経て完治し、歩ける姿に戻った。療養中の母を元気づけようとした私は、病室で持て余している時間を楽しく過ごせるだろうと、母の日のプレゼントに音楽のCDを贈ることにした。その昔、母は村田英雄が好きだったので、往年の歌手の名前を挙げて希望を尋ねた。母の口をついて出てきたのは意外な歌手 (グループ) だった。それはSMAP!! えーっ! ファンだったのか!? 母のお気に入りSMAPの楽曲 BEST3:『がんばりましょう』 — 軽快なテンポで「どんな時も くじけずに がんばりましょう」と、老人を応援してくれているようで元気が出る。『らいおんハート』 — 家族愛が心に伝わって思わず涙が出る。『夜空ノムコウ』 — 「夜空のむこうには 明日がもう待っている」。素晴らしいあの世が開けているような気持になる。・・それぞれの歌に自分のコメントまで付けている。マイッタ。90歳を甘く見ていた。私はオンラインでベストアルバム 『SMAP 25YEARS』 を探し当て、母の日に届くように手配した。嵐よりもSMAPだそうだ。 (SS)
|
 |
|
 |
▽小学生の頃、母の日によく『肩たたき券』を贈った。福島から千葉に移り住み、裸一貫から父と八百屋を開いた母は、早朝から晩までよく働いていた。近くにスーパーがオープンすると、軽トラックで曳き売りの行商に出た。パンパンに凝った母の肩はなかなかほぐれず、手が痛くなった。省エネのため、有効期限付きの券を贈るようにした。「期限切れだけど、最強の肩たたきの注文入りました」と、元気で明るい母の声が今でも聞こえてくる。▽動画再生回数が130万回を超えて話題となった「全国一斉 母の日テスト」。2018年に西武そごうが母の日プロモーションの一環として企画したもので、「母」にまつわる100の問題をテスト形式で作成。動画内で、東大生がテストを受け、終了後に母親に電話で正解を聞くまでの様子が「感動する」と、注目を集めたとのこと。母の好きな食べ物は? 生年月日は? 趣味は? 初恋はいつ? 幼いころの夢は? 尊敬する人は? など、意外に知らない「母」のことが100問 (https://bit.ly/2RUm3wL)。今年も母の日がやってくる。天国の母とは、もう一緒に答え合わせはできないけれど、私には、いつも「お母さん」と呼んでいる義理の母がいる。旦那にも参加してもらい、スピーカーフォンで「母の日テスト」を楽しんでみたい。(NS)
|
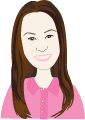 |
母が病気で亡くなって、もう5年以上経った。義理の母もFluで亡くなって、2年以上になった。二人のお母さんが天国に召され、子供もいない私には母の日とは無縁だけど、 世の中のお母さんはスゴいと最近常々思う! 女性しか体験できない、つらい妊婦生活&出産! そして出産後の大変な子育て。周りのママたちを見ていると、生活の優先順位、食事のこと、買い物など、、、何もかも自分のことを考えるよりも、子供のことを優先にしている! それだけでなく、子供の通学のアレンジ、放課後のサークル活動、Day Trip、誕生日会、発表会など、数え切れないイベントに対応して、協力し、用意し、参加し、片付け、、、子供をドロップして、ピックアップして、毎日に何回も家とを往復しないといけない場合もある。子供の世話以外は、仕事をしたり、家事をしたり、、、本当に大変だなぁ〜と心から尊敬! 母の日がもうすぐやってくる。よく働く世の中のお母さんたちにサルート! (S.C.C.N.)
|
 |
23歳で私を産んだ母は、私が小学生のころはまだ30代前半だった。参観日に母が来ると 「お母さん、若い〜、綺麗〜!」とクラスメイトに言われるのが自慢だった。父は家のことは母に任せっぱなしだった。母は仕事と家事を両立させながら、私たち姉妹をしっかり育ててくれた。毎朝、洗濯しながら、朝食を用意し、私たちを学校へ送り出した後、掃除機をかけ、ペットたちとたくさんの観葉植物の世話をしてから、会社へ行っていた。夕方に帰宅すると、夕ご飯の用意。私たちに食べさせ、お風呂に入れて寝かせる。お風呂の準備と洗濯物の取り込み&片付けは私の仕事。子供の学校が半日の土曜日には、お昼ご飯を用意しに会社から戻ってきて、また出社。休日の日曜日は、朝から私たちを起こして、みんなで家の掃除。毎日忙しく働く母を見て育った。母はすごい。大人になってから、やっと母の有り難味が分かった。まだまだ若いお母さん、これからは、自分のためだけに時間を使って、毎日を楽しく、健康に過ごしてください。 (YA)
|
 |
母の思い出いろいろ。手先が器用で、編み物や裁縫仕事が得意だった。ピアノの発表会に着る素敵なドレスも作ってくれた。真っ白な布で縫い上げ、それを自分で素敵な藍色に染色してくれた。宝物だったはずなのに、今はどこにあるのか不明 (涙)。大好きなリカちゃん人形の服の数々も毛糸で編んでくれたっけ。味噌、梅干し、らっきょう、天然酵母のパン、ヨーグルト、何から何まで、手作りできるものはなんでも作っていた。ピアノを教えたり、父の幼児教室を手伝っていたりしたこともあって、多忙な母だった。よその子にも自分の子供のように、悪いことをするとしっかり叱るので、生徒さんからは恐れられていたようだが、面倒見が良く、困っている人を放っておけない性質で、子供や親たちからも頼られることが多かった。疑い深い性格 (笑) で、風評、迷信、デマなどにはそう簡単には引っかからない人だった。しっかり者ではあったけれど、おっちょこちょいなところも結構あった。早くに自分の母を病気で亡くしていたので、私たち子供に対しての愛情のかけ方は人一倍強かったように思う。思春期の頃はよく衝突したりもしたけれど、いつも私たち子供のことを一番に考えてくれて、世界一の母だったなと思う。 (RN)
|
 |
|
 |
52歳で急逝した私の母は、昔の、どの母親もそうであったかのように、働き者だった。かまどで、薪でご飯を炊き (どれほどの手間か想像もつかない)、洗濯板で洗濯をし (湯沸し器などない時代だから、冬は水の冷たさで手は荒れ放題)、掃き掃除と拭き掃除。その間には飼っていた鶏やウサギの餌やり。そして毎朝、父の靴をピカピカに磨き…。家事が一段落すると、歩いて市場に食事の買い物に。その合間に、子供たちの下着も含めた洋裁仕事。夕食後は、またまた薪でお風呂を焚いたり、せっせと編み物をしたり、あるいはセーターの毛糸をほどいて湯通ししたり…。これが、今と同じ24時間しか持たない主婦の毎日か? ホッとする時間などあったのだろうか、と思うほどだ。それに比べ、私の生活の体たらくぶりは、一体何なんだ? 母になれなかった、ならなかった私は、母の日を祝ってもらうことなど一生無いが、この親不幸モノの娘は、母と暮らした18年の中で、母の日だからと、母に感謝の意を伝えたことがあっただろうか。それどころか、私の誕生日が母の日と重なる年には、娘は母の日はそっちのけで、母が私の誕生日祝いをしてくれたりしたものだ。とっくの昔に逝ってしまった母に、せめてもの罪滅ぼし。母の写真にカーネーションを飾る。そして言う、「お母ちゃん、親不孝でごめんね」。 (Belle)
|
 |
|
 |
親不孝だわ、わたし。母の日の記憶が、ない (ヒドイ!)。小学校でカーネーション配られて、あげた、かな?(記憶に、、うっすらあるような・・・) でも、小学校でカーネーションを全校生徒に配るバジェットがあったのか、など現実的なことを考えてしまう 笑。1回くらい米国からお花を頼んで宅配してもらったっけ (記憶がうっすら 笑)、なぜプレゼントをしないかというと、、お母さんからの、わたしが大人になってからの言いつけで、モノをくれなくてよいと。そのお金があれば、恵まれない子たちに寄付しなさいって。なーーんていい母親じゃなーい?一方、自称似非 (えせ) メキシコ人のわたしは、メキシコの母の日の習慣が好き。米国や日本の母の日とは違って、変動日ではなく固定日。日曜日も関係なく毎年5月10日。今年なんかは月曜日よ。でも、関係ないさ、あのお国は 笑。お母ちゃんがとっても大切な国なので、盛大にお祝いすること間違いなし 笑。スゴイのは、自分のお母ちゃんはもちろん、他人のお母ちゃんもお祝いすること。世界の “母“ 全てを祝福するのよ。子供と旦那がお母さんにありがとうだけじゃなくて、女性同士がハグしてんの 笑。その日、よーく観察してみて。やたらおばちゃん同士がチューしてハグしてるから 笑。(笑っちゃいけないけど、笑えるから!笑) (ゴメンね!笑)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
今回のお題で、私は自分の母のことを書くつもりだった。締切日が過ぎ、ヤバいぞと焦っていた昨晩、旦那のお母さんが亡くなった。私の旦那は日本人母とアメリカ人父のハーフだ。5歳の時に両親が離婚し、父親と一緒に人生を過ごした。彼の母は、その後日本で再婚したが、子供は作らず、新しい旦那さんと共にアメリカと日本、離れていても精一杯、息子 (私の旦那) を愛してくれた。私も2人の息子を持つ母。海を越えて母親の愛情をアメリカにいる息子に届けるのは、涙することが多かったと想像する。旦那の母親は30年前に脳梗塞から半身不随になり、心臓にカテーテルを入れる手術もし、それでも84歳まで頑張った。数年に1回、日本に帰ってくる息子のために頑張っていたんだろう。このコロナ状況で、旦那を日本に行かせてあげたかったが難しい。改めて自分の周りにいる人たちに、愛情と感謝を日々伝えることを忘れてはいけないと感じた。母の日には、旦那のお母さんと義父と私たちで写っている写真に、花をそなえよう。(IE) |
(2021年5月1日号に掲載)

 |
20代初めの頃、普通車運転免許証を取得する「合宿コース」に申し込んだ。静岡県の小都市にある自動車学校で同室になったのは、私を含めて5名。考えてみれば、目的が同じとはいえ、年齢も職業も生活環境も異なる男たちが偶然にルームメイトとなり、2週間以上も寝起きを共にする機会など、生涯でそうあるものじゃない。私は単独行動を好む人間なので、合宿所での夕食後、街の中心部まで散歩するのを日課としていた。喫茶店で寛いだ後、門限には帰宿していたが、毎晩私が何をしているのか、ルームメイトから怪しまれた。夜遊びなどしていません。陽気な40代の自営業者は運動神経が鈍すぎると悩んでいた。「どうしても、方向指示器を逆に出しちゃうんだよ。教官から 『ふざけてんのか!』 と雷を落とされる」 と笑いながら話す。普通、右折の時は右に出すだろ? 運動神経の話じゃないだろ! 問題児は18歳のトビ職人。運転技術はピカイチで誰よりも上手い。路上教習でスピードを出しすぎて教官から怒鳴られまくっていた。その彼がテクニックに溺れたのか、教習所内で交通事故を起こした! 同乗していた教官が負傷して病院に搬送される。地元のTVニュースは「自動車学校内の事故で救急車が出動したのは、前代未聞の珍事」と報じた。(SS)
|
 |
|
 |
▽明治生まれの祖母が、私の最初のルームメイトだった。子どもの頃から実家を出るまで、ずっと一緒の部屋で暮らしていた。「知らざあ言って聞かせやしょう 浜の真砂と五右衛門が〜」「あんたの父母はモダンな人で、結婚前にふたりで旅館に〜」「私は腹膜炎で一度死んでね、でも、また生き返ったのさ」など、毎晩、寝る前に面白い話を披露してくれた。テストに朝寝坊したことを祖母に八つ当たりしたり、ひとりの空間が欲しくて作ったダンボールの城壁の小窓から、祖母が特製のおはぎを差し入れてくれたり、落ち込んでいると「さすけね〜」と慰めてくれた。人生の機微を教えてくれたルームメイトだった。▽ワシントン州の学生寮で、クリスという金髪のルームメイトと暮らしたことがある。バドワイザーとビザが大好きな法律専攻の学生で、レッドツェッペリンのロックを年中流していた。母子家庭対象の返済不要の奨学金を得て頑張っていた。スニーカーを乾燥機で乾かしたり、バイトの前にリステリンで酒の匂いを消し、好きな時におならを連発。私が持っていたウォークマンに興奮して、自分のモノのように学生寮の皆に見せびらかしていた。今は弁護士として活躍している。「運命は自分で変える」的な、たくましい精神を彼女に教えてもらった。(NS)
|
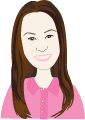 |
台湾の親元から離れ、日本へ留学中、小さな6畳のアパートを借りて一人暮らしをしていた。小さな台所、小さな浴室、小さな洗濯機、とりあえず生活には必要な “コンパクト設備” が全部揃っていた(全部サイズが小さい^-^)。住み始めて1年後、すぐ下の妹も日本に留学した。私の小さなアパートで二人の共同生活がスタート! 私は大学、妹は日本語学校。生活費だけは自分たちの力で頑張ると両親に言い張ったので、学校以外の時間は二人ともバイトしていた。妹は日本語学校から歩いて行ける喫茶店、私は大学から電車に乗って30分ほどの場所にある喫茶店でウェイトレスをしていた。妹とは休日になると原宿や新宿へ行ったり、食べたり、遊んだりしていた。でも妹は、やはり台湾の生活が自分に合っていると思い直して、1年だけで台湾に帰国。また一人暮らしになってしまい、私はとても寂しくなった! いつでも目いっぱい明るかった妹は、私にとって最初のルームメイト。そして可愛くて最高のルームメイトだった。 (S.C.C.N.)
|
 |
ルームメイトと部屋をシェアしたことがない。ホームステイ中にはハウスメイトが何人かいたが、部屋は別々だった。ハウスメイトの子たちは短期留学のヨーロッパからの留学生が多かった。一緒の家にいると自然に仲良くなるので、休日は大体一緒に過ごしていた。ハウスメイトの子がイタリア人だった時は、イタリア人の友人グループに入れてもらい (私だけイタリア語が解らない)、スイス人の時はスイス人のグループと遊んでいた。みんな気さくで良い子たちだった。ホストファミリーの家を出てから、ボーイフレンドとアパートをシェア (というか、相手が勝手に転がり込んできた) していたことはある。彼はゲームばかりして「吸って」「飲んで」夜中までお隣さんと騒いでいたし、散らかされるしで、あまり良い思い出は残っていない。ひとり暮らしの間は猫がルームメイトだった。散らかされても猫だと許せる (笑)。週末は一緒にごろごろ過ごして、平日は私が家に帰る頃にドアの前で待っていてくれた。可愛かったな〜。 (YA)
|
 |
私が人生で初めてルームメイトと暮らしたのは、21歳の時。サンディエゴの大学に1年間交換留学した際、キャンパス内の寮の2人部屋でアメリカ人女子と共同生活をした。縦長の狭い部屋にベッド、机、それぞれの荷物を入れる小さなクローゼットが2つずつ。小さい冷蔵庫と電子レンジは共用。慣れない英語や文化の中、英語しか喋れない見ず知らずの超アメリカ人な若者との生活は、面白かったけれど、いろいろと大変なこともあった。私はそれまで、自分のことを綺麗好きとか整理魔とか思ったこともなかったけれど、彼女と同じ部屋で暮らすようになってから、こんなに部屋を散らかして生活する人がいるものかとびっくりした。脱いだ服や使ったタオルがベッドの上のみならず、床にも散らかり、彼女の机の上は教科書やノートブック、食べかけのスナックの袋やら、その他雑多なもので山盛り状態。片付けたくなる衝動を抑えるのが一番難しかった。寮の他の部屋に住むアメリカやその他各国の学生が私たちの部屋に来ると、私のルームメイトのスペースの乱雑ぶりに閉口していて、私だけが気になっている訳じゃないと分かり、ホッとしたのを覚えている (笑)。 (RN)
|
 |
|
 |
私はこの国に来て人生初の主婦なるものを体験。子供なし。来たばかりの頃は友達もそうそういる訳もない。日々の主な会話相手は、必要以外はほとんどしゃべらない旦那、というつまらない生活をしていた。こんな生活を2年送ったら、飽きた、飽きた。何かをせねば、と始めたのが、自宅を使っての今で言う Airbnb (ま、対象は日本人限定だったが)。それが世に出てくる、う〜んと前のことだ。以来、フルタイムではないが、お客さんが我が家に滞在してくださる時は、まさにルームメイトという感覚。「全く知らない人と、よく一緒に暮らせるわね。私はダメだわ」と言う人もいたが、元来、私は人好き、世話好きという性格も相まって、このパートタイムのルームメイト生活が気に入っていた。彼らは、それまでのつまらなかった私の生活を大いに生き生きとさせてくれ、おまけにお金まで払ってくださる。宿を始めて3年後の離婚でその家を離れるにあたり、一旦、この仕事は中断したが半年後に再開。パートタイムのルームメイト生活を合計20年も楽しませてもらった。彼らの滞在中は夕食を囲みながら大いに飲み、大いに語り、中には1年に4回も来る人、毎年訪れるカップル等もいて、賑わせてくださった。まさしく パートタイム ルーメイト、万々歳!!だった。(Belle)
|
 |
|
 |
いろんな人がいるよねー。自分のルームメイトもそうだけど、人の家のルームメイト (笑)。パンデミック前は、ロスの友達のところに遊びに行くと、どこに泊まるか分からなかった、、。それは、、、彼に定まった家がなく、友達の家を転々としていたから (笑)。ストリートミュージシャンで、待ち合わせ場所はファーマーズマーケットのXX店の前、とか、演奏の音を聞きながら探す、とか (笑)。一日中外にいる間に 「今日どこに泊まるの?」と聞いていても、答えはその時になるまで謎だった。だから、かもだけど、わたしの旅行はいつもバックパック1つでどこでも行けるよう超身軽。ある時から、いつも泊まる家 (というか居候?) が決まった (笑)。そこの家では彼の楽団も練習をしていたので、いつも大勢が家にいて、誰が住んでいて、誰がルームメイトで、誰が遊びに来ているのか区別がつかない (笑)。それでも寝場所の確保だけは、いつもちゃんと収まった (笑)。いろんなとこ泊まったな、工事中の倉庫とか (笑)。どこに泊まるか分からん、ていうのが、トラさんっぽくて、オツじゃな〜い?(じゃないって?笑) そもそも、住所の定まっていない友達を訪ねていく?(やっぱり、わたしってフウテンのトラさん!笑) (結局、あの家のルームメイトって、、誰? 笑)。 (りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
アメリカに来て1年ほど過ぎた頃、なかなか上達しない英会話をなんとかしたいと思い、台湾人の女の子と1年ほどルームシェアをしたことがある。初めて他人と暮らしてみて、驚いたことがいくつかあった。まずは部屋の整理整頓。私は細かいところにはあまり気にしないが、基本的にソファーや床に靴下や洋服などが転がっているようなことは、昔も今もない (今は子どもたちの服を拾って歩いているが)。しかし、彼女はすごかった。部屋は基本グチャグチャ。あちこちに脱ぎ捨てた服が散乱しており、カーペットには付けまつ毛がいくつも落ちており、何度、毛虫と間違えて心臓が止まりそうになったことか。そして料理。とても衝撃的だった。ある日のこと、彼女が白飯の上にカレーのルーを置いて、電子レンジに入れようとしていた。何をしようとしているのかと思い、聞いてみたら、カレーを食べるのだと言う。彼女はカレーのルーをご飯に乗せてチンすれば、カレーが食べられると思っていたのだ。それを見た時、私は『Back to the Future 2』で、主人公のマーティが未来の自分の家に行った際に、彼の母親が手のひらサイズの小さなピザを機械に入れると、大きなピザが出来上がってきたシーンを思い出した。きっと彼女は、どこか遠い未来から来ていたのかもしれない。(SU) |
(2021年4月16日号に掲載)