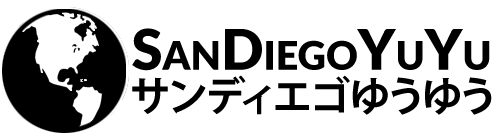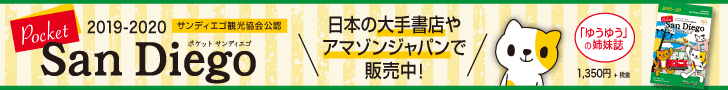寒季の到来とともにパンデミック第3波が米国に襲来。Covid-19感染拡大のピークが見えず、不安の中で2020年が過ぎていく。新型コロナ情報を追い続けて8か月半。インディアナ州のR病院が発表したマスク着用と免疫力増進に関する論文の内容に驚いた。キーワードは Cross-Protective Immunity = 交差免疫。隔離していない1人の軽症患者から病院スタッフへの感染度を調べた実験報告。全員がマスクを使用した結果、感染しても92%以上が無症状で済んだばかりか、誰もが新型コロナへの免疫力を獲得していた。手短に言うと、マスクはウイルスを完全遮断できないが、むしろ微量感染を繰り返すことで、免疫細胞が抗体を作り続けて (交差免疫) 重症化を防ぐらしい。これが事実なら (科学的には未証明)、マスクには自然のワクチンと言うべき素晴らしい効能がある。米国と比べて日本の感染状況が緩和されているのは国民のマスク依存度の差? “強いアメリカ” を印象づけるためにマスク着用を軽視したのは現政権の大罪? 市民にワクチンが行きわたるのは4月頃? 1人当たりの2次感染者数を1未満に抑える投与効果があれば、ウイルス制圧の数理モデル (1-p) x RO<1 に合致して収束へ向かう。2020年回顧はその日までお預け。 (SS)
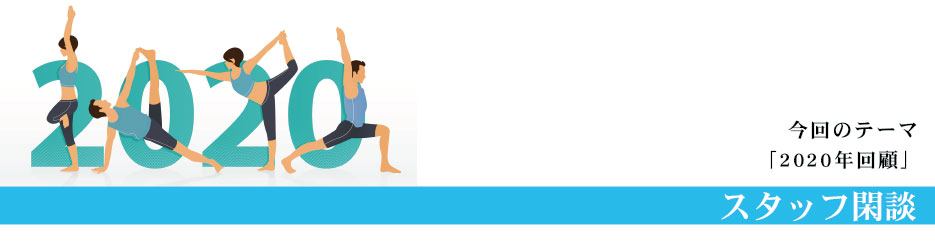
 |
|
 |
|
 |
▽地球を総なめしたCovid-19。2020年は世界中の人々にとって、大変な年になってしまった。リタイア後、初めての船旅に参加した友人夫妻。集団感染が起きたクルーズ船から2月中旬、無事に下船したとのLINEが届いて安心したのもつかの間、3月中旬にWHOが 「パンデミック」を表明。私たちの暮らしが一変した。▽2020年の流行語大賞に 「3密」 が選ばれた。「アベノマスク」 「Go Toキャンペーン」「アマビエ」「オンライン○○」がトップ10に選ばれるなど、新型コロナウイルスの影響を反映した言葉が並んだ。▽ウイルスに詳しい知人が教えてくれた。「ウイルスとの戦いはハッカーとの戦いのようなもの。ウイルスはあらゆる手段を使ってパスワードを見つけ、人間の細胞に侵入しようとする。猛烈な勢いで変異をつくり出して侵入してくる。人間もまた、カギ穴をふさいで侵入させないようにする。人類の歴史はウイルスとの戦いの歴史なんだ」。▽アメリカでは、早ければ今年の12月11日からワクチンが提供される見通しとのこと。明けない夜はない。やまない雨もない。過ぎ去らない嵐もない。嵐が過ぎ去った後は、きっと、澄み切った空気と素晴らしい景色が広がっている。私たちは、過去に繰り返された感染症の大流行から生き残った『幸運な先祖』の子孫なのだから。 (NS)
|
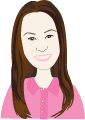 |
それは "新型コロナウイルス" でしょう! 年明けからずーーーっとその影響でアメリカを含む全世界の経済がダウン。死亡者数がどんどん増え、どこの国でも今まで経験したことがない戦いの1年となった! このような生活になるなんて、今まで想像もしていなかった。このパンデミックの期間に仕事を無くした人が沢山いて、数多くのお店やビジネスもクローズ。非常に大変な状況になっている。しかし、こんな苦境の中でも頑張って生きていかなければと思い、「良いこと」 をここで発表。《その1》マスクをするので、化粧をしなくてOK! 化粧品を買わなくてOK! 《その2》 家にいる時間が長いので、ガゾリンを入れる回数がかなり減った! いろいろな料理ができるようになった! 庭の雑草もきれいに取れた! 倉庫の整理も多少できた! 《その3》 ジムが閉鎖されて Virtual エクスサイズになった。クラスが多いので、運動時間が以前と比べてかなり増えた! 前向きに考えないと前に進まない。この大変な状況から1日でも早く抜けられるように、楽観的に考えていきたい!! (S.C.C.N.)
|
 |
今年ほど大変な1年は今までになかった。年が明けたと思ったら、すぐに新型コロナウイルスが広がり、皆、リモートワーク、オンライン授業に切り替わった。外出禁止令も出て、フリーウェイもローカル道も車通りがガラガラ。散歩をしている人だけ急に増えた。食料品、日用品を買いに行くと、店に入るまで列に並び、チェックアウトでまた列に並ぶ。トイレットペーパー、消毒液類、米、パスタ、小麦粉類が売り切れている。学校はリモート授業を子供も親も先生方も手探りで進め、課題は親が大変だった。2020年の春と初夏の記憶はこんな感じだ。夏休みになり、マスク、度々の消毒、手洗いにも慣れ、外遊びは公園でバイクライドかスクーターライドのみの状況にも慣れた。そして新学期もオンライン授業で始まった。毎朝のズームミーティング、リモート授業もすっかり当たり前になった。でも、そろそろ学校に通えるようになってほしい。コロナも少し落ち着いたかと思いきや、第3波襲来だそうだ。来年もオンライン授業でスタートらしい。。。。。(YA)
|
 |
2020年は新型コロナウィルスに振り回され、今まで経験したことのないことを次々に経験した年だった。まずは、ミドルスクールに通う娘が3月中旬から学校に行かず、ずっと家にいる。最初は試行錯誤だったオンライン授業も、今ではすっかり馴染んでいる。先日は、Zoomを使った友達のお誕生日会に出席。プレゼントはオンラインで買って、その子のお家に届けてもらった。インターネットがなかったらどうなっていたんだろう、娘のコロナ生活…。スクリーンタイムは急上昇したが、こうやって友達とも繋がっていられるし、我が家では良しとしている。食料品をオンラインで注文して届けてもらうというのも初めてやり始めた。日本じゃないのに、行き交う人が皆マスク姿という光景にもすっかり慣れてしまった。人との接触が限りなくゼロに近い生活を送っているおかげか、今のところ、家族の誰もコロナだけでなく、その他の病原菌をもらってきていないようだ。体調も良い。でも油断は禁物。感染状況が改善し、安定するまで隔離生活を続けて乗り切りたい。 (RN)
|
 |
|
 |
コロナよ、コロナよ、ああ、コロナ。中国の春節後あたりから世界中で猛威を振るった (いや振るっている) 新型コロナウイルス感染症。この新コロ (ショートカットが大好きな日本での報道の際、誰も短くしなかったのを、私があえて短くする) のせいで、世界中の人たちがそれまでの生活スタイルを変えることを余儀なくされただけでなく、人生まで狂わされた人も少なからず。そんな中での私の2020年は…。私の日常の中での小さな楽しみといえば、ランチやディナーを共にしながらの友達とのおしゃべり、月1〜2回の図書館のコンサート、映画館にビールとサンドイッチを勝手に持参する「映画館ピクニック」、そしてハッピーアワー。これら全てが見事に奪われた。残った日常は何の変哲もない、僅かな仕事とスーパー通いと自宅時間 (まあ、Myハッピーアワーは続けられているが)。非日常では、5月のペルーとチリでの雲丹 (ウニ) 三昧計画、8月のイタリア (シエナ、チンクエテッレ、サルディーニア、そしてシシリーのカルタジローネなど)、マルタ行きを涙を呑んでキャンセル。まったくぅ! 残り僅かの人生にあって、その1年が無くなるということは私にとっては超一大事。「新コロ、新コロ、新コロよ、わが大事な老春を返してくれ〜」と大声で叫びたい年末である。 (Belle)
|
 |
|
 |
今年1月にニッポンに帰って本当によかったぁ!って、いつもはそんなに感じないことを、今になって実感したわ。思い出せば、成田に着いたとき、なーんで小学校のプールに入る前みたいな、靴底を消毒するマットが敷いてあるの?と思ったし、中国の感染ニュースが毎日のように流れてたり、あのときは他人事だったわ。そしたら、ヨーロッパのお友達たちが外出禁止令で動けなくなり、ニューヨークの友達も家からリモートワークに切り替え。あれよあれよといううちに、スーパーのトイレットペーパー売り切れ。サンディエゴのレストラン内で食事禁止。散歩時間が増えた増えた (笑)。サンディエゴ動物園の駐車場に車が1台もなかった光景も見た。それで気付いたら、公園のピクニック人口が増えていた。しかも豪華な感じの。テント張って、テーブルクロス付きテーブル置いて、オシャレににお花飾ったり。普段は公園としては見ていない道路脇の芝生エリアでも水着で日光浴してたり (日本じゃ考えられん 笑)。でも、リトルイタリーの夏は「密」だったでしょ (笑)。絶対6フィート空けて歩いてないし。街で一番様子が変わったのは、道路に建った仮設レストランのエクステンション (小屋?)。あれ、どう見てもビアガーデンでしょ 笑! 歩いてるだけでウキウキー! (今年、一番嬉しかったのはコレ?! 笑)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
何と言っても2020年は憎き「COVID-19」の年だった。米ジョンズ ホプキンス大の集計によると、現在のところ、世界全体の新型コロナウイルス感染者が6000万人超、死亡者は150万人とあるが、毎日目にしているこれらの数字にも何も感じなくなってきてしまった。こうしている間にも、感染者や死亡者が増えているのだろう。幸いこれまでに自分も含めて、周りにも感染者がいないせいか、あまり実感もなくこれまで過ごしてきた。私はもともとそんなに出歩くタイプでもないので、家に籠 (こも) っていること自体はそんなに苦ではないが、学校にも行けず、先生や友達にも会えない子供たちは本当に可哀想だと思う。学区からは早くても2月から少しずつ学校での授業を始めたいと連絡が来たが、最近の状況を知る限り、それも難しいでしょう。とにかく、今年は「我慢の年」であったが、来年は少しでも新型コロナが収束に向かい、元の生活に戻っていけることを願う。 (SU) |
(2020年12月16日号に掲載)

 |
語学留学生として米国生活を始めた1982年。当時は貿易摩擦でジャパンバッシングの叫びが喧 (かまびす) しかった。時代背景と相まって、ワシントン州東部のS市は白人が9割を占め、隣り町には白人至上主義団体の本部があった。日本人の存在が珍しいのか、店頭で顧客サービスを拒否されたり、何処からかリンゴをぶつけられたりもした。真珠湾攻撃の日 (12/7) に酔っ払い集団に行く手を阻まれながら難を逃れたことも。語弊があるかもしれないが、私はそんな体験を「新鮮」に感じていた。むしろ白人の本質を知りたかった。S市に暮らす私の大叔父 (great-uncle) からは、収容所体験として「白人は最後に裏切る」と聞かされた。私はこれらの出来事をエッセイにしてクラスに提出したところ、教員ほぼ全員がよそよそしくなった。ただ一人、20代の女性教師 Jさんから驚くべきアドバイスを受ける。「アメリカ市民になるのよ。そこから社会を変えるの」と、真顔で具体的なプロセスを私に細かく説明するのだ。アメリカ的な pragmatism の精神に触れた瞬間。冬の夕刻、大人数の少年少女聖歌隊が私を囲んで「あなたに神のご加護があるように」と賛美歌を合唱してくれた。子供たちの歌声を聞きながら、私は灰色の空を仰ぎ見て、落ちてくる綿雪の冷たさを感じつつ「これもアメリカか」としみじみ思った。在米1年目の冬の記憶。(SS)
|
 |
|
 |
▽故郷の福島県会津柳津は日本有数の豪雪地帯で、梁 (はり) や柱が黒光りする頑強な我が家には、煙にいぶされた大きい囲炉裏があった。祖母が作ってくれる味噌田楽を囲炉裏の前でほおばりながら、茅葺き屋根の空気穴からキラキラと雪が舞い降りてくるのを眺めるのが好きだった。雪はパチパチと燃える炉の上で一瞬で溶けてなくなった。「紅炉上一点雪 (こうろじょう いってんのゆき) だべ。大人になったら分かる」と、祖母が難しい話を教えてくれた。人間の命はもちろん、 この世に存在するすべてのものは、炉の上の雪のように現れて消えていく。一瞬でなくなる「はかない存在」だ。でも、だからこそ尊い。今、この瞬間、そして、今日という日を丁寧に生きなさい。そうして、明日という日をきちんと迎えなさい。還暦をすぎてようやく、祖母の話が少し分かってきたような気がする。▽雪国の粘り強さは「雪かき・雪下ろし」に由来するような気がする。千葉に移り住んだ我が家では、新天地の快適な気候を「千葉ボケ」と称して揶揄 (やゆ) していた。サンディエゴにも冬はある。でも、最も寒い1月の平均気温は14℃。会津の人にも千葉の人にも申し訳ないような冬だ。朝夕少し冷え込むようになると、すぐに暖房を使い始めるが、お気楽な「カリフォルニアボケ」にならないよう気をつけたいと思う。 (NS)
|
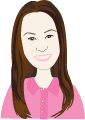 |
短大生のとき、家族旅行で母国の台湾から日本の大阪と京都へ行った。私と二人の妹にとって初めての海外旅行だったので、みんなワクワクしていた。冬の日本はめちゃめちゃ寒いと聞いていたので、暖かい格好で台湾から出発。若かったせいかも知れないが、そんなには寒く感じなかった。当時、日本語を勉強していた私は、台湾で日本語を教えてもらっていた先生から 「大阪の友人に本を届けてくれないか?」 と頼まれた。「もちろんです」と先生に告げた。家族でホテルにチェックイン後、両親から許可をもらい、二人の妹を連れて、梅田駅から目的の住所へ向かった。迷子になると困るから、三人で行き方と道をメモして、いざ “大阪探検” へ! めちゃくちゃな日本語で人に尋ねながら、無事に本を届けた。ホテルへ戻る途中、なんと雪が降ってきた! 初めて雪を見て、雪に触った私たちはとても興奮していた。通りかかった日本人の目を気にせず、ギャーギャー笑って、姉妹三人で楽しく雪遊びをした。あれから35年以上も経ったが、あの日のことは一生忘れられない! (S.C.C.N.)
|
 |
私の冬の記憶は、炬燵 (こたつ) にホットカーペット、みかんに猫。多分、どこの日本の家にもあるであろうこたつは実家では和室に置いてあった。テレビのある居間にはホットカーペットが敷いてあった。暖かいホットカーペットも好きだったが、やはり冬はこたつが一番。私も妹も、普段は和室をあまり使わないのだが、こたつが置かれると、自分たちの部屋から、小説、雑誌、漫画本を持ってきて、そこで寛いでいた。こたつぶとんの上には、こたつ板、こたつ板の上にはお菓子とみかん。傍らには猫が寝そべる。寒い日の休日にこたつでぬくぬくと本を読み、眠くなったら寝ころんで座布団を二つ折りにして枕にし、そのまま昼寝して、起きると夕方が近い。1日を無駄に過ごしてしまったなぁと、ちょっと反省する。こんな記憶が懐かしい。それほど寒くないサンディエゴでは必要ないが、もし、家にこたつがあったらどうだろう。。。こたつに入ったら全く動かない夫と息子に、私と娘が文句を言っている様子が眼に浮かぶ。やはり、こたつ購入はやめておこう。 (YA)
|
 |
北関東に実家がある。冬は東北地方などに比べると積雪量は大したことないが、それゆえに、たまに雪が降ると大変だった。すぐに交通機関が乱れてしまう。東京都内に会社勤めをしていた時、雪が降ると、通勤が命がけに近かった。まず、駅にたどり着くまでが至難の技。待てど暮らせど、バスが来ない、来ない、来ない・・・。仕方なく、父に車を出してもらって駅まで送ってもらうのだが、チェーンを付けても凍った雪道は滑る! 途中、田んぼに落っこちた車や溝にはまってしまった車が数台。やっと電車に乗っても、途中で何度も止まって、なかなか目的の駅に着かない。やっとの思いで出社しても、帰りがまた憂鬱。夜はもっとひどくなるのが分かっているから。電車は、ひどい時は自分の駅のかなり前の駅でストップしてしまい、そこからタクシーで帰らざるを得ないこともあった。タクシー乗り場は長蛇の列。凍える雪景色の夜更けに、いつタクシーに乗れるか分からずに待つ不安。思い返せば懐かしいけど、もう二度と経験したくない冬の記憶。 (RN)
|
 |
|
 |
冬といえば雪。雪といえばスキー、という訳で、私の冬の記憶は、スキーに直結している。高校時代、鳥取県の大山でのスキーが高校の行事にあったが、私はそれをキャンセルして、一人夜行列車で東京へ。初代ジャニーズのミュージカル鑑賞に出かけ、人生初のスキー経験を逃した。次に訪れたスキーの機会は大学時代、友達の誘い。スキー道具を揃え、夜行バスで信州、越後へ。生まれて初めて着るスキー服に胸を躍らせた。が、宿泊先のロッジの余りにもの汚さに耐え切れず、初日はスキーよりも掃除を買って出た。皆がスキーを楽しんでいる間に、一人黙々と掃除をしていたら…あろうことか、スキーパンツがストーブに当たり、お尻の部分に穴が…。替えがあるはずもなく、結果、ロッジ番をするだけのスキーツアーとなった。三度目の悲劇は、舞台が変わってスイス。言わずと知れたスキーの本場である。姉がチューリッヒにいたことで、長年勤めた出版社を辞めて訪れた際、姉家族が出かけるスキー場について行った。見たことないような広〜いゲレンデ。今度こそ初のスキー体験が、スキー人間憧れの場、スイスである。しかし! その美しいゲレンデで転げまくっているのは、周りを見渡せば私一人!!!! ああ、I don't likeスキー、But WE スキー (Whisky) (^_^)。 (Belle)
|
 |
|
 |
寒いのは苦手だから、冬に旅行するのはイヤなんだけど、実家への帰省は真冬の12月末〜1月の、どストライクゾーン (笑)。家にこもってればいいのに、と思うでしょ。うちは築50年の風通しのきく隙間風だらけの日本家屋。ネコのいる縁側が唯一あったかいので (昼限定)、そこにじっとしているけど、家のどこにいても基本、吐く息が白い!(笑)。クリスマスケーキやお刺身が「冷蔵庫に入らんよ」とお母さんに言うと「大丈夫、この部屋が一番寒いんだわ」(笑) と、応接間の床に置きっぱなしなのは、お決まりの光景 (笑)。だから、どうせ寒いなら、外も寒いけど、旅行に出かけたの。南国パラダイス、石垣島〜!! 名古屋と大違い! ヒートテック不要、カーデガンでおっけ〜! でも、なんと天気は雨・・・冬の雨って、さいあくの事態! と思ったけど、恐るべし石垣島 (笑)、寒く、、ない! (笑!) 宿で貸してくれる自転車を乗り回して、具志堅さんの親戚のマグロ屋へ行ったり、イノシシ刺し探しに行ったり、千ベロ (千円でベロベロになるの意 笑) 飲み街に行ったり、雨が、気にならない (笑)。すごい!石垣マジック!笑!が、同行したH部長に後で聞いたら、寒さが気にならなかったワケは、南国だからというより、泡盛でベロベロだったから、らしい (笑)。冬は千ベロで乗り越えよう! (は?笑)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
▽『私のサンタクロース編』:日本ではサンタクロースは枕元にプレゼントを置いていく。小学4年の私、イブの夜に就寝中、何かの音で目が覚めた。「あ、サンタが来た!」と思って薄目を開けると、そこにはとても見慣れた顔が…。いけないモノを見てしまった罪悪感で、そのまま眠っているフリをした。翌朝、母親の「あら~、サンタさん来たのね!」のコメントに「フフ、私はもう知ってしまったんだよ」と心で呟いた。▽『息子たちのサンタクロース編』:小さい頃は朝が早く来てほしいから、イブの夜は早く寝ていた。が、ある程度の年齢になると、サンタに会いたくて「リビングで寝る!」「今晩はずっと起きてる!」とか言ってくる。ある年、朝起きてクリスマスツリーの下を見ると、前の晩に置いたクッキーとミルク、一口ずつしか口をつけていない。息子たちが旦那に「何でサンタさん、ちょっとしか食べてないのかな?」と聞くと「お前たちが早く寝ないから、サンタは来るのが遅くなって、長時間放置したミルクとクッキーは不味いと思ったんじゃないの?」と、しれっと返事していた。現在17歳と15歳の息子、プレゼントは数が多い方が良いとサンタクロースに手紙を書き、ニヤニヤしながら私に渡してくる。今は、冬の記憶=金欠。(IE) |
(2020年12月1日号に掲載)

 |
宇宙への扉を開いてくれたのは、父の手作りによる天体望遠鏡。父には悪いけれど、屈折式経緯台の簡易版とは言えたものの、ファインダーは付いてないし解像度も低かった。まあまあ月面観測はできても、土星のリングをキャッチするのは無理。「宝物」と呼べない望遠鏡は子供部屋の「飾り物」となり、悲惨な末路をたどる。相撲を取っていた私と弟が望遠鏡に激突し、真っぷたつに折れた。父の逆鱗 (げきりん) に触れて2人は家の外に出された。高校1年の秋、某光学機器メーカーの工場で購入した反射式赤道儀 (口径100mm)。これこそ「宝物」。ところが、架台に選んだ鉄柱の重量がハンパなく (キャスターなし)、マンションの屋上に固定したまま動かせない (今もそのまま)。やむなく野外用のカーボン三脚も買い、観測用具とテントを自転車に括り付け、郊外に出て組み立て作業を始める。暗がりではラーメン屋台の設営に見えたらしく、酔っ払いが何度も近寄ってきた。「天体観測です」と反応すると「気取ってんじゃねぇよ!」と絡まれることもしばしば。「すいません! 閉店なんで、またあした!」と煙に巻いて、次の日は場所を変えた。星空を眺めながら深夜放送も聞いた。当時の人気DJ落合恵子さんから頂いた自筆のイラスト入り返事。これも「宝物」の一つ。 (SS)
|
 |
|
 |
▽メンコ、ビー玉、牛乳のフタなど、子どもの頃、たくさんの宝物を集めていた。溢れんばかりの戦利品をみかん箱から取り出して、得意げに見せびらかして喜んでいた。「本当に男勝りだよ。大切なモノ、お腹の中に忘れてきたんだよね」と、家族が苦笑いしていた。▽アメリカに来るとき、東京のアパートの荷物を実家の店の倉庫に置かせてもらった。「ごめんね〜。暴走族のタバコの不始末で荷物が燃えてしまったのよ」と母から国際電話があった。お気に入りのレコード、アルバム、着物、千趣会で集めた嫁入り道具など、10年間の青春の宝物がぜんぶ消えてしまった。でも、時間の経過がそうさせたのか、あまり悲しくなかった。▽「すごい豪邸だったよ。使い込んだ料理道具、銀の食器、手作りのジュエリーや洋服、すべてが彼女の宝物なんだって」と、ラホヤに住む知人の暮らしぶりを説明したら「おしゃれで繊細!? あなたにはムリでしょう。なんせ男前だから」と旦那が爆笑した。確かにムリだと思った。▽母はゲラゲラよく笑う人だった。祖父の商売が傾いて、人一倍苦労したはずなのに、磨き抜かれたユーモアのセンスを炸裂させて、周囲を元気にしてしまう不思議な力を持っていた。そして、いつの頃からか、自分も母の文化遺伝子を受け継いで、珠玉の笑いとユーモアが人生の宝物となった。(NS)
|
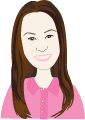 |
人によって、お金で買うことができる、手に入れられる、ビジネス、家、車、、、などは現実的な宝物になるかもしれないが、私にとって大切な宝物は「記憶」かも。母が亡くなってから、毎週土曜日に母国の台湾にいる父との “電話デート” を続けている。「昔はこれ、あれ、いろいろな人に会って、いろいろなことがあった、、、お母さんが病気の時は、、、あなたたちが子供の頃、、、パパが自分の会社を設立する前に、、、日本へ留学の時、、、昔の台湾は、、、」と、いろいろな話をお父さんから聞いていた。20歳で台湾の実家を出て、日本とアメリカでの外国生活が非常に長い私にとって、こんなに父と仲良くなれて深い話ができるのは、自分でもとても不思議に思う。昔、いつも母と話していて、あまり父と会話する機会がなく、今になって、やっと父のことが理解できたような気がする。父の記憶は私の大切な記憶になり、何とも言えない幸せを感じる。いくつ年を取っても、大切な記憶をそのまま残してほしい! いつまでも覚えておきたい! (S.C.C.N.)
|
 |
キレイな色と形の落ち葉、河原で拾った白い小石、桜貝の貝殻、自分で作った押し花のしおり、誰かからお土産でもらった星の砂の入った小瓶、お土産屋さんで売っているつるつるした紫の石、小さな珊瑚 (さんご) の付いたネックレス、祖父からのお土産の色が変わる石 (?) の付いたペンダント・・・子供の頃はいろいろな細々したものが宝物だった。それらを、誕生日に買ってもらったクマの付いたオルゴールの引き出しに入れていた。そのオルゴールは引き出しを開けると音楽が鳴り、引き出しの上に付いたクマの人形がお辞儀をする仕様になっていた。どれも大事にしていたはずなのに、いつの間にか宝物ではなくなっていた。里帰りしたとき、自分が使っていた部屋にクマのオルゴールがまだ置いてあった。うっすら埃 (ほこり) をかぶって薄汚くなったクマを懐かしく眺めた憶えがある。そのまま部屋に置いてきたあれはまだあるだろうか。今は、私にとってかけがえのない存在はやはり子供たちだ。いくつになってもずっと可愛いと思う。(YA)
|
 |
▽宝物と言えるかどうかわからないけれど、ずっと捨てられずに持っているものがいくつかある。その一つが、中学生の頃、友達と放課後の理科室で、苛性ソーダを使って葉肉を溶かして葉脈だけにしたもの。なんの葉っぱかわからないけれど、葉脈だけになった葉っぱはアート作品のようで美しい。それを木の箱に入れてずっと持っている。アメリカに引っ越してくるときも持ってきてしまった (!)。ずっとしまってあったのを娘が見つけて、その繊細な美しさに魅かれたらしく、今は彼女が持っている。母から娘に引き継がれた葉脈。飼っている猫と同じ匂いがするらしい。
▽我が家のリビングの壁に飾っている父の版画。元々は実家の玄関に飾ってあったもの。夫が気に入っているのを知っていた両親が、私たちにプレゼントしてくれた。かなり大きな作品なので、国際便で送付する手配が大変だったらしい。ニワトリと思われる鳥を抱いた人が大きく描かれたその版画。背景には地層が広がる。いも虫みたいなのもいるし、魚の骨みたいなのもある。父は何を言いたかったのかなと思いを巡らせてしまう。私たちの大事な宝物だ。 (RN) |
 |
|
 |
この世で形のないもの (例えば、心とか恋愛関係、友情関係とか) だって、壊れることは多々なのだから、まして形のあるものは、必ずと言っていいくらい壊れる、無くなる。という私の持論から、モノに対してあまり執着を持たない。高価な貴金属にも全く興味がない。心から好きになった人から贈られて、その当時は宝物のように扱っていたものも、その人と別れれば、ただのモノ。どころか、逆に嫌な記憶を思い出させる悪者と化す。物に使うお金を最小限?にくい止め、そのお金を形のないもの、思い出作りに使う。旅行である。いつか自分に問うたことがある。「私は何故に、何かに駆り立てられるように、旅行に出かけるのか」。そして辿り着いた答えが 「老いを感じ、行動の自由を失った時、ロッキングチェアにでも揺られながら、わが旅の記憶に浸って、心豊かに過ぎゆく時を楽しむ。そのための思い出作りを、今一生懸命やっているのである」と。日常の時間は記憶にはほとんど残らないが、非日常である旅行での日々はかなり鮮明に記憶にとどまる。その量が多ければ多いほど、わが老後の心は充実したものになるであろう。そう、私の宝物は、ずばり「旅の思い出」である。その記憶を薄れさせないために、今せっせと、人生で出かけた海外旅行の全記録を整理している。 (Belle)
|
 |
|
 |
タカラ、といえば! 真っ先に頭に浮かぶのが、まだまだ若かった (小さかった 笑) 頃に手にした、昭和のポップな黄色のデザインの、タカラ缶チューハイ!(笑)。衝撃的だったなー。缶の中にカクテル的な飲み物がすでに出来ていて、手軽に買えて家飲みできるなんて。でも、さすがに酒は、お宝ではないな (笑)。お宝といえば、ニッポンを代表する大泥棒、ルパン三世を思い浮かべるでしょう (笑)。お宝のある場所にルパンあり! こりゃ名作アニメだよねー。ルパン三世を知らない人でも、これは知ってるかも? 2020年ルパン関連作といえばテレビドラマ「ルパンの娘」。秘宝やお宝を探して次々と盗むんだけど、悪党が入手したお宝しか盗まず、盗むときのお決まりのセリフ「ここで会ったが運の尽き、あんたが犯した罪、悔い改めな!」で、平手でぶん殴る (笑)。これが、昭和っぽくって、ばっからしくて超オモシロい! でも、、絵画や宝石のお宝って、家に飾っておくだけでは、ご飯は食べていけないじゃない。このルパンの娘の一族は、どうやって生活してるんだろう、、と現実的なことを急に考え出しているわたしのお宝は、、ずっと戸棚に眠っている1997年製のナパバレーのシャルドネよ!(あ、白ワインね) (コレ食べらんないじゃん!笑) (・・・さすがに酒は、、お宝だった!爆)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
子どもたちに今一番大切にしている宝物は何か聞いてみた。長女は買ったり拾ったりして集めたお気に入りの石や、「Hatchimales」という小さな動物たちのコレクション。次女は大好きなお友達からもらったバースデーカードだという。聞いておいてよかった・・。どれもよく部屋のあちらこちらに散らばっているものなので、続くようなら、こっそり捨ててしまおうかと思っていたものばかりだった。私の宝物は・・なんだろう? あまり思いつかない。子どもたちが私のために描いてくれた絵やイラスト、昔、描き貯めた4コママンガ、写真などなど。どれもお金で何とかなるようなものではないが、やはり、これらは失くしたくないものかな。そういえば、私は実家の母の「宝箱」(年季が入った段ボール箱) を知っている。その中には、昔、父が海外から買ってきた香水や装飾品が入っている。たまに開けて見せてくれたが、中に入っている香水はすでに乾いており、ほとんど残っていなかった。それでも、まだ大事そうにしまっている。でも、その気持ち、少し分かる。嬉しいと勿体なくて使えないのだ。私は買ってきた服なんかも汚すのが嫌で、すぐに着ないで、ちょっと置いてから身に着ける。そんな感覚に似ているのかも。あれ、ちょっと違うか? (SU) |
(2020年11月16日号に掲載)
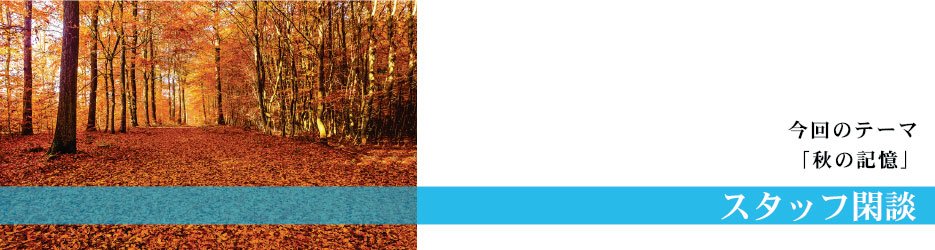
 |
三島由紀夫が割腹自決した1970年11月25日。底冷えする当日の朝、家の近くに立っていたスギの神木が倒れていた。忘れ得ぬ秋の記憶。三島が16歳で発表した小説『花ざかりの森』を読んでいた中学生の私は、その流麗な文体に感動していただけに、報道写真で彼の生首 (なまくび) を目にした時の衝撃は言葉にならなかった。魔的な死を選んだ “三島の謎” から50年。世間では、右翼思想と武士道への異常な傾倒を原点として三島の行動美学を分析しているけれど、そこが本質ではないような気がする。切腹そのものが目的だったと思う。(ここからは私の勝手な見解です) 言霊 (ことだま) の邪悪なパワーに縛られた不完全な人間は、例えば「醜い存在」というネガティブな契約を自分と交わしながら、どうにか社会と折り合いをつけ、規範を超えない善良な小市民に自らを育て上げる。一方で、森羅万象を言葉にしたい天才文士の深い欲望は、自分の流儀で死を獲得する瞬間に満たされ、完璧な表現者として軽々と社会を超えていく。冥界で『切腹』という小説を書いている三島の姿が目に浮かぶ。武士道に殉じたというより、文士道を極めた、ニーチェの言う「超人」。顕界 (げんかい) と魔界を遮断する神木が同じ日に倒壊したのも象徴的。妖気 (ようき) 漂う晩秋だった。 (SS)
|
 |
|
 |
▽「あんたは、稲刈りの時に生まれたから、ほんとうに大変だったのよ」。毎年9月になると、母のこの言葉を思い出す。農家にとって、収穫作業がピークになる秋は、猫の手も借りたいほど忙しい。でも最近は、空から畑を監視するドローン、無人のトラクター、野菜収穫ロボット、乳牛を見守るAIシステム、アルバイトを雇うアプリなど、強力な助っ人が現れて、収穫の秋が激変しているそうだ。農業がビジネスになる時代が到来している!? 「あら〜、すごいね〜」と天国の母が拍手喝采して喜んでいる気がする。▽その昔、留学生として暮らしたワシントン州東部の街では、9月になると多くの農家が風の穏やかな日を選んで野焼きをする。秋枯れの原野に火を放つと、火は風をおこして一面に燃え広がる。黄金色に輝く小麦畑が、どこまでも続く丘陵地に忽然と現われる広大なキャンパスが懐かしい。▽「春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえて冷しかりけり」。四季を感じる日本人ならではの感性は素晴しい。でも、年中常秋のカリフォルニアに長く住んでいると、季節の移ろいを情緒的にとらえるDNAがまったく機能しなくなる。春と秋の区別もつかないようでは「はかなさ」や「無常観」の感性は育たない。ますます情緒レスになっていく自分が恐い。 (NS)
|
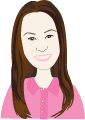 |
2年半前に入居した家のバックヤードに大きく、美しく、元気な ficus(イチジク)の木が6本もあった! フェンス側に並べてあったため、お隣さんの2階のお家は完全にカバーされ、プライバシー抜群のバックヤードはまるで公園のような感じだった。とても良かったが、樹齢40年以上の ficus の根っこがあちこちに伸びて、落葉も半端じゃない! お隣さんのプールにいつも沢山の葉が入っていた。問題を完全に解決するため、結果的に去年の秋 (10月)、お隣さんと相談した上で、木を全部カットすることになった。4〜5人グループの業者さんに頼んで、まるまる2日間も掛かった大作業! 一番暑い2日間だったので、冷たい飲み物を1日中用意していた私もヘトヘト! 終了後、お隣さんの2階建てのお家が丸見え、公園のようなバックヤードの雰囲気がなくなり、結構ショックだった! でも、木が無くなったので、地面の雑草、葉の掃除が簡単にきれいに出来て、とても助かった! 去年の秋は「木の記憶」の秋だった。 (S.C.C.N.)
|
 |
秋の記憶といえば、やはり四季が分かりやすい日本で過ごした秋が思い浮かぶ。▷たとえば、秋の木々。真っ赤に染まった紅葉。黄色く色づいた扇のようなイチョウの葉っぱ。他にもオレンジ、黄色、赤色、緑色の落葉樹。きれいな色と形の落ち葉を拾い集めるのも楽しかった。子供の頃はどんぐりもよく拾っていた。拾ったどんぐりはコマにしたり、ままごとに使ったりしていた。▷それから、秋の食べ物の味覚と香り。◎幼い頃に母がフライパンで炒 (い) ってくれた栗。香ばしくて美味しかった。◎秋になると祖母から届いていた箱いっぱいの甘い柿 (たまに渋いのに当たる)。置きすぎると最後はべちゃっとゼリーみたいになったのを、母が好んで食べていた。◎リンゴを煮ているときのシナモンとお砂糖、バター、ブランデー少々の香り。家に常備されていたリンゴを煮てアップルパイを作ったら、母と妹に好評で、わが家の秋の恒例となった。◎夕食にしょっちゅう出てきたサンマの塩焼き。当時はうんざりしていたのに、今は無性に食べたくなる。 (YA)
|
 |
子供の頃、秋の森が好きだった。蒸し暑い夏と違って、蚊もいなくなり、涼しく過ごしやすい。そして、黄色やオレンジに色づいた木々の葉が美しい。アケビや栗など、食べられるものを探しに行くのも楽しみだった。森の中の広場で、自家菜園で採れたさつまいもを焼き芋にしたり、巨大鍋で豚汁を作ったりして、みんなでワイワイと食べたのも楽しい思い出。小さな苗木から見上げるような大木に育った銀杏の葉が、息をのむほど美しい黄色に輝くのも秋。鼻がもげそうな異臭を放つ銀杏の実を拾い集めたっけ。▽実家のある牛久 (茨城県) はサツマイモの産地。美味しい干し芋が出回るのも秋。子供の頃は食べ慣れたおやつでしかなかったけれど、アメリカに住むようになって、美味しい干し芋はそう簡単に手に入らない。実家の父が毎年、何袋もの干し芋をまとめて郵送してくれるのが楽しみの一つになっている。▽娘が生まれてから、アメリカの秋の行事が一気に身近になった。夫婦二人だけの時には行ってみようとも思わなかったパンプキンパッチ。お友達ファミリーと一緒にいろいろなパンプキンパッチに行ったのも、秋の楽しい思い出。子供がいると、ないことにできないハロウィン。仮装してトリックオアトリートに出かけた頃が懐かしい。 (RN)
|
 |
|
 |
食欲の秋、読書の秋、紅葉の秋・・秋の代名詞は多々あるが、私にとって、新潟県は津南 (つなん) の山奥、日本一の豪雪地帯と言われる秋山郷の紅葉が一番の秋の記憶である。そこの秋が強烈な記憶として私の脳裏に留まる半年ほど前、私は東京で異業種交流会の “ログハウスを建てる” という会に誘われて参加した。会員30人を募り、各人30万円の出資で、津南にログハウスを自らの手で建てよう、という大掛かりなプロジェクト。まず、秋山郷をその建設予定地に定め (土地は村から無償で借り受けた)、ログをカナダから輸入。基礎工事こそ業者に依頼したが、後は全て自分たちで組み立てる、という壮大な計画だった。メンバーは三菱自動車の社員を中心に職業は多々。7月後半より、東京から3時間半ほどの目的地に、私は皆の食事係として毎週末通うこと3か月。遂に我々のログハウスが完成。10月になると、山肌が徐々に色づいて毎週の変化が車窓から見て取れる。ログが完成する週、それはそれは人生初の見事な、見事な紅葉だった。完成祝賀会には関係者約80人を招いて、私が3日がかりで作ったインド料理を振る舞った。物音一つしない山奥の一軒家の静寂の中で一人寝泊まりして、一日中料理に明け暮れた3日間も特別な秋の記憶として残っている。 (Belle)
|
 |
|
 |
秋の印象は薄いけど、思い出した! 秋はめちゃ暑くもなく寒くもないから、キャンプ行ったわー! ジョシュアツリーでキャンプ場が満杯だったから、そのヘンの砂漠で野営したときのこと。周りはだっれもいない、ぽつんと我々のテントのみ。裸で歩こうが、トイレが土の上だろうが、お構いなし (笑)。朝になっても誰もいない。することもないし (笑) もう帰りましょう、ってことで、車を動かしたら、タイヤが砂にはまって動けなくなっちゃった。パリ・ダカ (パリ・ダカール・ラリー) 状態よ (笑)。AAAに電話したら、砂漠に通常の牽引車は来れない、と。絶体絶命〜。そこにいてもしょうがないし、助けを求められる人がいそうな方向へ果てしなく砂漠を歩き出した (ドラマみたい〜 笑)。でも、電波も弱く、Google Map もない。昼間の砂漠は暑い、日陰もない、歩いても誰もいない (涙)。もう、私たちダメなの? と思っていたら、車が来た! ヒッチハイクってもんじゃあないわよ! 両手を広げて立ちはだかり、車を停めた (笑)。かなり必死 (笑)。その人の車とロープで砂から車を引っ張り出してもらい、脱出成功! 達成感に満ちて、頭の中では「情熱大陸」のバイオリンの音が鳴りっ放し (笑)。秋の記憶=葉加瀬太郎さん、、 のグルグルパーマ (そこ?笑!)。(りさ子と彩雲と那月と満星が姪)
|
 |
|
 |
今月末で上の息子は17歳になる。2003年、生まれたての赤ちゃんをどう扱っていいのか分からず、ナースに「家に帰りたくない!」と泣いて駄々をこね、保険がきくギリギリの時間まで病院にへばりつき、自分はとんでもないことをしてしまったと、本気で考えるほどに不安だった。旦那は翌日から仕事。家で赤ちゃんと二人きり。一日に何十回も、息をしているか確認のため、他のことが全く手につかない。赤ちゃんが泣けば私も一緒に泣き、限りなく精神的に不安定・・のところに、何と山火事が起きた! ミラメサに住んでいる私。お隣のスクリプスランチが燃えている! 太陽は煙のおかげで不気味な色になり、空は入道雲のような黒い煙がモクモク。外は灰が雪のように降っている。母性本能が働いた私。「この子を守らなければ・・」。避難するために荷物を詰め始めた。そんな私に、旦那は頭が狂った人を見るような視線を送る。そして、新生児1週間目の検診。「この子に灰の空気を吸わせてはいけない!」 と、病院の駐車場では車から建物まで猛ダッシュ! そんな私に医者は「こういう状況で、無理に連れて来なくても良かったんだけどね〜」と。私が狂人と化した、ひと秋の記憶。 (IE) |
(2020年11月1日号に掲載)