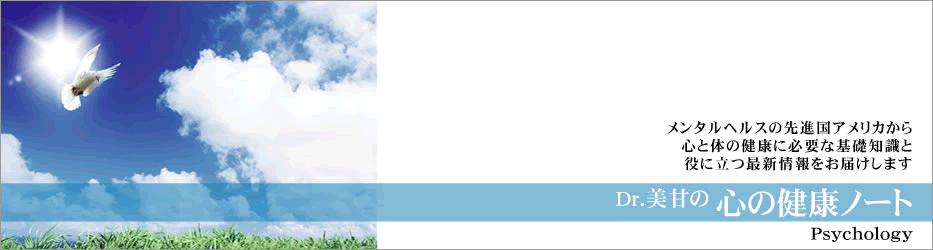 |
|||
.jpg) |
美甘 章子 臨床心理医。医療や教育現場て幅広く臨床経験を積み、みなと学園コンサルタントも務めた。 エグゼクティブ・コーチング、スポーツ心理、精神科薬相談、心理療法、精神鑑定、教育心理アセスメント、発達障害相談など日・欧・北中南米などグローバルに従事。 「8時15分 ヒロシマで生きぬいて許す心」著者。 平和教育団体San Diego-WISH代表。 |
||
 |
|||
|
認知症と家族 |
|||
|
人ごとではない家族の認知症 2014年の九州大学による厚生労働省特別研究の結果をまとめた内閣府の発表(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html)によると2012年には65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症であったが、2025年には約5人に1人になると推計されています。 アメリカに住む日本人の中高年世代は、日本に住む高齢者の親のことを心配しつつも長期間日本に帰って世話をするわけにもいかず、兄弟や親戚に頼る負い目を感じながらも何かできることはないかと悩んでいる人も多いでしょう。 中には、才能を生かした有望なキャリアを諦めて日本に帰って高齢の親の介護をする人もいますが、それを本望としない親もいるでしょう。
老・老介護 2018年11月に日本でプレミアした信友直子監督によるドキュメンタリー『ぼけますからよろしくお願いします』(bokemasu.com)は、TVディレクターであった信友監督がスーパー主婦だった80代の母の異変に気付き、1人娘かつディレクターとしての視点から、認知症と診断された母と90代になって初めて家事と妻の介護を始めた大正生まれで昔気質の父の間の思いがけない深い絆と自身を含んだ3人家族の泣き笑いを正面から映し出した感動的作品です。 漫画・アニメ『この世界の片隅に』の舞台となった広島県呉市出身の信友監督は、実は私の高校時代の同級生なのですが、監督のメッセージには私が普段から患者さんやクライエントに発見・理解して頂きたいと尽力しているパースペクティブと共通した点がたくさんあり、日本人だけでなく世界の多くの人たちに是非観て頂きたい作品です。
不幸の中の気づきと喜び 信友監督はインタビュー(『ぼけますからよろしくお願いします』公式プログラム)の中で、「母が認知症になる前はあまり話をしたこともなかった父とのコミュニケーションと連携が増し、父は実は母思いでいい男なんだなとわかった」ということを認知症が与えてくれた贈り物かもしれないと述べています。 また、それまでは母に色々面倒を見てもらう側だった自分が、自身の能力低下を嘆きながらも喜怒哀楽の感情表現が増えた母を愛らしいと思い、自分のできることのベストをしてあげたいと思う心底から湧き出る暖かい気持ちも表現されています。 東京で仕事に忙殺される監督が仕事を辞めて広島県呉市に帰って母の介護をするべきか悩んでいた際、父が「できる間はわしが(介護を)する。あんたはあんたの仕事をしんさい」と言う場面では、家庭の事情から帝國大学進学を諦めた勉強好きの父が、娘(東京大学卒)には自分達のことより自身の才能を生かして世の中に貢献する仕事を精一杯やって欲しいと言う気持ちが現れています。
介護サービスの利用 日本の高齢者家族には、介護サービスについてよく知らない人が多く、知っていたとしても「家に他人を入れるのは気兼ねする、主婦の恥」などと感じてなかなか受け入れられない気持ちが強くあります。 中高年の子供達が日本国内、または同じ都道府県内に住んでいたとしても、人生100年と言われる現代に認知症の親の介護を家族だけで賄うのは現実的に無理があります。 アメリカでは常識的なことですが、日本ではサポートが必要な親に介護施設に入ってもらうのは、伝説的な「うば捨て山」のように親を見捨てる罪悪感が強すぎて無理と感じる人もいます。 高齢者の割合が増え続ける社会では、昔のように家族だけで高齢者の世話をすると言うのは無理なことが多く、高齢者の親の世話はするが、そのストレスで中高年の子どもの方が抑うつになったり夫婦の仲が険悪になったり、 他の兄弟を恨んだり、自分の子どもたちに当たったりしてしまう例がたくさんあります。 子どもが人類の宝であるように、これまで色々な形で貢献や知恵を与えてきた高齢者も人類の宝と言えます。 その宝を大切にするのは個々の家族だけの責任ではなく、社会全体の責任であり、家族・親戚・友人、介護のプロ、ケースワーカー、医師、カウンセラー、介護施設など借りられる手は全部借りてチームで取り組む課題なのです。
|
|||
 |
|||
| 「心の健康ノート」シリーズでは、主な心の病気やストレスの表れ方、心理療法、精神科薬、人との接し方、家族関係、職場でのメンタルヘルス等について、心と体の健康のために、ぜひ皆さんに正しく理解して頂きたいことを紹介していきたいと思います。 | |||
| (2019年1月16日号掲載) | |||
